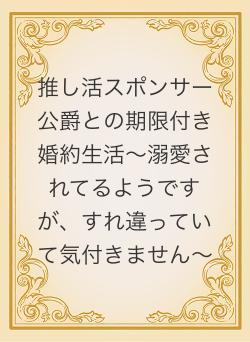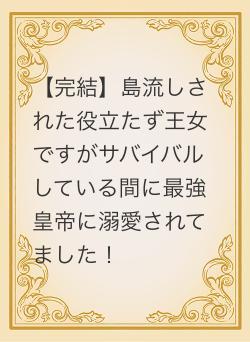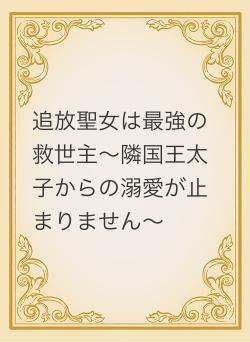手のひらにじんわりと汗が滲んでいく。
運悪くあのブティックで買い物をしていた令嬢がいたのだと気づいた時にはもう何も言葉を発せなくなっていた。
「シュリーズ公爵を敵に回すなんて……ねぇ?」
「まさかいきなり殴りかかるなんて、非常識にもほどがありますわ。信じられない」
「ああ、王都にはもうエディット様の入れるお店はないんだったかしら!」
「……お可哀想に。わたくしのお古なら差し上げますわよ」
「アハハ、ティンナール伯爵もあの年でお盛んなこと……娼館に入り浸るなんて、よほど屋敷の居心地が悪いのかしら」
「──ッ!」
令嬢たちはティンナール伯爵家の噂をすべて知っていたのだ。
「フフッ、おかしい! この際だから言うけれどエディット様、令息たちからなんて言われているか知ってる? 傲慢令嬢ですって!」
「ご自分をアピールする前に婚約者がいるかどうかくらいは確かめた方がいいわよ? 顔のいい男には見境なくなんて、発情した動物じゃあるまいし」
「よくお茶会に顔を出せたわね! あと何回参加できるのかしら」
「………………」
そこからはよく覚えていない。
けれど、落ちるのは一瞬だった。
これが夢だったらいいのにと思った。
涙を流さなかったのは意地だ。
馬車の中では叫び声を上げながら、思いきり椅子を叩いていた。
それでも気分は晴れることはない。
(いつかっ、お前たちのその顔をヒールで踏み潰してやるわ!)
運悪くあのブティックで買い物をしていた令嬢がいたのだと気づいた時にはもう何も言葉を発せなくなっていた。
「シュリーズ公爵を敵に回すなんて……ねぇ?」
「まさかいきなり殴りかかるなんて、非常識にもほどがありますわ。信じられない」
「ああ、王都にはもうエディット様の入れるお店はないんだったかしら!」
「……お可哀想に。わたくしのお古なら差し上げますわよ」
「アハハ、ティンナール伯爵もあの年でお盛んなこと……娼館に入り浸るなんて、よほど屋敷の居心地が悪いのかしら」
「──ッ!」
令嬢たちはティンナール伯爵家の噂をすべて知っていたのだ。
「フフッ、おかしい! この際だから言うけれどエディット様、令息たちからなんて言われているか知ってる? 傲慢令嬢ですって!」
「ご自分をアピールする前に婚約者がいるかどうかくらいは確かめた方がいいわよ? 顔のいい男には見境なくなんて、発情した動物じゃあるまいし」
「よくお茶会に顔を出せたわね! あと何回参加できるのかしら」
「………………」
そこからはよく覚えていない。
けれど、落ちるのは一瞬だった。
これが夢だったらいいのにと思った。
涙を流さなかったのは意地だ。
馬車の中では叫び声を上げながら、思いきり椅子を叩いていた。
それでも気分は晴れることはない。
(いつかっ、お前たちのその顔をヒールで踏み潰してやるわ!)