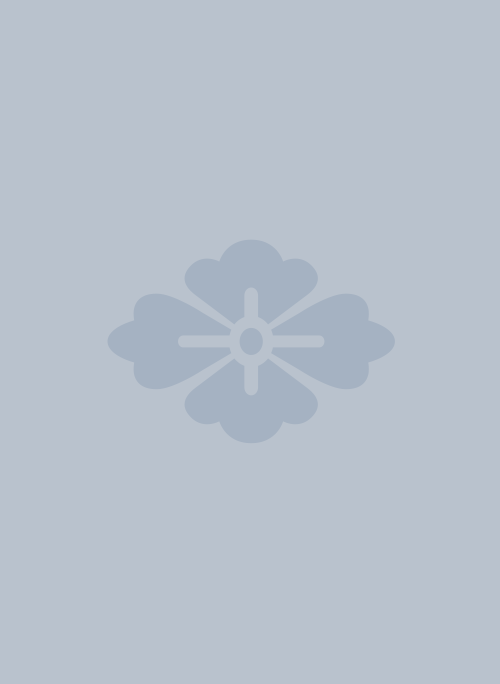新選組に住み込みで働く日々が続く中、私は徐々に屯所の生活に慣れてきていた。最初は不安だったけれど、雑用係としての役割が決まったことで、少しずつ仲間たちとも顔を合わせるようになり、そこに温かさも感じることができるようになった。
けれども、沖田総司のことだけはどうしても気になって仕方がなかった。彼は、どこか天然でふわふわとした雰囲気を持っていて、まるで何もかもを気にしないように振る舞っているが、その目にはどこか警戒心が漂っているように感じられる。
「お疲れ様、沖田さん。」
私はその日、昼食を作り終えてから台所を片付けていた時、沖田に声をかけられた。振り返ると、そこには彼が立っていて、少し照れくさそうに笑っていた。
「うん、お疲れ様…だね。」
沖田はそう言って、ふわふわとした感じで空を見上げながら歩いてきた。私が感じていた警戒心と、彼の表情が微妙に一致していた。それでも、彼はすぐにそれを気にしないように、またぼんやりとした様子で言った。
「ご飯、すごくおいしそうだね。」
そう言って、私の作った料理に目を向ける沖田。彼の無邪気な言葉に、少しだけ胸が温かくなる。しかし、それが私が知っていた沖田総司とは違うことを感じさせる。
「ありがとうございます。でも、沖田さんもよく食べているんですね。」
少し気まずさを感じて、私は別の話題に持ち込もうとした。沖田はその言葉を聞いて、ふわりとした笑顔を見せる。だが、その笑顔はどこかよそよそしく、まるで昔の記憶が薄れてしまったかのようだった。
「うん、食べるの大好きなんだ。あれ、でも、梨花ちゃんはよく料理してくれるんだね、ありがとう。」
彼の言葉はすぐに浮かぶような軽さで、でもそこにはどこか遠慮と警戒のようなものが感じられた。沖田総司は、私に対して何かしらの違和感を抱いているのかもしれない…でも、それが何なのか、私はまだはっきりとわからなかった。
「…あ、うん。昔から、ちょっとお料理が得意で。」
言葉に詰まりながらも、私は笑って答える。沖田はそれにうん、と頷くと、少しだけ後ろを向いてからまたぼんやりと歩き出す。
「じゃあ、俺、ちょっと外で訓練してくるね。」
そう言って、沖田はそのまま去って行った。その後ろ姿に、私の心はまたざわざわと揺れる。幼い頃の沖田は、もっと私に対して自由に接していたはずなのに、今はまるで誰かのように遠く感じられる。
その日は、沖田との距離がますます広がった気がした。ふわふわとしたその態度の裏に隠れた警戒心、そして少しだけ不安げな表情。私の目には、彼が記憶を失ったわけではなく、ただ過去のことを遠くに感じているだけのように映った。
「どうして…」
思わず口に出てしまったその言葉に、私は自分でも驚いた。沖田に対して、何かもっと深い絆があると感じていたのは確かだ。でも、彼があの頃の私を覚えているのか、覚えていないのか、それすらもわからないままだった。
その後、私はしばらくその気持ちを引きずりながらも、新選組の仕事を続けていった。沖田との距離が開いたように感じる一方で、どこかで彼が再び過去を思い出してくれるのではないかという淡い期待も抱きながら。