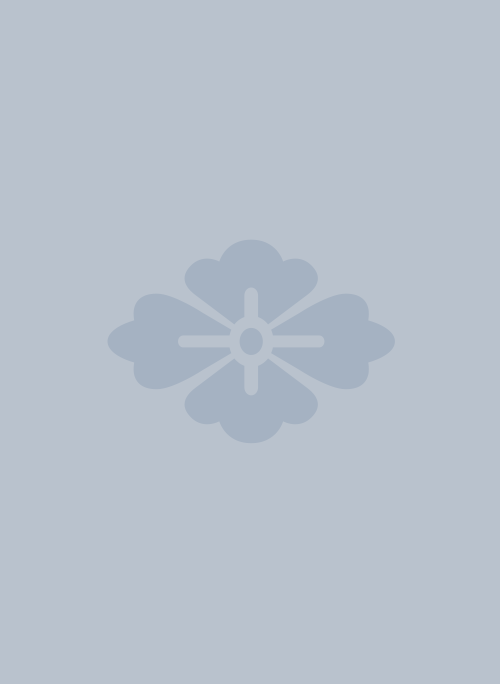奉行所に預けられてから、幾日が経ったのか。
沖田総司は牢の隅に座り、じっと膝を抱えていた。
寒さや空腹よりも、周囲から向けられる疑いの目が辛かった。
牢の外では、役人たちが総司をどうするべきか話し合っていた。
「どうする、あの子?」
「毒を盛った証拠はないが……不自然すぎる」
「そもそも、あの年の子が家族全員を毒殺できるとは思えん」
「だが、毒を口にして生きているのは、どう説明する?」
総司はただ静かに、その会話を聞いていた。
証拠がない以上、すぐに処刑されることはないだろう。
だが、このままではずっと「犯人」として牢に閉じ込められたままだ。
──僕は、本当におかしいのか?
総司はふと、自分の体に意識を向けた。
家族と同じものを食べたのに、自分だけが生き残った。
普通の人間なら死ぬはずの毒が、なぜか自分には効かなかった。
思い返せば、以前にも不思議なことがあった。
子供の頃、誤って腐った魚を口にしても腹を壊さなかった。
茶屋で出された苦いお茶を飲んだ時、周りの人は苦しんだのに、自分は平気だった。
──もしかして、僕の体は毒が効かないのか?
そんなはずはない、と思いながらも、総司は自分の体質について考え始めた。
*
その日の夜、牢の前にひとりの役人が現れた。
灯りを手にしたその男は、総司を見下ろして言った。
「お前、試してみる気はあるか?」
「……試す?」
役人は懐から小瓶を取り出し、牢の格子の間から差し出した。
それは青黒い液体が入った瓶だった。
「これは強力な毒だ。普通の人間なら、舐めるだけで喉が焼ける」
総司は小瓶をじっと見つめた。
「これを……僕に飲めって言うの?」
「ああ。もし本当にお前が毒に耐性があるなら、何も起こらないはずだ」
役人の目は、まだ疑念を捨てきれないようだった。
総司は迷った。
だが、このまま疑われ続けるくらいなら、確かめてしまった方がいい。
覚悟を決め、小瓶を受け取る。
蓋を開けると、鼻をつく刺激臭が広がった。
──飲めば、死ぬかもしれない。
だが、総司は迷わず一気に飲み干した。
*
役人は息を呑んだ。
「おい……大丈夫か?」
総司は喉を鳴らしながら飲み下し、ゆっくりと息をついた。
「……なんともない」
役人は驚き、まじまじと総司を見つめる。
「嘘だろ……?」
普通なら、激痛に転げ回るはずだ。
だが、総司はただ平然と立っている。
むしろ──
「あれ……なんだか、少し元気になった気がする」
総司は自分の体を見下ろし、不思議そうに呟いた。
さっきまで感じていた倦怠感が消え、頭が冴えている。
むしろ、毒を飲んで体調が良くなるなんてことがあるのか?
「馬鹿な……」
役人は呆然とした。
この時、初めて人々は気づいた。
──沖田総司は「毒が一切効かない」異常な体質を持っている。
*
それから数日後、総司は牢から解放された。
奉行所の者たちは、「特異体質である以上、毒殺犯ではない」と判断したのだ。
だが、周囲の目は変わらなかった。
「アイツ、人間じゃないんじゃないか?」
「毒を飲んで生きてるなんて、妖怪みてぇだ……」
「気味が悪い……」
誰もが総司を恐れ、距離を置くようになった。
生き残ったことが、罪のようだった。
総司は一人、冷たい江戸の町を歩いていた。
家はなくなり、家族もいない。
どこへ行けばいいのかも分からない。
だが、この異常な体がある限り──
自分には、普通の人間としての居場所はないのかもしれない。
沖田総司は牢の隅に座り、じっと膝を抱えていた。
寒さや空腹よりも、周囲から向けられる疑いの目が辛かった。
牢の外では、役人たちが総司をどうするべきか話し合っていた。
「どうする、あの子?」
「毒を盛った証拠はないが……不自然すぎる」
「そもそも、あの年の子が家族全員を毒殺できるとは思えん」
「だが、毒を口にして生きているのは、どう説明する?」
総司はただ静かに、その会話を聞いていた。
証拠がない以上、すぐに処刑されることはないだろう。
だが、このままではずっと「犯人」として牢に閉じ込められたままだ。
──僕は、本当におかしいのか?
総司はふと、自分の体に意識を向けた。
家族と同じものを食べたのに、自分だけが生き残った。
普通の人間なら死ぬはずの毒が、なぜか自分には効かなかった。
思い返せば、以前にも不思議なことがあった。
子供の頃、誤って腐った魚を口にしても腹を壊さなかった。
茶屋で出された苦いお茶を飲んだ時、周りの人は苦しんだのに、自分は平気だった。
──もしかして、僕の体は毒が効かないのか?
そんなはずはない、と思いながらも、総司は自分の体質について考え始めた。
*
その日の夜、牢の前にひとりの役人が現れた。
灯りを手にしたその男は、総司を見下ろして言った。
「お前、試してみる気はあるか?」
「……試す?」
役人は懐から小瓶を取り出し、牢の格子の間から差し出した。
それは青黒い液体が入った瓶だった。
「これは強力な毒だ。普通の人間なら、舐めるだけで喉が焼ける」
総司は小瓶をじっと見つめた。
「これを……僕に飲めって言うの?」
「ああ。もし本当にお前が毒に耐性があるなら、何も起こらないはずだ」
役人の目は、まだ疑念を捨てきれないようだった。
総司は迷った。
だが、このまま疑われ続けるくらいなら、確かめてしまった方がいい。
覚悟を決め、小瓶を受け取る。
蓋を開けると、鼻をつく刺激臭が広がった。
──飲めば、死ぬかもしれない。
だが、総司は迷わず一気に飲み干した。
*
役人は息を呑んだ。
「おい……大丈夫か?」
総司は喉を鳴らしながら飲み下し、ゆっくりと息をついた。
「……なんともない」
役人は驚き、まじまじと総司を見つめる。
「嘘だろ……?」
普通なら、激痛に転げ回るはずだ。
だが、総司はただ平然と立っている。
むしろ──
「あれ……なんだか、少し元気になった気がする」
総司は自分の体を見下ろし、不思議そうに呟いた。
さっきまで感じていた倦怠感が消え、頭が冴えている。
むしろ、毒を飲んで体調が良くなるなんてことがあるのか?
「馬鹿な……」
役人は呆然とした。
この時、初めて人々は気づいた。
──沖田総司は「毒が一切効かない」異常な体質を持っている。
*
それから数日後、総司は牢から解放された。
奉行所の者たちは、「特異体質である以上、毒殺犯ではない」と判断したのだ。
だが、周囲の目は変わらなかった。
「アイツ、人間じゃないんじゃないか?」
「毒を飲んで生きてるなんて、妖怪みてぇだ……」
「気味が悪い……」
誰もが総司を恐れ、距離を置くようになった。
生き残ったことが、罪のようだった。
総司は一人、冷たい江戸の町を歩いていた。
家はなくなり、家族もいない。
どこへ行けばいいのかも分からない。
だが、この異常な体がある限り──
自分には、普通の人間としての居場所はないのかもしれない。