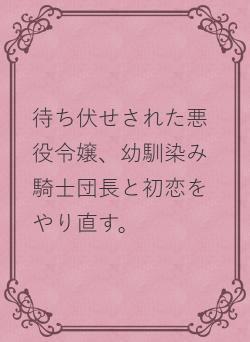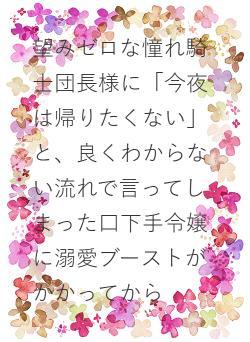そして、ようやく外へ出ることを許されたウィリアムの監督責任はエレイン様にあり、私は婚約者としてそんな彼の動きを監視する役割を担っている。
帰城した私たちはエレイン様に遠出した時にウィリアムは、私を庇って傷を負ってしまったと報告していたのだ。
「あら……ウィリアム様。確かにエレイン様より叱責を受けましたが、あれは落ち込むようなものではありません」
「は? どういうことだ?」
ウィリアムはエレインから厳しい叱責を受けた私が、平然としているのが不可解らしい。
「あれは、双方の立場上、必要なやりとりだったのです。エレイン様とて私を庇いウィリアム様が怪我をしたことは把握してらっしゃいます。心から私が悪いと、思っている訳ではありません。ですが、あの方の立場上、王太子たる弟王子の身体に傷を付けてしまい、私を叱らない訳にはいかずに……あの方は、ああいったお叱りを」
「まあ……そうだろうが、俺ならばあのように姉上に叱られれば、落ち込んでしまうだろう。そう思ったからな」
帰城した私たちはエレイン様に遠出した時にウィリアムは、私を庇って傷を負ってしまったと報告していたのだ。
「あら……ウィリアム様。確かにエレイン様より叱責を受けましたが、あれは落ち込むようなものではありません」
「は? どういうことだ?」
ウィリアムはエレインから厳しい叱責を受けた私が、平然としているのが不可解らしい。
「あれは、双方の立場上、必要なやりとりだったのです。エレイン様とて私を庇いウィリアム様が怪我をしたことは把握してらっしゃいます。心から私が悪いと、思っている訳ではありません。ですが、あの方の立場上、王太子たる弟王子の身体に傷を付けてしまい、私を叱らない訳にはいかずに……あの方は、ああいったお叱りを」
「まあ……そうだろうが、俺ならばあのように姉上に叱られれば、落ち込んでしまうだろう。そう思ったからな」