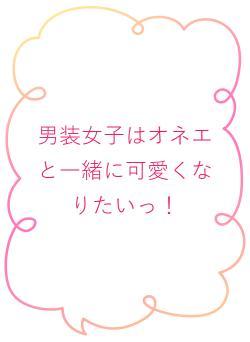「ゴミはみんな、きちんと持って帰るんだぞ」
担任の池田先生に言われて、お弁当やお菓子のゴミを、あらかじめ持ってきていたビニール袋に入れて、リュックにしまう。
遠足の時間が終わって、みんな山をおりて帰る準備をしているところだった。
「あれ? 鬼丸くんは?」
アタシは、クラスメイトの鬼丸くんがいなくなっていることに気づいたのだ。
鬼丸虎鉄くんは、六年一組ではいたずらっ子として知られている。
教室のドアに黒板消しをはさんで、ドアを開けた子がチョークの粉まみれになってしまうのをたびたび見かけた。
先生たちも手を焼く厄介な生徒として、学校では有名だ。
「私、探してきますね。みんなは、ここから動かないで」
曜子先生が自ら名乗り出て鬼丸くんを探しに行った。
……ということは、もしかしたら……。
「曜子先生、アタシも行きます!」
アタシは曜子先生を追って、山道に入ったのである。
***
「こころちゃんまで、ついてこなくて良かったのに」
「保健委員ですから、鬼丸くんがケガしてたら大変だし」
アタシはそんな言い訳を並べたけど、実のところ、クラスに迷惑をかけてばかりの鬼丸くんをそこまで心配していない。
「……これ、オバケ案件ですか?」
「かすかに妖気……オバケの気配を感じるわ」
曜子先生は難しい顔をしていた。
「ただ、山にオバケなんていくらでもいるから、なんとも。鬼丸くん、無事だといいんだけど……」
「先生は、鬼丸くんの居場所に心当たりが?」
だって、曜子先生は迷いなく、どこかを目指して歩いている。
「ええ、まあ。鬼丸くんがイタズラするだろうなって場所はなんとなく」
鬼丸くんは当然、曜子先生にもイタズラをしたことがあった。
ただ、曜子先生のほうが一枚上手だ。
たとえば、黒板消しを挟んだ教室のドアに気づいた曜子先生は、なかなか教室には入らなかった。
早く罠にかかれ~とジリジリしていた鬼丸くんに、曜子先生が「家庭科実習で作ったクッキーがあるわよ」とわざとクッキーの香りを教室の中に漂わせる。
食いしん坊の鬼丸くんはドアを開けてしまって、逆にチョークの粉まみれになってみんなで大笑いしたこともあったっけ。
よく考えたら、キツネって人を化かすこともあるイタズラの名人だ。
そんな曜子先生にイタズラで勝負を挑んだ鬼丸くんがおバカなのだ。
「……ここじゃないかしら」
曜子先生は、山を少しおりたところで立ち止まった。
「ここって、山に登る途中で通った場所ですよね」
「そうね。それに、鬼丸くんなら、いかにもイタズラしそうでしょう?」
そこにあったのは、なにかをまつっている祠。
山を登ったときには、おモチがお供えされていたけど、それがなくなっている。
もしかしたら、食いしん坊の鬼丸くんが食べちゃったのかもしれない。
さらに大変なことに、祠に貼られていたはずの御札が、ビリビリに破かれて剥がされていた。
「まさか、鬼丸くんがこれを?」
「予想的中。これは厄介ね……」
曜子先生は、ふうとため息をつく。
どうやら、鬼丸くんは、この祠にまつられていた『なにか』にさらわれてしまったらしいのだ。
曜子先生は、祠に顔を近づけて鼻をクンクンさせた。
「こっちね。行きましょう」
まるで警察犬みたいに、匂いをかぎながら山の中を進む。
アタシは木の根っこに足を取られないように、必死に曜子先生のあとを追いかけた。
やがて、アタシたちは山の中にある、巨大な木にたどり着く。
それは山の中心にどっかりと根を張って、樹齢五百年はありそうだった。
木の中には空洞があり、『なにか』が住むにはぴったりだろう。
「鬼丸くん! そこにいるの?」
曜子先生が木の空洞を覗き込みながら声を掛ける。
「……いた!」
先生が指差すほうを見ると、木の空洞の中に、鬼丸くんがぐったりとしていた。
どうやら眠っているようだけど……。
「オイラの獲物になにか用かい? 妖怪だけに、なんちってな」
突然、男の人の声が聞こえた。
曜子先生はアタシをかばって身構える。
「おいおい、そんなに警戒するなよ」
「姿を見せなさい!」
「さっきからお前さんたちの頭上にいるぜ」
すると、声の主が木の上から逆さまにぶら下がって、その正体を現した。
アタシは「ひえっ」と悲鳴を上げる。
その男は――下半身が蛇だったのだ。
「蛇神、ってやつね」
「そういうアンタは、なんだかケモノくさいなあ」
蛇神はノンキな口調で笑っている。
しかし、口からはシューシューと細長い舌が……。
アタシは蛇が苦手だ。
一瞬、曜子先生に任せて、ついてこなければよかったと後悔してしまった。
でも、なんとか勇気をふりしぼって、ガクガクと震えるひざを叩く。
その間にも曜子先生と蛇神との会話は続いていた。
「そこの子どもは私の大切な生徒よ。返して」
「生徒? ふうん、アンタ、先生やってるのかい。そんなケモノの匂いをさせて」
「ケモノ」呼ばわりされて、曜子先生はだいぶ気が立っているらしい。
チェシャ猫に襲われたときと同じ、木々がざわざわと先生に恐れをなすような感覚がある。
先生の髪は、毛先から透き通るような金色に変わっていき、キツネの耳としっぽが生えていく。
蛇神はそんな先生の姿を見ても、「へえ」と言うだけで、特に驚いた様子も見せなかった。
「子どもを返さないなら、無理やり取り返すけど?」
「まあ、そう言いなさんな。オイラもほとほと参ってるんだよ」
手から生えたするどい爪を見せつける曜子先生に対して、蛇神はなんとも思ってなさそう。
「いやな、オイラはさっき目覚めたばっかなんだよ。そこのチビスケが祠の御札を剥がしちまったもんだから」
シュルシュルと蛇の下半身をたくみに動かして、逆さまの状態から木をつたい、木に巻き付く形でおりてきた蛇神は、木の空洞の中で眠っている鬼丸くんを親指で指し示す。
「それで、お腹も空いてんのにチビスケがお供え物のおモチも食っちまったってわけよ。こうなったら、それなりの『落とし前』が必要だよなあ?」
アタシには「落とし前」という言葉の意味がよくわからなかったけれど、あまり良くないことだというのは、なんとなくわかった。
「それで、鬼丸くんを食べようってわけね」
「た、食べる!?」
アタシはぎょっとしてしまった。
こんな木に巻き付くほどの大きな蛇神に食べられたら、鬼丸くんなんてぺろりと丸呑みにされてしまう。
「子どもを食べられるのは困るわ」
「でも、仕方ないんじゃねえかなあ。バチ当たりなことをするのが悪いんだぜ」
曜子先生と蛇神、二人の間にはバチバチと火花が散っていた。
このままじゃ、二人は争いを始めちゃう。
「ま、待って!」
そこへ、アタシが思わず割り込んだ。
「蛇神さん、お腹が空いてるんだよね?」
「そうだけど?」
「じゃあ、アタシのお弁当分けてあげる! 食べきれなくて余ったおにぎりがあるの」
アタシはリュックの中を探って、ラップに包まれたおにぎりを差し出す。
「これを、あなたへのお供え物にする。だから、鬼丸くんのことは許して!」
アタシは、おそるおそる蛇神におにぎりを渡して、またひゅっと曜子先生の後ろに走って戻った。
蛇神は、渡されたおにぎりをじっと見つめて、手の中で転がしている。
「いいのかい、お嬢ちゃん。オイラにこれをくれるのかい?」
「鬼丸くんは、女の子のスカートをめくったり、本当にしょうもないことばっかりするけど、それでも蛇神さんに食べられるのはダメ!」
アタシは勇気を出して、蛇神をにらみつけるように、じっと見つめた。
曜子先生も蛇神も、あっけにとられたように、アタシを見ている。
やがて、蛇神は「あっはっは」と笑った。
曜子先生も争う気をなくしたみたいで、髪の色も黒に戻り、キツネの耳やしっぽも消えていたのだ。
「いや、こりゃまいったね。まさかこんなちっちゃな人間の女の子に仲裁されちまうとは」
蛇神は自分の手で額をぴしゃりと叩いて、しばらく笑っていた。
「ありがとよ、お嬢ちゃん。このおにぎりは、ありがたくいただいておくよ。いや、しかし気に入っちまうな。山をおりて、お嬢ちゃんについていこうかね?」
「そ、それは困ります……」
「わかってる、冗談だ」
ケラケラと笑って、蛇神は「じゃあ、そのチビスケは先生に預けるよ」と曜子先生に言い残し、しゅるしゅると蛇の下半身を動かして、山の奥に消えていったのだ。
曜子先生はすぐに鬼丸くんのもとに駆け寄って、彼の手首を持ち上げる。
そして、ホッと息をついた。
「……よかった、脈はある。ケガもしてないみたい」
それを聞いて、アタシもホッとしたのだ。
曜子先生が気絶したままの鬼丸くんをおんぶして、みんなのところへ戻ると、先生も生徒もみんなびっくりしていた。
曜子先生は「鬼丸くんは木の空洞の中で寝ていて、ケガもしていない」と説明して、みんな笑い話として納得してくれたのだ。
でも、鬼丸くんは目を覚ましたあと、「みんなを心配させた」と池田先生にこっぴどくしかられてしまったのだった。
これで、鬼丸くんがこりてくれればいいんだけど、彼はイタズラが生きがいみたいな男の子なので、難しいかもしれない。
アタシがリュックを背負い直して、みんなといっしょに山をおりようとすると、「春風さん」と誰かが呼ぶ声がした。
「渡辺くん? なに?」
それは渡辺綱吉くんという、よく学級委員長の安倍くんといっしょにいるクラスメイトの男の子。
「春風さんは、八雲先生といっしょに鬼丸を探しに行ったよね。何を見たの?」
「え……、だから、寝てる鬼丸くんを見つけて、連れて帰ってきて……」
「本当に?」
渡辺くんの言葉に、アタシはドキドキしていた。
渡辺くんは、なんだか、すべてをお見通しのような気がしたのだ。
「ほ、本当だよ」
「ふうん、そう」
渡辺くんは、納得したのかわからない。
ただ、その場はそれで引き下がった。
彼は、鬼丸くんがそんなに好きではないので、どうでもよかったのかもしれない。
とにかく、それで鬼丸くん行方不明事件は解決して、アタシたちは遠足を終えて家に帰ったのであった。
〈続く〉
担任の池田先生に言われて、お弁当やお菓子のゴミを、あらかじめ持ってきていたビニール袋に入れて、リュックにしまう。
遠足の時間が終わって、みんな山をおりて帰る準備をしているところだった。
「あれ? 鬼丸くんは?」
アタシは、クラスメイトの鬼丸くんがいなくなっていることに気づいたのだ。
鬼丸虎鉄くんは、六年一組ではいたずらっ子として知られている。
教室のドアに黒板消しをはさんで、ドアを開けた子がチョークの粉まみれになってしまうのをたびたび見かけた。
先生たちも手を焼く厄介な生徒として、学校では有名だ。
「私、探してきますね。みんなは、ここから動かないで」
曜子先生が自ら名乗り出て鬼丸くんを探しに行った。
……ということは、もしかしたら……。
「曜子先生、アタシも行きます!」
アタシは曜子先生を追って、山道に入ったのである。
***
「こころちゃんまで、ついてこなくて良かったのに」
「保健委員ですから、鬼丸くんがケガしてたら大変だし」
アタシはそんな言い訳を並べたけど、実のところ、クラスに迷惑をかけてばかりの鬼丸くんをそこまで心配していない。
「……これ、オバケ案件ですか?」
「かすかに妖気……オバケの気配を感じるわ」
曜子先生は難しい顔をしていた。
「ただ、山にオバケなんていくらでもいるから、なんとも。鬼丸くん、無事だといいんだけど……」
「先生は、鬼丸くんの居場所に心当たりが?」
だって、曜子先生は迷いなく、どこかを目指して歩いている。
「ええ、まあ。鬼丸くんがイタズラするだろうなって場所はなんとなく」
鬼丸くんは当然、曜子先生にもイタズラをしたことがあった。
ただ、曜子先生のほうが一枚上手だ。
たとえば、黒板消しを挟んだ教室のドアに気づいた曜子先生は、なかなか教室には入らなかった。
早く罠にかかれ~とジリジリしていた鬼丸くんに、曜子先生が「家庭科実習で作ったクッキーがあるわよ」とわざとクッキーの香りを教室の中に漂わせる。
食いしん坊の鬼丸くんはドアを開けてしまって、逆にチョークの粉まみれになってみんなで大笑いしたこともあったっけ。
よく考えたら、キツネって人を化かすこともあるイタズラの名人だ。
そんな曜子先生にイタズラで勝負を挑んだ鬼丸くんがおバカなのだ。
「……ここじゃないかしら」
曜子先生は、山を少しおりたところで立ち止まった。
「ここって、山に登る途中で通った場所ですよね」
「そうね。それに、鬼丸くんなら、いかにもイタズラしそうでしょう?」
そこにあったのは、なにかをまつっている祠。
山を登ったときには、おモチがお供えされていたけど、それがなくなっている。
もしかしたら、食いしん坊の鬼丸くんが食べちゃったのかもしれない。
さらに大変なことに、祠に貼られていたはずの御札が、ビリビリに破かれて剥がされていた。
「まさか、鬼丸くんがこれを?」
「予想的中。これは厄介ね……」
曜子先生は、ふうとため息をつく。
どうやら、鬼丸くんは、この祠にまつられていた『なにか』にさらわれてしまったらしいのだ。
曜子先生は、祠に顔を近づけて鼻をクンクンさせた。
「こっちね。行きましょう」
まるで警察犬みたいに、匂いをかぎながら山の中を進む。
アタシは木の根っこに足を取られないように、必死に曜子先生のあとを追いかけた。
やがて、アタシたちは山の中にある、巨大な木にたどり着く。
それは山の中心にどっかりと根を張って、樹齢五百年はありそうだった。
木の中には空洞があり、『なにか』が住むにはぴったりだろう。
「鬼丸くん! そこにいるの?」
曜子先生が木の空洞を覗き込みながら声を掛ける。
「……いた!」
先生が指差すほうを見ると、木の空洞の中に、鬼丸くんがぐったりとしていた。
どうやら眠っているようだけど……。
「オイラの獲物になにか用かい? 妖怪だけに、なんちってな」
突然、男の人の声が聞こえた。
曜子先生はアタシをかばって身構える。
「おいおい、そんなに警戒するなよ」
「姿を見せなさい!」
「さっきからお前さんたちの頭上にいるぜ」
すると、声の主が木の上から逆さまにぶら下がって、その正体を現した。
アタシは「ひえっ」と悲鳴を上げる。
その男は――下半身が蛇だったのだ。
「蛇神、ってやつね」
「そういうアンタは、なんだかケモノくさいなあ」
蛇神はノンキな口調で笑っている。
しかし、口からはシューシューと細長い舌が……。
アタシは蛇が苦手だ。
一瞬、曜子先生に任せて、ついてこなければよかったと後悔してしまった。
でも、なんとか勇気をふりしぼって、ガクガクと震えるひざを叩く。
その間にも曜子先生と蛇神との会話は続いていた。
「そこの子どもは私の大切な生徒よ。返して」
「生徒? ふうん、アンタ、先生やってるのかい。そんなケモノの匂いをさせて」
「ケモノ」呼ばわりされて、曜子先生はだいぶ気が立っているらしい。
チェシャ猫に襲われたときと同じ、木々がざわざわと先生に恐れをなすような感覚がある。
先生の髪は、毛先から透き通るような金色に変わっていき、キツネの耳としっぽが生えていく。
蛇神はそんな先生の姿を見ても、「へえ」と言うだけで、特に驚いた様子も見せなかった。
「子どもを返さないなら、無理やり取り返すけど?」
「まあ、そう言いなさんな。オイラもほとほと参ってるんだよ」
手から生えたするどい爪を見せつける曜子先生に対して、蛇神はなんとも思ってなさそう。
「いやな、オイラはさっき目覚めたばっかなんだよ。そこのチビスケが祠の御札を剥がしちまったもんだから」
シュルシュルと蛇の下半身をたくみに動かして、逆さまの状態から木をつたい、木に巻き付く形でおりてきた蛇神は、木の空洞の中で眠っている鬼丸くんを親指で指し示す。
「それで、お腹も空いてんのにチビスケがお供え物のおモチも食っちまったってわけよ。こうなったら、それなりの『落とし前』が必要だよなあ?」
アタシには「落とし前」という言葉の意味がよくわからなかったけれど、あまり良くないことだというのは、なんとなくわかった。
「それで、鬼丸くんを食べようってわけね」
「た、食べる!?」
アタシはぎょっとしてしまった。
こんな木に巻き付くほどの大きな蛇神に食べられたら、鬼丸くんなんてぺろりと丸呑みにされてしまう。
「子どもを食べられるのは困るわ」
「でも、仕方ないんじゃねえかなあ。バチ当たりなことをするのが悪いんだぜ」
曜子先生と蛇神、二人の間にはバチバチと火花が散っていた。
このままじゃ、二人は争いを始めちゃう。
「ま、待って!」
そこへ、アタシが思わず割り込んだ。
「蛇神さん、お腹が空いてるんだよね?」
「そうだけど?」
「じゃあ、アタシのお弁当分けてあげる! 食べきれなくて余ったおにぎりがあるの」
アタシはリュックの中を探って、ラップに包まれたおにぎりを差し出す。
「これを、あなたへのお供え物にする。だから、鬼丸くんのことは許して!」
アタシは、おそるおそる蛇神におにぎりを渡して、またひゅっと曜子先生の後ろに走って戻った。
蛇神は、渡されたおにぎりをじっと見つめて、手の中で転がしている。
「いいのかい、お嬢ちゃん。オイラにこれをくれるのかい?」
「鬼丸くんは、女の子のスカートをめくったり、本当にしょうもないことばっかりするけど、それでも蛇神さんに食べられるのはダメ!」
アタシは勇気を出して、蛇神をにらみつけるように、じっと見つめた。
曜子先生も蛇神も、あっけにとられたように、アタシを見ている。
やがて、蛇神は「あっはっは」と笑った。
曜子先生も争う気をなくしたみたいで、髪の色も黒に戻り、キツネの耳やしっぽも消えていたのだ。
「いや、こりゃまいったね。まさかこんなちっちゃな人間の女の子に仲裁されちまうとは」
蛇神は自分の手で額をぴしゃりと叩いて、しばらく笑っていた。
「ありがとよ、お嬢ちゃん。このおにぎりは、ありがたくいただいておくよ。いや、しかし気に入っちまうな。山をおりて、お嬢ちゃんについていこうかね?」
「そ、それは困ります……」
「わかってる、冗談だ」
ケラケラと笑って、蛇神は「じゃあ、そのチビスケは先生に預けるよ」と曜子先生に言い残し、しゅるしゅると蛇の下半身を動かして、山の奥に消えていったのだ。
曜子先生はすぐに鬼丸くんのもとに駆け寄って、彼の手首を持ち上げる。
そして、ホッと息をついた。
「……よかった、脈はある。ケガもしてないみたい」
それを聞いて、アタシもホッとしたのだ。
曜子先生が気絶したままの鬼丸くんをおんぶして、みんなのところへ戻ると、先生も生徒もみんなびっくりしていた。
曜子先生は「鬼丸くんは木の空洞の中で寝ていて、ケガもしていない」と説明して、みんな笑い話として納得してくれたのだ。
でも、鬼丸くんは目を覚ましたあと、「みんなを心配させた」と池田先生にこっぴどくしかられてしまったのだった。
これで、鬼丸くんがこりてくれればいいんだけど、彼はイタズラが生きがいみたいな男の子なので、難しいかもしれない。
アタシがリュックを背負い直して、みんなといっしょに山をおりようとすると、「春風さん」と誰かが呼ぶ声がした。
「渡辺くん? なに?」
それは渡辺綱吉くんという、よく学級委員長の安倍くんといっしょにいるクラスメイトの男の子。
「春風さんは、八雲先生といっしょに鬼丸を探しに行ったよね。何を見たの?」
「え……、だから、寝てる鬼丸くんを見つけて、連れて帰ってきて……」
「本当に?」
渡辺くんの言葉に、アタシはドキドキしていた。
渡辺くんは、なんだか、すべてをお見通しのような気がしたのだ。
「ほ、本当だよ」
「ふうん、そう」
渡辺くんは、納得したのかわからない。
ただ、その場はそれで引き下がった。
彼は、鬼丸くんがそんなに好きではないので、どうでもよかったのかもしれない。
とにかく、それで鬼丸くん行方不明事件は解決して、アタシたちは遠足を終えて家に帰ったのであった。
〈続く〉