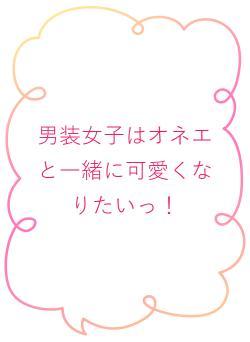体がどこもかしこも痛い。
もっと道路を注意深くわたるべきだった。
車はまるで、猛スピードで走る鉄でできたイノシシみたいに、『彼女』のからだを簡単にはねとばしたのだ。
私の生涯もここまでか……。
『彼女』が諦めて目をつぶろうとした、そのとき。
「おい、大丈夫か?」
うっすらと目を開けると、大人の男性が『彼女』に駆け寄った。
「しっかりしろ。今、病院につれてってやるからな」
思えば、この男との出会いがなければ、『彼女』は今まで通り、妖怪――オバケとして、自由気ままに生きるはずだっただろう。
でも、後悔はしていない。
これが『彼女』にできる、心尽くしの恩返しなのだから。
***
――『笑う猫』って話、知ってる?
――なにそれ?
――最近、学校の近くに出るんだって。ニヤニヤと人間みたいにイヤな笑い方をする猫。その猫に出会っちゃったら、大変なことになるんだって。
――どうなるの、出会っちゃったら。
――なんでも、不幸な目にあうとか、命をうばわれちゃうとか、四次元の世界に連れて行かれちゃうとか。
――え~、こわ~い。
小学六年生の女の子たちが悲鳴をあげながら、でも楽しそうに、怖い話をしている。
そう、みんな怖い話が大好き。
本当の話かどうかわからない、でも本当にあったらどうしよう。
そんな話が、みんな大好き。
小学生というのは、好奇心のかたまりだ。
毎日学校に行って、友だちと遊んで、宿題をするような日常も、まあ退屈ではないけれど、たまにはふしぎなものに出会って、ふつうじゃないことに巻き込まれたい。
たとえば、魔法使いの学校から招待状が届くとか。
たとえば、タイムスリップして過去の世界に行っちゃうとか。
子どもたちは、そんなふしぎな体験が自分の身に降りかかるのを待っている。
王馬小学校の六年生であるアタシ、春風こころも、そんな女の子だった。
およそ百年前、大正時代からの歴史がある王馬小学校の生徒数は年々減ってきていて、一学年に一クラスしかない。
アタシは六年一組。
「一組」とはいっても、一クラスしかないから、二組や三組はない。
だから、学年が変わっても、クラスの顔ぶれはそんなに変わらないのだ。
変わるものといえば、転校生がやってくるか委員会くらいのものだろう。
アタシは教室にいる安倍くんにチラッと目をやった。
安倍くんは五年生のときに転校してきた男の子だ。
この一年でずいぶんクラスになじんで、今は学級委員長。
男の子だけど黒い髪を長く伸ばして後ろでひとくくりにまとめていた。
そして、前髪の中央に一房だけ、白髪が生えている。
こういう髪の染め方を「メッシュ」というらしいけど、担任の池田先生に注意された時、「地毛なんです」と言っていた。
本当のことかどうかはわからないけど。
転校してきた頃から「かっこいい」と女の子に囲まれていたけど、六年生になった今でも、かくれファンがいるらしい。
その安倍くんは、同じクラスの渡辺くんと一番仲がよく、いっしょにいる姿をよく見かける。
渡辺くんの髪は色がうすく、灰色がかった短い茶髪だ。
これも本人が「地毛です」と言い張っており、池田先生が頭を悩ませている。
アタシはそんな二人を横目に見ながら、放課後の委員会の準備をすることにした。
アタシは一年生のときは図書委員だったけれど、二年生になってからはずっと保健委員に手をあげている。
どうして保健委員かというと、その理由は簡単だ。
放課後、アタシはホームルームが終わって、真っ先に保健室に駆けつけた。
「曜子先生、こんにちは!」
「あら、こころちゃん。今日も一番乗りね」
保健室の先生、八雲曜子先生がアタシにほほえみかけてくれる。
曜子先生は、アタシのあこがれの人だ。
一年生の運動会で転んでひざをすりむいたときに、手当てをしてくれたのが曜子先生だった。
曜子先生は「ちょっとしみるけどガマンしてね」と言いながら、アタシのひざをきれいに水で洗ってから消毒液をかけたのだ。
消毒液はとても痛かったけれど、アタシは目に涙を浮かべながらガマンした。
そのあと、曜子先生は傷口にばんそうこうを貼って、「よくガマンできたわね、えらいわ」とやさしく頭をなでてくれたのだ。
そのやさしい声と笑顔に、アタシはすっかり夢中になってしまった。
それで、二年生に上がってからはずっと保健委員になっている。
王馬小学校の保健委員の仕事はけっこう地味だ。
毎朝自分のクラスメイトの爪の長さや、爪が汚れていないかをチェックしたり、給食の時間の前に手洗いうがいをするように呼びかけたり、給食を食べ終わったらみんなで順番に歯みがきをするように指示したりする。
放課後には保健室に集まって、曜子先生から傷口の手当ての仕方や包帯の巻き方などを教わっていた。
そういった活動をめんどうくさいと思って、誰も立候補しないのをいいことに、アタシは毎年保健委員になっていたわけだ。
アタシは毎日、曜子先生に会えるのが楽しみだったし、傷の手当ての仕方を先生から習うのが好きだった。
これを勉強すれば、自分でも誰かがケガした時に役に立てると思ったからだ。
それから、曜子先生はとても美人だった。
モデルみたいに細くて長い足はロングスカートにかくれているけれど、歩くたびにスカートが魚のヒレみたいにゆらゆらとゆれて、その動きがとてもきれいだと思う。
緑色のたてじまのセーターの上から白衣を着ていて、汚れひとつない、清潔な感じが理科の先生とはまた違った。
髪はシャンプーのCMに出てくる女の人みたいにツヤツヤした黒色で、横髪は短い三つ編みにしていて、それがなんともオシャレだと思う。
そして、曜子先生はいつも優しいほほえみを浮かべている。
それが王馬小学校の子どもたちだけでなく、同じ学校の先生たちもメロメロにしていることを、アタシは知っていた。
この間も、体育の先生が曜子先生に話しかけているのを見たおぼえがある。
男の先生は曜子先生の前ではいつも顔を赤くして、鼻の下を伸ばしてデレデレした笑みを浮かべていて、アタシはおかしくなってふきだしそうなのをガマンするのが大変だった。
保健室に一番乗りしたアタシのあとから、他の保健委員も次々に到着して、曜子先生が指示を出す。
その日の放課後の保健委員の仕事は、曜子先生といっしょに保健室においてある包帯やばんそうこうなどの数を確認したり、学校のみんなに手洗いうがいをするように呼びかけるポスターを作ったりすること。
それが終わった頃には、保健室の時計は夕方の六時を示していた。
「みんな、今日もお疲れさま。気をつけて帰ってね」
曜子先生に「さようなら」とあいさつして、子どもたちは帰っていく。
アタシも、ランドセルをせおって校門を出た。
春の夕方は、冬に比べて日が落ちるのがおそい。
空は昼の青と夕方の赤が混じって、絵の具みたいに紫になっている。
早く帰らなくちゃ。
アタシの足は、自然と早歩きになっていた。
お父さんとお母さんは共働きだ。
だから、アタシは家の鍵を持たされている。
両親が帰ってくるのは夜の九時。
それまでに家に帰って、洗濯ものをしまう。
そして、おふろをわかして待つのだ。
そんなアタシの前に、一匹の猫が通り過ぎた。
――黒猫だ……。
黒猫が目の前を通ると不吉、なんて言われるけど、アタシはそれを知らなかった。
アタシは猫がかわいいから好きだ。
なでさせてもらえないかな。ちかよったら逃げちゃうかな?
おそるおそる、黒猫に近づいた。
そっとしゃがんで、なるべく猫と目線をあわせ、手を伸ばしてさわろうとする。
すると、猫の顔がこころのほうを向いた。
ニヤリと。
その猫が笑ったのだ。
「……え?」
アタシはその笑みを見るまで忘れていた。
その日の朝、クラスの女の子たちが話していたウワサ。
『笑う猫』の話を。
猫がギザギザした歯を見せつけるようにむきだして、耳まで裂けるくらい笑っているのを見て、ゾッとした。
――笑う猫に出会ったら、不幸な目にあう。
もしくは、命をうばわれる。
あるいは……四次元の世界に連れて行かれる。
しゃがんでいたアタシは、腰を抜かして地面に座ったままあとずさりをした。
「――キヒヒ。お前、王馬小学校の生徒だな」
黒猫が笑った顔のまま、アタシに話しかけてくる。
「ね、猫がしゃべった……!?」
いや、猫が笑う時点ですでにおかしいのだが、まさか言葉を話すとは。
猫はびっくりしているアタシに構わず、しゃべり続けた。
「王馬小学校で『鍵』を見たことはないか?」
「か、鍵……? なんの鍵?」
小学校には、鍵なんていくらでもある。
それぞれの教室の鍵だけでもかなりの数だ。
猫はニタァっと笑ったまま、あとずさりするアタシに近寄る。
「王馬小学校のオバケを自由にしてやれる、魔法の鍵さ」
「えっ……なにそれ……?」
そんな鍵は知らない。
そもそも、学校のオバケを自由にしてしまったら、まずいのではないだろうか。
「なんだ、何も知らないのか。じゃあ、しょうがないな……」
笑う黒猫は、前足からするどい爪を出す。
「――なら、お前は用済みだ」
その爪に、アタシは切り裂かれるはずだった。
それを、すんでのところで止めてくれた人がいたのだ。
「やめなさい!」
女の人の声がして、誰かがアタシを後ろから抱きかかえて引っ張った。
アタシが先ほどまでいた場所を、猫のするどい爪が通り過ぎる。
――あ、あぶないところだった!
背中に、冷や汗がふきでた。
でも、誰が助けてくれたんだろう?
その女の人の声に、聞き覚えがあった。
顔を見上げると、やっぱり知ってる人だったのだ。
「――よ、曜子先生……!」
保健室の八雲曜子先生が、アタシの体を抱きかかえていた。
その体を地面におろし、「私のうしろに下がっていて」と、アタシをかばうようにして、笑う猫の前に立ちふさがる。
黒猫は、ニタニタと笑ったまま、その表情を変えない。
「お前、小学校の先生か。なら、鍵の場所も知ってるんじゃないか?」
「知ってても教えると思う?」
アタシはぽかんと口を開けていた。
曜子先生は、猫がしゃべっていても、ちっとも変だと思ってないみたい。
それどころか、ふつうに会話してる……。
「なら、そこのガキといっしょに、バラバラに切り刻んでやるよ!」
笑う猫の爪が、ようしゃなく曜子先生の肌をひっかいた。
曜子先生のきれいな顔が、あっと声を上げる間もなく、赤ペンを引いたみたいに引っかき傷をつけられる。
「やめて! 曜子先生にひどいことしないで!」
アタシが叫んでも、黒猫はニヤニヤとイヤな笑みを浮かべたまま、曜子先生を切り裂こうと爪を持ち上げた。
そのときだ。
「……生徒の前では正体を見せたくなかったけど、こうなったら仕方ないようね」
曜子先生がそうつぶやくと、周りの空気がざわつく。
まるで、草や木が曜子先生を恐れるみたいに。
そして、曜子先生の長い黒髪は、毛先から、透き通るような金色に変わっていった。
動物のような耳が頭の上に生えてきて、ふさふさのしっぽまで。
「――私は妖狐・八雲。ここで引き下がらなければ、私がここであなたを始末する」
曜子先生――いや、妖狐八雲は厳しい口調で、笑う猫をにらみつけていた。
猫は妖狐八雲の姿を見た途端、あのイヤな笑みがようやく消える。
「フン、王馬小学校には変わり者のキツネが住んでいると聞いたが、本当らしいな」
そう言って、黒猫はくるりと方向を変えた。
「だが、覚えておけよ。俺は必ず、オバケの鍵をいただくぞ」
そして、猫は夕方の闇の中に姿を消したのだ。
残されたのはアタシと、キツネのような姿の曜子先生だけ。
「曜子先生、どういうことなの……?」
アタシは首をかしげて曜子先生を見る。
先生は、するすると耳としっぽを引っ込めて、髪も黒い、元の人間の姿に戻っていた。
「こころちゃん、お願いがあるの」
「な、なんでしょう……?」
「このことは、こころちゃんと私のひみつにしてほしいの」
曜子先生の目は真剣そのもの。
アタシは思わずうなずいていた。
「わかりました……。でも、何が起こっているのか、わかりません」
「事情は明日、私が説明します。明日の放課後、保健委員の仕事が終わったら、保健室に残って」
そして、曜子先生はアタシを家まで送ってくれたのだ。
「もうあの猫は来ないと思うけど、念のため、お父さんやお母さんが帰ってくるまでは家に鍵をかけていて。それじゃ、また明日」
「あ、はい……」
曜子先生は長い黒髪とロングスカートをひるがえして歩き去っていく。
その姿は、やっぱりきれいだと思った。
〈続く〉
もっと道路を注意深くわたるべきだった。
車はまるで、猛スピードで走る鉄でできたイノシシみたいに、『彼女』のからだを簡単にはねとばしたのだ。
私の生涯もここまでか……。
『彼女』が諦めて目をつぶろうとした、そのとき。
「おい、大丈夫か?」
うっすらと目を開けると、大人の男性が『彼女』に駆け寄った。
「しっかりしろ。今、病院につれてってやるからな」
思えば、この男との出会いがなければ、『彼女』は今まで通り、妖怪――オバケとして、自由気ままに生きるはずだっただろう。
でも、後悔はしていない。
これが『彼女』にできる、心尽くしの恩返しなのだから。
***
――『笑う猫』って話、知ってる?
――なにそれ?
――最近、学校の近くに出るんだって。ニヤニヤと人間みたいにイヤな笑い方をする猫。その猫に出会っちゃったら、大変なことになるんだって。
――どうなるの、出会っちゃったら。
――なんでも、不幸な目にあうとか、命をうばわれちゃうとか、四次元の世界に連れて行かれちゃうとか。
――え~、こわ~い。
小学六年生の女の子たちが悲鳴をあげながら、でも楽しそうに、怖い話をしている。
そう、みんな怖い話が大好き。
本当の話かどうかわからない、でも本当にあったらどうしよう。
そんな話が、みんな大好き。
小学生というのは、好奇心のかたまりだ。
毎日学校に行って、友だちと遊んで、宿題をするような日常も、まあ退屈ではないけれど、たまにはふしぎなものに出会って、ふつうじゃないことに巻き込まれたい。
たとえば、魔法使いの学校から招待状が届くとか。
たとえば、タイムスリップして過去の世界に行っちゃうとか。
子どもたちは、そんなふしぎな体験が自分の身に降りかかるのを待っている。
王馬小学校の六年生であるアタシ、春風こころも、そんな女の子だった。
およそ百年前、大正時代からの歴史がある王馬小学校の生徒数は年々減ってきていて、一学年に一クラスしかない。
アタシは六年一組。
「一組」とはいっても、一クラスしかないから、二組や三組はない。
だから、学年が変わっても、クラスの顔ぶれはそんなに変わらないのだ。
変わるものといえば、転校生がやってくるか委員会くらいのものだろう。
アタシは教室にいる安倍くんにチラッと目をやった。
安倍くんは五年生のときに転校してきた男の子だ。
この一年でずいぶんクラスになじんで、今は学級委員長。
男の子だけど黒い髪を長く伸ばして後ろでひとくくりにまとめていた。
そして、前髪の中央に一房だけ、白髪が生えている。
こういう髪の染め方を「メッシュ」というらしいけど、担任の池田先生に注意された時、「地毛なんです」と言っていた。
本当のことかどうかはわからないけど。
転校してきた頃から「かっこいい」と女の子に囲まれていたけど、六年生になった今でも、かくれファンがいるらしい。
その安倍くんは、同じクラスの渡辺くんと一番仲がよく、いっしょにいる姿をよく見かける。
渡辺くんの髪は色がうすく、灰色がかった短い茶髪だ。
これも本人が「地毛です」と言い張っており、池田先生が頭を悩ませている。
アタシはそんな二人を横目に見ながら、放課後の委員会の準備をすることにした。
アタシは一年生のときは図書委員だったけれど、二年生になってからはずっと保健委員に手をあげている。
どうして保健委員かというと、その理由は簡単だ。
放課後、アタシはホームルームが終わって、真っ先に保健室に駆けつけた。
「曜子先生、こんにちは!」
「あら、こころちゃん。今日も一番乗りね」
保健室の先生、八雲曜子先生がアタシにほほえみかけてくれる。
曜子先生は、アタシのあこがれの人だ。
一年生の運動会で転んでひざをすりむいたときに、手当てをしてくれたのが曜子先生だった。
曜子先生は「ちょっとしみるけどガマンしてね」と言いながら、アタシのひざをきれいに水で洗ってから消毒液をかけたのだ。
消毒液はとても痛かったけれど、アタシは目に涙を浮かべながらガマンした。
そのあと、曜子先生は傷口にばんそうこうを貼って、「よくガマンできたわね、えらいわ」とやさしく頭をなでてくれたのだ。
そのやさしい声と笑顔に、アタシはすっかり夢中になってしまった。
それで、二年生に上がってからはずっと保健委員になっている。
王馬小学校の保健委員の仕事はけっこう地味だ。
毎朝自分のクラスメイトの爪の長さや、爪が汚れていないかをチェックしたり、給食の時間の前に手洗いうがいをするように呼びかけたり、給食を食べ終わったらみんなで順番に歯みがきをするように指示したりする。
放課後には保健室に集まって、曜子先生から傷口の手当ての仕方や包帯の巻き方などを教わっていた。
そういった活動をめんどうくさいと思って、誰も立候補しないのをいいことに、アタシは毎年保健委員になっていたわけだ。
アタシは毎日、曜子先生に会えるのが楽しみだったし、傷の手当ての仕方を先生から習うのが好きだった。
これを勉強すれば、自分でも誰かがケガした時に役に立てると思ったからだ。
それから、曜子先生はとても美人だった。
モデルみたいに細くて長い足はロングスカートにかくれているけれど、歩くたびにスカートが魚のヒレみたいにゆらゆらとゆれて、その動きがとてもきれいだと思う。
緑色のたてじまのセーターの上から白衣を着ていて、汚れひとつない、清潔な感じが理科の先生とはまた違った。
髪はシャンプーのCMに出てくる女の人みたいにツヤツヤした黒色で、横髪は短い三つ編みにしていて、それがなんともオシャレだと思う。
そして、曜子先生はいつも優しいほほえみを浮かべている。
それが王馬小学校の子どもたちだけでなく、同じ学校の先生たちもメロメロにしていることを、アタシは知っていた。
この間も、体育の先生が曜子先生に話しかけているのを見たおぼえがある。
男の先生は曜子先生の前ではいつも顔を赤くして、鼻の下を伸ばしてデレデレした笑みを浮かべていて、アタシはおかしくなってふきだしそうなのをガマンするのが大変だった。
保健室に一番乗りしたアタシのあとから、他の保健委員も次々に到着して、曜子先生が指示を出す。
その日の放課後の保健委員の仕事は、曜子先生といっしょに保健室においてある包帯やばんそうこうなどの数を確認したり、学校のみんなに手洗いうがいをするように呼びかけるポスターを作ったりすること。
それが終わった頃には、保健室の時計は夕方の六時を示していた。
「みんな、今日もお疲れさま。気をつけて帰ってね」
曜子先生に「さようなら」とあいさつして、子どもたちは帰っていく。
アタシも、ランドセルをせおって校門を出た。
春の夕方は、冬に比べて日が落ちるのがおそい。
空は昼の青と夕方の赤が混じって、絵の具みたいに紫になっている。
早く帰らなくちゃ。
アタシの足は、自然と早歩きになっていた。
お父さんとお母さんは共働きだ。
だから、アタシは家の鍵を持たされている。
両親が帰ってくるのは夜の九時。
それまでに家に帰って、洗濯ものをしまう。
そして、おふろをわかして待つのだ。
そんなアタシの前に、一匹の猫が通り過ぎた。
――黒猫だ……。
黒猫が目の前を通ると不吉、なんて言われるけど、アタシはそれを知らなかった。
アタシは猫がかわいいから好きだ。
なでさせてもらえないかな。ちかよったら逃げちゃうかな?
おそるおそる、黒猫に近づいた。
そっとしゃがんで、なるべく猫と目線をあわせ、手を伸ばしてさわろうとする。
すると、猫の顔がこころのほうを向いた。
ニヤリと。
その猫が笑ったのだ。
「……え?」
アタシはその笑みを見るまで忘れていた。
その日の朝、クラスの女の子たちが話していたウワサ。
『笑う猫』の話を。
猫がギザギザした歯を見せつけるようにむきだして、耳まで裂けるくらい笑っているのを見て、ゾッとした。
――笑う猫に出会ったら、不幸な目にあう。
もしくは、命をうばわれる。
あるいは……四次元の世界に連れて行かれる。
しゃがんでいたアタシは、腰を抜かして地面に座ったままあとずさりをした。
「――キヒヒ。お前、王馬小学校の生徒だな」
黒猫が笑った顔のまま、アタシに話しかけてくる。
「ね、猫がしゃべった……!?」
いや、猫が笑う時点ですでにおかしいのだが、まさか言葉を話すとは。
猫はびっくりしているアタシに構わず、しゃべり続けた。
「王馬小学校で『鍵』を見たことはないか?」
「か、鍵……? なんの鍵?」
小学校には、鍵なんていくらでもある。
それぞれの教室の鍵だけでもかなりの数だ。
猫はニタァっと笑ったまま、あとずさりするアタシに近寄る。
「王馬小学校のオバケを自由にしてやれる、魔法の鍵さ」
「えっ……なにそれ……?」
そんな鍵は知らない。
そもそも、学校のオバケを自由にしてしまったら、まずいのではないだろうか。
「なんだ、何も知らないのか。じゃあ、しょうがないな……」
笑う黒猫は、前足からするどい爪を出す。
「――なら、お前は用済みだ」
その爪に、アタシは切り裂かれるはずだった。
それを、すんでのところで止めてくれた人がいたのだ。
「やめなさい!」
女の人の声がして、誰かがアタシを後ろから抱きかかえて引っ張った。
アタシが先ほどまでいた場所を、猫のするどい爪が通り過ぎる。
――あ、あぶないところだった!
背中に、冷や汗がふきでた。
でも、誰が助けてくれたんだろう?
その女の人の声に、聞き覚えがあった。
顔を見上げると、やっぱり知ってる人だったのだ。
「――よ、曜子先生……!」
保健室の八雲曜子先生が、アタシの体を抱きかかえていた。
その体を地面におろし、「私のうしろに下がっていて」と、アタシをかばうようにして、笑う猫の前に立ちふさがる。
黒猫は、ニタニタと笑ったまま、その表情を変えない。
「お前、小学校の先生か。なら、鍵の場所も知ってるんじゃないか?」
「知ってても教えると思う?」
アタシはぽかんと口を開けていた。
曜子先生は、猫がしゃべっていても、ちっとも変だと思ってないみたい。
それどころか、ふつうに会話してる……。
「なら、そこのガキといっしょに、バラバラに切り刻んでやるよ!」
笑う猫の爪が、ようしゃなく曜子先生の肌をひっかいた。
曜子先生のきれいな顔が、あっと声を上げる間もなく、赤ペンを引いたみたいに引っかき傷をつけられる。
「やめて! 曜子先生にひどいことしないで!」
アタシが叫んでも、黒猫はニヤニヤとイヤな笑みを浮かべたまま、曜子先生を切り裂こうと爪を持ち上げた。
そのときだ。
「……生徒の前では正体を見せたくなかったけど、こうなったら仕方ないようね」
曜子先生がそうつぶやくと、周りの空気がざわつく。
まるで、草や木が曜子先生を恐れるみたいに。
そして、曜子先生の長い黒髪は、毛先から、透き通るような金色に変わっていった。
動物のような耳が頭の上に生えてきて、ふさふさのしっぽまで。
「――私は妖狐・八雲。ここで引き下がらなければ、私がここであなたを始末する」
曜子先生――いや、妖狐八雲は厳しい口調で、笑う猫をにらみつけていた。
猫は妖狐八雲の姿を見た途端、あのイヤな笑みがようやく消える。
「フン、王馬小学校には変わり者のキツネが住んでいると聞いたが、本当らしいな」
そう言って、黒猫はくるりと方向を変えた。
「だが、覚えておけよ。俺は必ず、オバケの鍵をいただくぞ」
そして、猫は夕方の闇の中に姿を消したのだ。
残されたのはアタシと、キツネのような姿の曜子先生だけ。
「曜子先生、どういうことなの……?」
アタシは首をかしげて曜子先生を見る。
先生は、するすると耳としっぽを引っ込めて、髪も黒い、元の人間の姿に戻っていた。
「こころちゃん、お願いがあるの」
「な、なんでしょう……?」
「このことは、こころちゃんと私のひみつにしてほしいの」
曜子先生の目は真剣そのもの。
アタシは思わずうなずいていた。
「わかりました……。でも、何が起こっているのか、わかりません」
「事情は明日、私が説明します。明日の放課後、保健委員の仕事が終わったら、保健室に残って」
そして、曜子先生はアタシを家まで送ってくれたのだ。
「もうあの猫は来ないと思うけど、念のため、お父さんやお母さんが帰ってくるまでは家に鍵をかけていて。それじゃ、また明日」
「あ、はい……」
曜子先生は長い黒髪とロングスカートをひるがえして歩き去っていく。
その姿は、やっぱりきれいだと思った。
〈続く〉