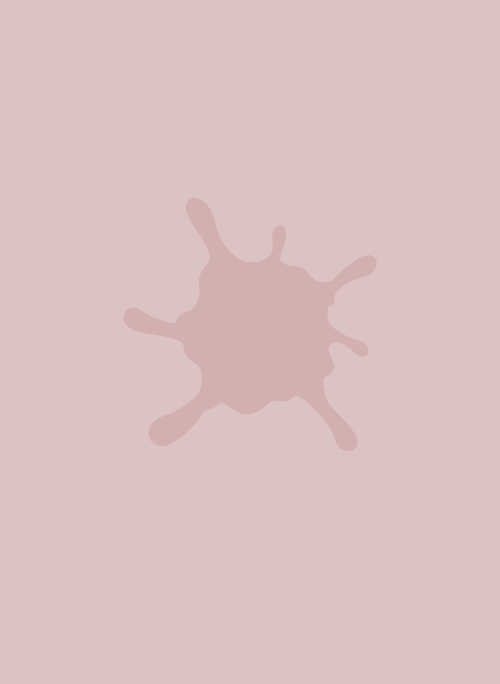「っ! なんてことを言うのかしら! そちらの娘を嫁入りでなく、ウチが婿入りにするというのも仕方なく飲み込んだというのに! いいわ、他にいくらでも嫁に来てもらう財閥はあるもの。あなた達! 帰りますよ!」
よほど核心をついたのか、おばあさんは急に態度を変えた。
「おっと。ルイジョーヌくんは残ってもらえるかな?」
「ーーえ?」
「構いませんよ。どうせ、妾の子ですから。役に立たないにも程があるわ」
と、嫌味を吐き捨てて黄山くんのおばあさんとお父さんは退席した。
「あ、あのーー」
「あぁ、すまないね。キミの貴重な時間をこんかことに使ってしまって。お詫びにーー二つほど、私の話を聞いて貰えないかな?」
パパがそう言うと、一人残された黄山くんは戸惑いながらも小さく頷いていた。
「それはよかった。まず、一つ目ーー」
そう言うと、パパは扉の方を見てフランス語で『入って頂けますか?』と言った。
その声で、扉はゆっくりと開いた。
扉の向こう側に立っていたのは、二人の外国の方。
ーー誰だろう?
二人をじっと見ていると、ガタッと音がしたのでそちらを見た。音を出したのは、立ち上がった黄山くんだった。