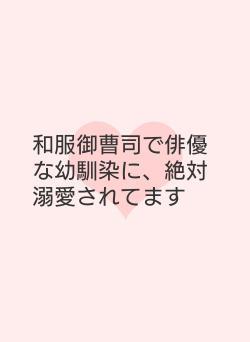帰りの車の中、紗理奈と近江の二人は終始無言だった。
(せっかく素敵なレストランに連れて行ってもらったし、ちゃんと御礼だって言いたいのに……)
紗理奈は、喉に何か引っかかっているかのように、声を発することができないでいた。
すると、珍しく近江が口を開く。
「あの二人は、元々警察官の同僚たちだったんだ」
先ほどの二人の話になって、紗理奈の身体がピクンと跳ね上がる。
「君の兄の事件があるまでは一緒に働いていた。けれども、あの事件をきっかけに二人とも警察ではいるのを嫌がって退職してしまったんだ」
紗理奈は俯いたままでいたが、こうやって近江が話してくれている内がチャンスだろう。
ひりついた喉から、なんとか問いかける。
「その……駿河千絵さんは、近江さんの婚約者だって話が出ていましたけれど、本当でしょうか?」
しばらく近江からの返事がなかったが、ぽつりと口を開いた。
「そうだ」
紗理奈は再び衝撃を受けた。
心が千々に乱れていく。
なんとなく泣きそうな気持になった。
けれども、動揺しているのを悟られたくなくて、無理に笑顔を作った。
「恋人はいないと仰っていたから、てっきり女性と全く縁がない人生を送ってこられていたのかと勘違いしていました」
近江は道路をまっすぐに見たまま伝えてくる。
「君には伝える必要がないことだと思っていたんだ」
ズキン。
近江から突き放されたような気がして、紗理奈は目の前が真っ暗になりかけた。
先ほどの駿河と近江の会話も拍車をかけてくる。
『事件解決のためなら手段は選ばない!』
ザワリ。
(近江さんは……)
紗理奈はそこでハッとする。
嫌な考えに行き当たってしまった。
違う、違う。
そう思いたかったが、どうしても嫌な想像が頭の中に膨れ上がってくる。
(最初から、近江さんは私のことを事件解決の手段としてしか考えていなかったんだわ)
そもそもが、一緒に暮らしたいとしか、近江は話してはこなかった。
期間限定の恋人同士になったのだって、そちらの方が都合が良いと判断したのかもしれない。
(そうよ、プロポーズだって、特別な感情を抱いての申し出ではなかったのに……)
異性から一緒に住もうと言われて、紗理奈が勝手に舞い上がっていたのだ。
だんだんと、兄の代わりに君を守ると話してきたことさえも、事件解決のために都合が良いと判断して話してきたのではないかと疑心暗鬼になってくる。
紗理奈はぎゅっと両手の拳を握って耐える。
「そうですね、私たちは所詮、期間限定の恋人同士でしかないですもんね」
「その件、堂本紗理奈、君が良ければなんだが……」
近江が何かの話を切り出し掛けたが、それ以上は話をしたくなくて、紗理奈は話を遮った。
「あ! そろそろマンションにつきますよ!」
「ああ、そうか」
苦しい言い訳まがいの発言だったが、近江は運転に集中しはじめる。
せっかく素敵なレストランでのデートだったけれど、紗理奈の気持ちは暗澹としたままだったのだ。