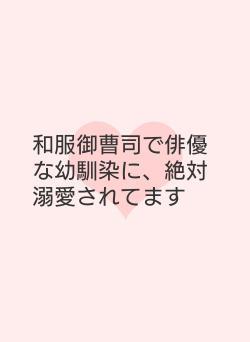帰宅した近江に連れて行かれたのは、フランス料理を提供するレストランだった。
電話で説明があった通り、近江のかつての同僚が定年後に経営をはじめたそうだ。
コック兼経営者の同僚は、白髪白髭のがたいの良い男性だったが、『皆が圭一に恋人ができたって話していたから見てみたかった。可愛いお嬢さんだ』と快活に笑っており、なんとなく真心新聞社の後藤局長のことを思い出させた。
紗理奈は、クラシックな黒のワンピースの上に黒白のツイードのジャケットを羽織り、それなりにおかしくない格好をしていたが、ちょうど良い塩梅だったようだ。
対して、近江は仕事の際に着用している黒いスーツの姿だ。普段着を身に着けていてもカッコいいが、正装姿は凛々しくてカッコいい。しかも、和食中心に育ったと話していたはずだが、やはり御曹司というべきか、洋食を食べる際のフォークとナイフ捌きも様になっていた。
いよいよデザートという頃、近江が紗理奈のことをじっと見つめてきていることに気付いた。
「近江さん、私の顔に何かついているでしょうか?」
すると、近江が目を少しだけ見開いた。かと思うと頬をさっと朱に染める。
「ああ、すまない。そんなに観察しているつもりはなかったんだ」
どうやら自覚なく紗理奈のことを観察していたようだ。近江の反応を見ていると、紗理奈の方まで体温が上昇していくようだ。
咳ばらいをした近江が、改めて口を開く。
「その……」
「なんでしょうか?」
「君はどんな時でもよく食べるな」
紗理奈としては反応に困った。
「それは食いしん坊ということでしょうか?」
「いいや、そういうわけではない」
だったら、いったいどういう意味なのだろうかと思っていたら……
近江が少しだけ視線を逸らしながら告げてくる。
「健康的で良いと思う。丈夫な子を産んでくれそうだ」
「……っ……!」
紗理奈は食べている途中だったパンを喉に詰まらせそうになった。
「大丈夫か!? 堂本紗理奈!」
近江が急いで立ち上がると、紗理奈のそばに近づいてきて背を擦ってくれた。
「げほっ、げほっ、走馬灯が見えました」
「すまない。おかしな発言をしてしまったようだ」
「ええっと、その、おかしくはなくてですね……」
なんとなく二人して赤面したまま、慌てふためいていたら……
「圭一さん?」