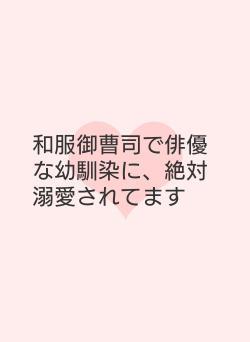最初に出会った時も、「勇気と無謀をはき違えるな」と言われたことを思い出す。
「猪突猛進とはよく言われます」
紗理奈はポツリと思いを吐露する。
「もっと近江さんみたいに慎重な人の方が記者には向いているんだろうなと思います」
「残念ながら、俺は警察、それも刑事だ」
「……例えの話ですよ。近江さんには揚げ足を取っているつもりは欠片もないのかもしれませんけど、こう、なんですかね、あまり無駄がないストレートな話し方をする男性ですよね」
「ん?」
紗理奈は肩をすくめた。
「和装なんかが似合いそうな日本人的な雰囲気なのに、機械的と言いますか、婉曲的な物の言い方はしないと言いますか」
「婉曲的な言い方をして話がかみ合わなかった場合に大事故が起こるからな……というよりも、警察関係者以外の人間たちには通じないような言葉を使うことはある」
「まる暴とかがさ入れとか、そういうのでしょう? 刑事ドラマの影響なんかで有名になっちゃっていますけど」
「ああ、そうだ」
「それとはまた話は別なんですよ」
「……というと?」
近江が不思議そうに首を傾げていた。
「合理的というやつでしょうか? 誰かと話すときに論理的に話すので、諭されちゃうというか? こう話の段階を踏んで説明するから、記事を書く時の説得力が増すと思うんですよ」
「お前の話したい内容に合点が行った」
どうやら紗理奈の話したい内容を、近江は理解してくれたようだ。
「何事も適正というものがある。警察にしろ、新聞記者にしろ」
紗理奈はゴクリと唾を呑み込んだ。近江の言葉を待つ。
「俺のように事実を淡々と述べる力に長ける者も確かに記者に向いているかもしれない。だがな……」
近江が紗理奈のことを真っすぐに見つめてくる。
あまりに真摯な眼差しに、全てを見抜かれてしまいそうだ。
「無謀だが、ヤクザ相手にも怯まず、取材を熱心におこなう。そういう行動力や情熱を持った人間だって、記者として向いていると俺は思う」
ドクン。
紗理奈の中で本当に自分は記者に向いているのだろうかと悩むことがあったが、近江の言葉を聞いていたら、なんだか勇気が湧いてきた。
(私ったら……あんなに警察に苦手意識があったくせに……)
けれども、警察としてではなく、近江圭一という人物の言葉であるならば、信用したい。
紗理奈はそんな風に思うようになっていた。
「俺から見れば、君の記者として記事を書く力や、腕も悪くないと思っている。だから、ぜひ新聞記者としてこれからも頑張ってほしい」
近江に褒められて、紗理奈の心中はパアッと明るくなっていく。
「そもそも新聞記者は常に俺たちの動向を探ってきていて、警察の張り込みよりも張っているようなところがあって、俺も苦手だ。探りを入れてこられることもあるし、少々関わるのは厄介だと思うこともあるが、無謀な振る舞いさえ避けてもらえるなら構わないと思っている」
近江は紗理奈の職業に対して、かなり率直な意見を述べてくれているようだ。
警察という職業には、まだ苦手意識や抵抗感があるが、近江に関して知りたいという気持ちがむくむくと湧いてくる。
紗理奈は今度は近江について問いかけることにした。
「近江さん、そういえば、どうして刑事部の中でも捜査第四課なんですか?」
「ん?」