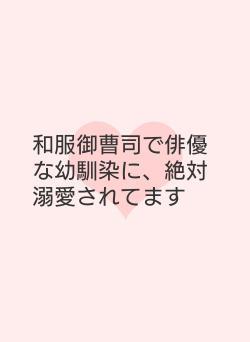少々反省していると、近江が理由を告げてくれた。
「こんな風に食事に菓子やデザートなどの甘い食べた経験が俺にはあまりない。だからどんなものがあるのか詳しく知らないんだ」
「えっ!?」
驚きのあまり、紗理奈の声がひっくり返ってしまった。
「近江さん、甘いもの、ほとんど食べたことがないんですか!?」
「ああ、そうだ」
「いったいぜんたいどうして!?」
すると、近江が静かな語り口調で話しはじめた。
「俺は幼少期に母を亡くしている」
「え? そういえば、父親である近江警視総監とは、幼少期からあまり関りがないと仰っていませんでしたっけ? だったら、ご両親は……」
「二人ともいないようなものだった。父方の祖母が俺の母親代わりを勤めてくれたんだが、武家家系の出身で厳格な女性でな。かなり厳しくしつけられて、『甘いものは人を堕落させる』と言って、菓子類は全て禁じられていたんだ。祖母ももう亡くなってこの世にはいないがな」
「た、確かに、甘いものの誘惑は危険ですけれど……」
近江を見ていたら、かなりストイックな雰囲気がある。きちんと整理整頓したり、厳格な祖母の教育の賜物なのだろう。
「もしも近江さんのおばあさんが生きていらっしゃって、今の光景を見つかりでもしたら、私はだらしがないって叱られそうですね。私、すっごく甘いものが好きだから」
「だろうな」
即答されてしまい、紗理奈は内心落ち込んでしまった。
「この数日一緒に過ごして思うが、お前は確かに祖母に比べるとだらしがない」
ストレートな言葉の数々に、紗理奈の心は抉れていっていたのが……