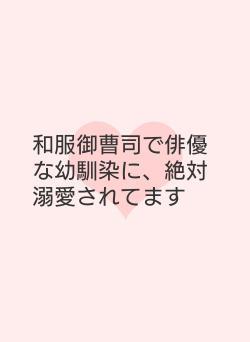近江はと言えば……どうしてだか、大きな片手で顔面を覆っていた。合間から覗く肌は真っ赤だ。
そんな彼の様子を見ていたら、紗理奈まで赤面してしまうではないか。
(年上の男の人のはずなのに、近江さん、どうしてこんなに純情なの……!?)
二人でしばらく慌てていたが、近江が咳ばらいをした。
「すまない、それでは先に風呂に入らせてもらう」
そうして、彼は浴室へと向かって行った。
紗理奈は台所へと向かう。春先なので、ネットスーパーで新じゃがと菜の花が頼んであったはずだ。冷蔵庫の食材を確認すると調理をはじめる。
しばらくすると、風呂上がりの近江が、タオルで黒髪を拭きながら姿を現した。
「うまそうな香りがするな」
「そうでしょう? 完成したので、どうぞお座りくださいな」
紗理奈はテーブルの上に、出来た料理を並べる。
今日は、肉じゃが、菜の花と豆腐の味噌汁、菜の花と新じゃがのマッシュポテトを作った。紗理奈本人としては、菜の花の緑がフレッシュな献立に仕上がったと思う。
椅子に座った近江が手を合わせる。
「すまない、いただこう」
「私も食べます、いただきます」
二人で黙々と食事する。旬の食材を使った料理は、自家製でも絶品だ。
全てを咀嚼し終わった近江が、「ごちそうさま」と箸を置いた後に、紗理奈に話し掛けてくる。
「君は、見た目は派手だがかなり家庭的なようだな。俺も簡単な和食を作るが、今日は旬の野菜をふんだんに作った品ばかりだった」
「ありがとうございます。貧乏性で、旬の食材の方が安上がりで済みますから、知っているだけなんですよ」
紗理奈も食事をし終わったので、箸をそっとテーブルの上に置いた。
真っ向から誰かを褒めるのには慣れているが、褒められるのには慣れていない。
紗理奈は、なんだか胸がムズムズしてしまう。
近江は、元々食に関心が薄い性質なのか、何も食べずに帰ってくることがあった。紗理奈は心配して夜食を作ってあげることにしたのだが、毎食こんな感じで褒めてくるものだから、なんだか調子に乗ってしまいそうだ。
近江が淡々と告げてくる。
「もしも新聞記者の仕事以外で働くのだとしたら、料理を誰かに振舞うのも悪くなさそうだな」
「レストランなんかの経営は私の大雑把な性格だと厳しいと思うんですよね、せっかくだから、誰かの家政婦さんになったりとか? あ、意外と奥さんにも向いてるかな? ……なんて」
紗理奈が笑いながら返すと、近江が頬を朱に染めながら返事をしてきた。
「その通りだ……誰かの伴侶になるのも向いていると思う」
紗理奈はまたしてもなんだか恥ずかしくなってきてしまった。
(うう、そんな風に照れながら話してこられたら、私まで照れちゃう)
頬が熱くて堪らない。それを誤魔化すかのように、紗理奈は席を立った。
「昼に退屈だったから、簡単にお菓子を作ったので、そちらをお持ちしますね」
「かたじけない」
そうして、冷蔵庫に冷やして置いたジャスミンティーゼリーを二人分持ってくる。透明なグラスにジャスミンティーを注いで砂糖とゼラチンを混ぜて固めただけの簡単なデザートだ。その上にホイップクリームとミントの葉を飾っている。
「まさかデザートまで食べられるとはな。こちらもいただこう」
「どうぞ」
近江が喜々としてゼリーをスプーンで食した。
「これはうまいな」
「近江さんが、お茶は中国茶でも日本茶でも好きそうで良かったです」
紗理奈が購入しなくとも、近江のキッチンに、元々色んなお茶の葉が置いてあったのだ。そのおかげで、このデザートを作ることが出来たのだ。
近江が優雅な所作でゼリーを全て食した。表情が淡々として分かりづらいが、少しだけ明るい印象だ。
「苦みと甘みが絶妙なバランスで、つるりとのど越しも良くて、とても美味だった。ありがとう、ごちそうさま」
「いいえ、どういたしまして。近江さん、好きなデザートがあったら教えてくださいね。また作りますから」
すると、近江からは思いがけない返答があった。
「教えたいのはやまやまだが、教えてやることはできない」
先ほどの喜ぶような返事とは違った解答だったため、紗理奈はちょっとだけショックを受ける。
(さすがに距離を縮め過ぎたのかも)