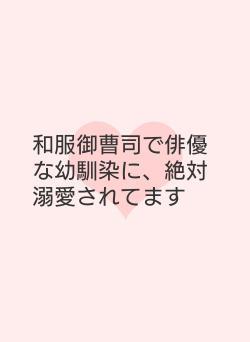「甘くて良い香りがするな」
近江が目を覚まし、むくりと身体を起こした。
「ごめんなさい、起こしてしまいましたね。後は、勝手にキッチンを借りてしまいました」
「いいや、こちらこそ料理を準備してもらえるとは、感謝する」
近江が立ち上がるとテーブルへと近づいてくる。黒いスーツのジャケットは脱いでしまっている。白いワイシャツ姿だが、ネクタイは留めておらず、第二ボタンまで開けているので、骨ばった鎖骨が覗いている。やや中性的ともとれる顔立ちの男性だが、こう見ると男性的だ。
優雅な所作で椅子を引いて着席すると、両手を合わせた。
「いただかせてもらおう。ああ、リゾットか、懐かしい」
「懐かしい、ですか?」
「そうだ」
近江はそれ以上は何も告げなかった。
「お口に合えば良いですが」
「俺はどんな料理でも食べるから気にしなくて良い」
そう言われると紗理奈としても少々癪だった。
近江が銀のスプーンを手に取り、リゾットを掬うと口へと運ぶ。しばらく口の中で咀嚼した後、ゆっくりと嚥下する。細身だが喉仏がしっかり太くて、上下する様がなんとなく妖艶だった。
そうして、彼は匙を持ったまま口を開く。
「うまいな」
近江が柔和な笑みを浮かべた。
一言だけだったが、心の奥底から満足しているような表情だった。
「どういたしまして」
トクン。
紗理奈の心臓が跳ね上がった。
心なしか頬が朱に染まる。
「どうした?」
彼女の異変に気付いたのか、近江が真顔で問いかけてきた。
「いいえ、兄に褒められて以来、誰かに褒められたのは久しぶりだなと思って」
「そうか」
それだけ言うと、近江は伏し目がちになりながら、次の一口を掬って口に運んでいく。
彼を見習って、紗理奈もリゾットを食べ始めた。
ふっくらしたご飯が、ほくほくと口の中で踊る。ミルクの甘みが口の中に広がっていくと同時に、コショウが舌先で弾けてスパイシーな香りが鼻腔を通っていく。
(我ながら美味しくできているわね)
母が兄に習ったという堂本家伝統のリゾットだ。
なんだか人恋しい時になんかよく作っていた。
「ごちそうさま」
全てを食べ終えた近江が両手を合わせて「ごちそうさま」と口にした後、紗理奈に向かって話し掛けてくる。
「とても美味だった。俺もこんな風に誰かの手料理を食べたのは、数年ぶりだった。感謝する」
表情がほとんど変わらない近江から感謝の念を告げられると、紗理奈としても悪い気はしなかった。
「どうしたしまして」
それからしばらく二人とも喋らなかった。
昼のバラエティ番組のにぎやかな音声が室内に響く。
「ごちそうさまです」
紗理奈が全てを食べ干して両手を合わせる。
すると、近江が話し掛けてきた。
「料理は兄に習ったのか?」
「ええ、そうですね。私が小学生の時に母が亡くなったので」
「そうか。先ほどのリゾットは兄直伝というわけだな」
「はい、そうなんです。お兄ちゃん、コショウをたくさん入れたがるから、小さい頃はよく喧嘩になっていました」
すると、近江がふっと口元を綻ばせた。
「そうか」
彼の表情は、どこか過去を懐かしむようなものに見えた。
ふと、近江が兄と年が近いことに思い至る。
「そういえば、近江さんはおいくつになられるんですか?」
「今年、三十を迎える予定だ」
「三十歳になるんですね」
兄も生きていたら、それぐらいの年になる。もしかすると、警察学校の同期だったりしないだろうか?
「そういえば、近江さん、同期の警察に――」