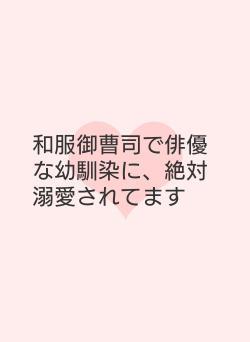紗理奈は気を取り直して問いかける。
「料理もそんなに上手じゃないですし」
「料理は俺が出来るから問題ない」
「掃除もそんなにできませんし」
「掃除は俺が好きだから構わない。そもそも最近は高性能の機械がある」
「洗濯と干すのはまあまあ好きですけど、畳むのは好きじゃありませんし」
「衣類が痛まないのが気にならないなら洗濯乾燥機がある。それに、俺は洗濯物を畳むのは好きだから、問題はない」
ことごとく論破されてしまった。
(男性だけど、家事が得意なのね、この人)
ひと昔前は女性の必須スキルだったが、今時は男性も家事は当然できるようだ。
どうにも相手が引いてはくれない。
とにかく相手を説得しようと、紗理奈は切り札を出す。
「男性と付き合ったことないし、おかしな真似をしないか心配ですし」
「奇遇だな。俺も誰とも付き合ったことがないから安心してほしい」
近江は無表情のままだが必死だ。
(ええっと、こんなに美青年なのに交際経験がないの……?)
それはそれで問題がある人物なのではないかと少々不安になってきた。
とはいえ、自分もないので、他人のことはあまりとやかくは言えない。
「それじゃあ! 私は仕事が好きなんです! 新聞記者に誇りを持っているんです! 仕事ばかりして家事をおろそかにします!」
「現代社会では男女共働きが当たり前だ。妻に家事全てを担ってもらいたいとは欠片も思っていない。そもそも夫婦のハードルが高いのならば恋人同士ならどうだ? すぐすぐ夫婦になるわけではない。どうだろう? 君を狙う犯人が捕まるまでの間だけでも? 他に何か支障はあるか?」
「……っ」
全てうまいこと論破されてしまった。
それにしたって、自意識過剰かもしれないけれど、通りの皆が自分たちの成り行きを見守っている気がする。新聞を読んだフリをしている私服警官と思しき男性も、チラチラこちらを覗いてきている。
こうなったら覚悟を決めるしかない。
紗理奈は顔を真っ赤にしながら返した。
「でしたら、恋人になって一緒に暮らしてください! お兄ちゃんの事件の犯人が捕まるまでの間で良ければですが!」
自棄になっての発言だったが、近江はこくりと頷いてきた。
「それは良い提案だ、そちらで頼む」
紗理奈は内心投げやりだった。
「だったら、しばらくの間、どうぞ恋人になってください」
しばらく相手からの返事はない。
恐る恐る見上げる。
近江がふっと口元を綻ばせた。
「よろしく頼む、堂本紗理奈」
ずっと不愛想だった近江が、頬を朱に染めながら笑う姿は、美青年なことも相まって破壊力がすごかった。
「……はい、どうぞよろしくお願いします」
かくして、紗理奈の護衛を兼ねた、近江との期間限定の恋人生活が始まったのだった。
「料理もそんなに上手じゃないですし」
「料理は俺が出来るから問題ない」
「掃除もそんなにできませんし」
「掃除は俺が好きだから構わない。そもそも最近は高性能の機械がある」
「洗濯と干すのはまあまあ好きですけど、畳むのは好きじゃありませんし」
「衣類が痛まないのが気にならないなら洗濯乾燥機がある。それに、俺は洗濯物を畳むのは好きだから、問題はない」
ことごとく論破されてしまった。
(男性だけど、家事が得意なのね、この人)
ひと昔前は女性の必須スキルだったが、今時は男性も家事は当然できるようだ。
どうにも相手が引いてはくれない。
とにかく相手を説得しようと、紗理奈は切り札を出す。
「男性と付き合ったことないし、おかしな真似をしないか心配ですし」
「奇遇だな。俺も誰とも付き合ったことがないから安心してほしい」
近江は無表情のままだが必死だ。
(ええっと、こんなに美青年なのに交際経験がないの……?)
それはそれで問題がある人物なのではないかと少々不安になってきた。
とはいえ、自分もないので、他人のことはあまりとやかくは言えない。
「それじゃあ! 私は仕事が好きなんです! 新聞記者に誇りを持っているんです! 仕事ばかりして家事をおろそかにします!」
「現代社会では男女共働きが当たり前だ。妻に家事全てを担ってもらいたいとは欠片も思っていない。そもそも夫婦のハードルが高いのならば恋人同士ならどうだ? すぐすぐ夫婦になるわけではない。どうだろう? 君を狙う犯人が捕まるまでの間だけでも? 他に何か支障はあるか?」
「……っ」
全てうまいこと論破されてしまった。
それにしたって、自意識過剰かもしれないけれど、通りの皆が自分たちの成り行きを見守っている気がする。新聞を読んだフリをしている私服警官と思しき男性も、チラチラこちらを覗いてきている。
こうなったら覚悟を決めるしかない。
紗理奈は顔を真っ赤にしながら返した。
「でしたら、恋人になって一緒に暮らしてください! お兄ちゃんの事件の犯人が捕まるまでの間で良ければですが!」
自棄になっての発言だったが、近江はこくりと頷いてきた。
「それは良い提案だ、そちらで頼む」
紗理奈は内心投げやりだった。
「だったら、しばらくの間、どうぞ恋人になってください」
しばらく相手からの返事はない。
恐る恐る見上げる。
近江がふっと口元を綻ばせた。
「よろしく頼む、堂本紗理奈」
ずっと不愛想だった近江が、頬を朱に染めながら笑う姿は、美青年なことも相まって破壊力がすごかった。
「……はい、どうぞよろしくお願いします」
かくして、紗理奈の護衛を兼ねた、近江との期間限定の恋人生活が始まったのだった。