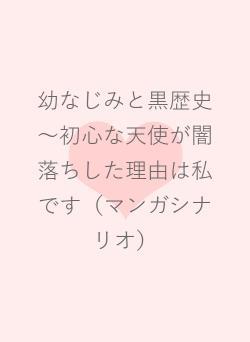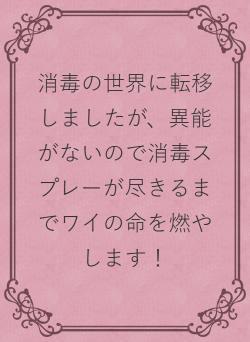「唯ちゃんひさしぶり。 突然だけど今週末、そちらにお泊りしてもいいですか?」
震える指で三角の送信ボタンを押したボクは、画面に残る文面を何度も読み直した。
(文章、変じゃないかな?)
時計は18時。
ボクは返信が来るまで何回もメールのチェックをした。
『ハーイ。』
19時すぎにようやく唯ちゃんから来た返信は、手のイラストのスタンプ一個だった。
(気張ってたのはボクだけか。)
ボクは一気に脱力してベットに倒れ込んだ。
※
「萌音、どこに行くの?」
スポーツバックに一泊分の着替えを詰めていると、ユウくんがボクの後ろから顏をのぞかせた。
「おばさんの唯ちゃんのうち。」
「昔、萌音がよく預けられていたおうちだよね・・・って、萌音が外出⁉」
ユウくんがマンガみたいにあんぐりと口を開ける。
クッ、かわいいかよ。
ほっこりしながら、ボクはバックのジッパーを閉めた。
「さすがユウくん。ボクのことは何でも知ってるね。」
「どうして?」
「唯ちゃんにも、魔法の糸のことを聞いてみようかと思って。もしかしたらおばあちゃんの手帳とかが残っていたら手がかりになるかもしれないから、直接行ったほうが早いかなって。」
「それならさ、ユウくんも一緒に行ってもいいでしょ? 僕の体のことだし。」
「あー・・・。」
当然のように腕を組んできたユウくんに、ボクは宙を見上げて答えを濁した。
ユウくんが、もし唯ちゃんにも見えるとしたら、ちょっと厄介だと思う。
万が一、お母さんに報告されたら困るし、年ごろの娘がブランケット少年と一緒に生活をしていることを問題視するかもしれない。
ユウくんはジロリとボクを横目で見た。
「もしかして、僕が唯ちゃんに見えるかもって心配してんの?」
う、当たり。
「あのね、この前こっそりお母さんの車に乗ってさ、一緒に街に行ってきたんだよ!」
「えー、街? いつの間にッ⁉」
「僕ね、たくさんの人間に出会って大発見したんだ。
子どもには僕の姿が人間に見えるけど、大人には僕の姿がブランケットに見えるみたい。」
私が寝ている間にユウくんが大暴走・・・じゃなくて大冒険をしていたらしい。
ユウくんはニッコリと素敵な笑顔をボクに向けた。
「だからー、僕も唯ちゃんちにお泊りしていいでしょう?」
ここまで言われたら、ダメって言えないじゃないか。
ボクはしぶしぶ頷いた。
「うん・・・いいよ。」
「わーい、萌音だいすき♡」
ユウくんがフワッとボクに抱きついてきて頬ずりした。
ぽわぽわした温かさが体に広がって、幸せな気分に包まれる。
思わずボクもつられて「だいすき」って言いそうになっちゃったことは、ユウくんにはヒミツにしよう。
※
日頃の行いが悪かったんだろうか。
唯ちゃんのうちに行く日に大雪警報が出てしまった。
玄関でお母さんが腕組みして呆れた顏をした。
「なにもこんな日に行かなくても。」
「もう行くって言ったもん。」
ボクはお母さんと目を合わせないようにブーツを履いた。
(いつもボクの否定ばっか。お母さんの言うことなんて、1ミリも聞きたくないんだから。)
頬を膨らませながら玄関を開けた瞬間に、風速13メートルの風がドアを押し戻そうとして、ボクは体をドアに押し付けながら家を出た。
※
予定よりも10分ほど遅れて到着した電車は雪まみれで、窓は曇っていた。
小学生のときにはじめて電車に乗った時には、まだ石油で動くディーゼル車が走っていた。
列に並んだ席の足元は、暖房が効きすぎて暑かった覚えがある。
電化した新しい車両は適温で快適だ。
けど、地下鉄みたいに席が向い合せになっていて、視線をどこに向けていいか分からない。
だからボクとユウくんは、入り口付近で立って乗車することにした。
駅に停車するたびに沢山の人が乗車してきて、ボクは慣れない人混みに緊張した。
閉鎖された車内は電車の走る音や集団の話し声がやたらと耳に響き、両手で耳をふさぎたくなる衝動にかられる。
(耐えなきゃ。)
俯いてブーツの先に溜まる水滴を眺めていると、いつものフランネルのパジャマに大きなリュックを背負ったユウくんがボクの顏をのぞきこんできた。
「萌音、顏が白いけど大丈夫?」
「うん。」
「座席空いてるから座ったら?」
優先席を指さすユウくんに苦笑いして、ボクは小声で囁いた。
「ユウくんがいるから平気だよ。」
ユウくんがクルリとボクの後ろに回り込み、背中合わせになってボクの体を支えた。
「ボクにもたれかかっていいからね。」
ボクは素直にユウくんに体重を預けた。
(ユウくんが居て良かった。)
ブランケットを頭から被ると落ち着くように、ユウくんの温度を背中に感じるだけで安心する。
ユウくんに背中を預けたボクは、ゴトンゴトンと揺れる振動に身をまかせて目を閉じた。
※
目的の駅に電車が止まると、ボクたちは開いた電車から慌ててホームに降り立った。
(危な! リラックスし過ぎて乗り過ごすところだった!!)
ノロノロと移動する人波に合流して出口に向うと、前方にジャージの一団を見かけた。
真冬にジャージにマフラーだけなんて、元気すぎ。
「あ!」
足早に横を通り抜けようとしたボクは、思わず小さく声を漏らした。
(うちの中学校の指定ジャージじゃないか!)
耳ざとくボクの声に反応したジャージのひとりが、不意に横を振り向いた。
それからアッと驚いた顏をしてボクを指さした。
「もしかして・・・古明地?」
聞き覚えのある、ハスキーな声。
ボクはその場に凍りついた。
「太陽先輩・・・。」
少しクセのあるマッシュヘアに意志の強そうな太い眉、バスケットボールの入ったカラフルな網のバック。
忘れもしない。
この人は、ボクの近所に住んでいる一年先輩。
しかも、ボクがバスで吐いた時にいちばん大騒ぎした人だ!
(ムリ!)
全身の血の毛が引くのを感じたボクは、脱兎のごとく改札口に向かう階段を走りだした。
「待てよ!」
なぜか先輩もボクの後を全力で追ってくる。
(ウソでしょ。なんでボクを追いかけてくるの⁉)
もっと速く走りたいけど、手足がガクガクして力が抜けてうまく走れない。
よく考えたら、走るのも一年ぶりのことで足の筋力がないのかもしれない。
息を切りながら振り返ると、すぐそこまで先輩が迫ってきている。
(もうダメ、追いつかれる!)
足がもつれて転びそうになったとき、突然、目の前に温かな気配がして体がグンと支えられた。
「ユウくん!」
目を開けると、ボクの体を支えたユウくんが、怖い顏で先輩の前に立ちはだかっていた。
あれ、いつの間に追い越されたんだろう?
「え・・・? お前、誰? どこから来たの?」
「僕はユウくん。萌音の友だち。」
「ユウくん? ウチの学校⁇」
バスケ部で足の速さには自信のある太陽先輩も、突然現れたユウくんに戸惑っている。
ユウくんは静かにボクを立たせると、そっと背中を押した。
「え、おい、ちょっと古明地・・・。」
「君は萌音に話しかけるな。」
「ハァ?」
「萌音、行っていいよ!」
「待てって、俺は古明地と話が・・・。」
ユウくんが両手を大きく広げて太陽先輩をけん制してくれる。
ボクはユウくんに手を合わせて頭を下げた。
「ユウくん、ゴメン! 唯ちゃんちで待ってるから‼」
ボクは全力で駅の通路を走った。
震える指で三角の送信ボタンを押したボクは、画面に残る文面を何度も読み直した。
(文章、変じゃないかな?)
時計は18時。
ボクは返信が来るまで何回もメールのチェックをした。
『ハーイ。』
19時すぎにようやく唯ちゃんから来た返信は、手のイラストのスタンプ一個だった。
(気張ってたのはボクだけか。)
ボクは一気に脱力してベットに倒れ込んだ。
※
「萌音、どこに行くの?」
スポーツバックに一泊分の着替えを詰めていると、ユウくんがボクの後ろから顏をのぞかせた。
「おばさんの唯ちゃんのうち。」
「昔、萌音がよく預けられていたおうちだよね・・・って、萌音が外出⁉」
ユウくんがマンガみたいにあんぐりと口を開ける。
クッ、かわいいかよ。
ほっこりしながら、ボクはバックのジッパーを閉めた。
「さすがユウくん。ボクのことは何でも知ってるね。」
「どうして?」
「唯ちゃんにも、魔法の糸のことを聞いてみようかと思って。もしかしたらおばあちゃんの手帳とかが残っていたら手がかりになるかもしれないから、直接行ったほうが早いかなって。」
「それならさ、ユウくんも一緒に行ってもいいでしょ? 僕の体のことだし。」
「あー・・・。」
当然のように腕を組んできたユウくんに、ボクは宙を見上げて答えを濁した。
ユウくんが、もし唯ちゃんにも見えるとしたら、ちょっと厄介だと思う。
万が一、お母さんに報告されたら困るし、年ごろの娘がブランケット少年と一緒に生活をしていることを問題視するかもしれない。
ユウくんはジロリとボクを横目で見た。
「もしかして、僕が唯ちゃんに見えるかもって心配してんの?」
う、当たり。
「あのね、この前こっそりお母さんの車に乗ってさ、一緒に街に行ってきたんだよ!」
「えー、街? いつの間にッ⁉」
「僕ね、たくさんの人間に出会って大発見したんだ。
子どもには僕の姿が人間に見えるけど、大人には僕の姿がブランケットに見えるみたい。」
私が寝ている間にユウくんが大暴走・・・じゃなくて大冒険をしていたらしい。
ユウくんはニッコリと素敵な笑顔をボクに向けた。
「だからー、僕も唯ちゃんちにお泊りしていいでしょう?」
ここまで言われたら、ダメって言えないじゃないか。
ボクはしぶしぶ頷いた。
「うん・・・いいよ。」
「わーい、萌音だいすき♡」
ユウくんがフワッとボクに抱きついてきて頬ずりした。
ぽわぽわした温かさが体に広がって、幸せな気分に包まれる。
思わずボクもつられて「だいすき」って言いそうになっちゃったことは、ユウくんにはヒミツにしよう。
※
日頃の行いが悪かったんだろうか。
唯ちゃんのうちに行く日に大雪警報が出てしまった。
玄関でお母さんが腕組みして呆れた顏をした。
「なにもこんな日に行かなくても。」
「もう行くって言ったもん。」
ボクはお母さんと目を合わせないようにブーツを履いた。
(いつもボクの否定ばっか。お母さんの言うことなんて、1ミリも聞きたくないんだから。)
頬を膨らませながら玄関を開けた瞬間に、風速13メートルの風がドアを押し戻そうとして、ボクは体をドアに押し付けながら家を出た。
※
予定よりも10分ほど遅れて到着した電車は雪まみれで、窓は曇っていた。
小学生のときにはじめて電車に乗った時には、まだ石油で動くディーゼル車が走っていた。
列に並んだ席の足元は、暖房が効きすぎて暑かった覚えがある。
電化した新しい車両は適温で快適だ。
けど、地下鉄みたいに席が向い合せになっていて、視線をどこに向けていいか分からない。
だからボクとユウくんは、入り口付近で立って乗車することにした。
駅に停車するたびに沢山の人が乗車してきて、ボクは慣れない人混みに緊張した。
閉鎖された車内は電車の走る音や集団の話し声がやたらと耳に響き、両手で耳をふさぎたくなる衝動にかられる。
(耐えなきゃ。)
俯いてブーツの先に溜まる水滴を眺めていると、いつものフランネルのパジャマに大きなリュックを背負ったユウくんがボクの顏をのぞきこんできた。
「萌音、顏が白いけど大丈夫?」
「うん。」
「座席空いてるから座ったら?」
優先席を指さすユウくんに苦笑いして、ボクは小声で囁いた。
「ユウくんがいるから平気だよ。」
ユウくんがクルリとボクの後ろに回り込み、背中合わせになってボクの体を支えた。
「ボクにもたれかかっていいからね。」
ボクは素直にユウくんに体重を預けた。
(ユウくんが居て良かった。)
ブランケットを頭から被ると落ち着くように、ユウくんの温度を背中に感じるだけで安心する。
ユウくんに背中を預けたボクは、ゴトンゴトンと揺れる振動に身をまかせて目を閉じた。
※
目的の駅に電車が止まると、ボクたちは開いた電車から慌ててホームに降り立った。
(危な! リラックスし過ぎて乗り過ごすところだった!!)
ノロノロと移動する人波に合流して出口に向うと、前方にジャージの一団を見かけた。
真冬にジャージにマフラーだけなんて、元気すぎ。
「あ!」
足早に横を通り抜けようとしたボクは、思わず小さく声を漏らした。
(うちの中学校の指定ジャージじゃないか!)
耳ざとくボクの声に反応したジャージのひとりが、不意に横を振り向いた。
それからアッと驚いた顏をしてボクを指さした。
「もしかして・・・古明地?」
聞き覚えのある、ハスキーな声。
ボクはその場に凍りついた。
「太陽先輩・・・。」
少しクセのあるマッシュヘアに意志の強そうな太い眉、バスケットボールの入ったカラフルな網のバック。
忘れもしない。
この人は、ボクの近所に住んでいる一年先輩。
しかも、ボクがバスで吐いた時にいちばん大騒ぎした人だ!
(ムリ!)
全身の血の毛が引くのを感じたボクは、脱兎のごとく改札口に向かう階段を走りだした。
「待てよ!」
なぜか先輩もボクの後を全力で追ってくる。
(ウソでしょ。なんでボクを追いかけてくるの⁉)
もっと速く走りたいけど、手足がガクガクして力が抜けてうまく走れない。
よく考えたら、走るのも一年ぶりのことで足の筋力がないのかもしれない。
息を切りながら振り返ると、すぐそこまで先輩が迫ってきている。
(もうダメ、追いつかれる!)
足がもつれて転びそうになったとき、突然、目の前に温かな気配がして体がグンと支えられた。
「ユウくん!」
目を開けると、ボクの体を支えたユウくんが、怖い顏で先輩の前に立ちはだかっていた。
あれ、いつの間に追い越されたんだろう?
「え・・・? お前、誰? どこから来たの?」
「僕はユウくん。萌音の友だち。」
「ユウくん? ウチの学校⁇」
バスケ部で足の速さには自信のある太陽先輩も、突然現れたユウくんに戸惑っている。
ユウくんは静かにボクを立たせると、そっと背中を押した。
「え、おい、ちょっと古明地・・・。」
「君は萌音に話しかけるな。」
「ハァ?」
「萌音、行っていいよ!」
「待てって、俺は古明地と話が・・・。」
ユウくんが両手を大きく広げて太陽先輩をけん制してくれる。
ボクはユウくんに手を合わせて頭を下げた。
「ユウくん、ゴメン! 唯ちゃんちで待ってるから‼」
ボクは全力で駅の通路を走った。