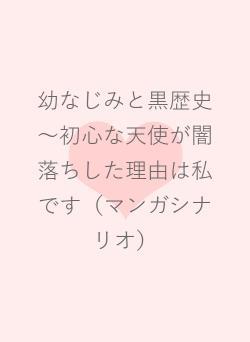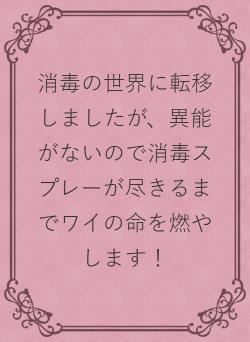「なんで俺、古明地の家にいるんだ⁉」
ボクの家の居間のソファで目覚めた瞬間、パニックになった太陽先輩が大騒ぎした。
「やだなぁ、先輩。忘れちゃったんですか?」
向かいのソファで本を読んでいたボクは、苦笑いしてキッチンから出てきたお母さんにアイコンタクトをした。
「忘れたって、何をだ?」
「何をって・・・ねぇ。」
ボクとお母さんは顏を見合わせて、用意していた台詞を口にした。
「汽車で久しぶりに会った先輩が、ボクの家で天体観測したいって言ったからですよ。」
「天体観測ゥ?」
「星が輝く夜中の0時に、ボクんちの庭にテント広げて一緒にコーンスープを飲みましたよ。」
「ええええ⁉ テント⁉ コーンスープ!?
ぜんっぜん、記憶にないんだが⁉」
そりゃそうだよ。
ボクは心の中で舌を出した。
太陽先輩を傷つけるというのはお芝居だったけど、運命の糸に関わった人の記憶は消さないといけないというのはお母さんの家に伝わる本当の掟だった。
お母さんからやり方を教わったボクは、木のボビンを使って太陽先輩の数日の記憶を消したのだ。
三人で一緒に過ごした日々。
太陽先輩がユウくんとケンカしたり、ボクに告白したりしたことも、全部・・・全部を消してしまった。
ボクは後味が悪くて寂しい気持ちになった。
けど、太陽先輩を家の特殊な都合に巻き込んでしまったのはボクのせいなのだから、ちゃんとしなきゃならない。
それがおばあちゃんが残した糸を受け継ぐという責任なんだ。
※
「そのあと家の前の氷で転んで頭打って、丸一日寝てたから・・・もしかして頭の打ちどころが悪くて記憶がないのかしら?」
カンペを棒読みのボクに比べて、太陽先輩を心配するお母さんは迫真の演技だ。
「そう・・・だったっけ?
でも、二人がそう言うのなら間違いないよな。」
萌々は知らんぷりしてブロック遊びをしている。
ブランケットじゃない太陽先輩には興味がないのか、人見知りが発動中なのかもしれない。
太陽先輩は後頭部を押さえて天井を見上げている。
「そんな気がしてきた。」
(よし、イイ感じに騙せてる。)
順調なお芝居に笑いそうになるボクとは違って、お母さんは女優ばりの演技を魅せる。
最後にトドメとばかりにクギを刺した。
「心配なら病院に行く?」
「や、病院なんてダセェっス。
スンマセン、逆にお世話になりました。」
お母さんはボクにだけ見えるようにウインクした。
素直すぎて詐欺に合わないか心配になるレベルだけど、根が単純なのは助かります。
律儀に頭を下げて家を出て行こうとする太陽先輩に、ボクはひと言声をかけたくなった。
「先輩、待って。」
呼び止めて振り返った先輩の笑顔が眩しくて、ボクは目を細めて笑った。
「また、いつでも遊びに来てくださいね。」
太陽先輩は、ポリポリと頬をかいてからボクをまっすぐに見た。
「ああ。お前こそ、明日からちゃんと学校来いよ。
待ってるからな。」
「・・・はい!」
ボクは太陽先輩の後ろ姿が見えなくなるまで手を振った。
(これで良かったんだよね、きっと。)
※
春の訪れとともに雪が融け魔法も解けて、ボクたちの日常が戻って来た。
いつもと違う朝なのは、早起きしたボクが学校の制服に袖を通したことだ。
窓の外から小鳥のさえずりが聞こえて、ボクは新しい靴下を履くと階段を降りた。
「ねね、どこ行くの?」
いつもと違う行動をするボクに、不思議そうな顔をする萌々。
ボクはお母さんが用意してくれたサンドイッチを食べながらミルクコーヒーを飲んだ。
「学校だよ。」
「がっこう?」
「人が沢山いて、勉強したりするところ。」
急に萌々が目を輝かせた。
「お友だちいっぱいいる?
ユウくんや、太陽も??」
ボクはユウくんの名前に胸の奥がズキンとした。
萌々はユウくんのこと、大好きだったもんね。
ボクは萌々の質問をはぐらかすように大きな声で話した。
「萌々も大きくなったら、一緒に学校に行こうね。」
「ヤダ、モモはがっこう行かない!」
萌々が急に足にしがみついてきて、ボクはビックリした。
「ねね、行かないでー!」
今までお母さんの後追いをすることがあっても、ボクが恋しくて泣かれることは無かったのに。
ボクは今まで厄介者だと思っていた萌々を、急に愛おしく感じてしまったんだ。
萌々の目線に高さを合わせて屈んだボクは、萌々の頭をヨシヨシと撫でて抱きしめた。
「心配しないで。
帰ってきたら、たくさん遊ぼうね。」
ゆびきりげんまんをした萌々は、涙と鼻水でグチャグチャになりながらボクに手を振った。
※
スクールバスの頭が坂道の向こうに見えて、ボクは大きく息を吸い込んだ。
「乗りまーす!」
ボクの目の前で停車したバス。
緊張しながらタラップを一段ずつ上がると、みんなの視線がボクひとりに注がれた。
シーン。
怖ッ・・・。
思わず後ずさりしそうになったボクの名前をハスキーな声が呼んだ。
「古明地、こっちに来いよ。」
太陽先輩が自分の横の席からリュックを退かした。
「おはようございます。」
ボクが縮こまりながら横の席に座ると、先輩がニヤリと笑った。
「これから毎日、ココが古明地の指定席だから。」
ボクは太陽先輩に笑顔で頷いた。
※
ボクの千切れたブランケットのユウくんは、新品のスモーキーピンクの糸で丁寧に繕った。
人はやる気になれば、何でもできる。
早速頭からすっぽり包まれる。
前回よりも満足できる仕上がり。
でも、ボクは言いようのない寂しさを覚えた。
ボクのスパダリ彼氏は、もう二度と喋らない。
甘えた声で「くるませて」って言ったり、優しく抱きしめたりしない。
でも、今のボクを見たユウくんなら、こう言うはずだ。
「良かったね、萌音。
僕は喋れなくても、いつでもここに居るよ。」
ボクはいつの間にか泣いていた。
もう簡単には泣かないつもりだったのに、熱い涙が溢れ出す。
胸が痛くてツライ。
この気持ちに名前はないのかな。
「好きだったけど、バイバイ。」
スモーキーピンクのフランネルのパジャマに艶々したプラチナの髪、砂糖より甘いボクの大切なユウくん。
「大好きだよ、萌音。」
そんな声が聴こえた気がして、ボクは窓を開け放った。
そのとたん、林の向こうに流れ星が夜空を駆け抜けた。
その流れ星が、ボクらの未来に重なって見えた気がしたんだ。
願っていれば、夢は夢じゃなくなる。
それはユウくんが教えてくれたんだよね。
ボクは服の袖で涙をぬぐった。
またユウくんに会う時まで、笑顔でいたい。
ボクは窓の外に手を伸ばして微笑んだ。
「またいつか会おうね。」
ボクの家の居間のソファで目覚めた瞬間、パニックになった太陽先輩が大騒ぎした。
「やだなぁ、先輩。忘れちゃったんですか?」
向かいのソファで本を読んでいたボクは、苦笑いしてキッチンから出てきたお母さんにアイコンタクトをした。
「忘れたって、何をだ?」
「何をって・・・ねぇ。」
ボクとお母さんは顏を見合わせて、用意していた台詞を口にした。
「汽車で久しぶりに会った先輩が、ボクの家で天体観測したいって言ったからですよ。」
「天体観測ゥ?」
「星が輝く夜中の0時に、ボクんちの庭にテント広げて一緒にコーンスープを飲みましたよ。」
「ええええ⁉ テント⁉ コーンスープ!?
ぜんっぜん、記憶にないんだが⁉」
そりゃそうだよ。
ボクは心の中で舌を出した。
太陽先輩を傷つけるというのはお芝居だったけど、運命の糸に関わった人の記憶は消さないといけないというのはお母さんの家に伝わる本当の掟だった。
お母さんからやり方を教わったボクは、木のボビンを使って太陽先輩の数日の記憶を消したのだ。
三人で一緒に過ごした日々。
太陽先輩がユウくんとケンカしたり、ボクに告白したりしたことも、全部・・・全部を消してしまった。
ボクは後味が悪くて寂しい気持ちになった。
けど、太陽先輩を家の特殊な都合に巻き込んでしまったのはボクのせいなのだから、ちゃんとしなきゃならない。
それがおばあちゃんが残した糸を受け継ぐという責任なんだ。
※
「そのあと家の前の氷で転んで頭打って、丸一日寝てたから・・・もしかして頭の打ちどころが悪くて記憶がないのかしら?」
カンペを棒読みのボクに比べて、太陽先輩を心配するお母さんは迫真の演技だ。
「そう・・・だったっけ?
でも、二人がそう言うのなら間違いないよな。」
萌々は知らんぷりしてブロック遊びをしている。
ブランケットじゃない太陽先輩には興味がないのか、人見知りが発動中なのかもしれない。
太陽先輩は後頭部を押さえて天井を見上げている。
「そんな気がしてきた。」
(よし、イイ感じに騙せてる。)
順調なお芝居に笑いそうになるボクとは違って、お母さんは女優ばりの演技を魅せる。
最後にトドメとばかりにクギを刺した。
「心配なら病院に行く?」
「や、病院なんてダセェっス。
スンマセン、逆にお世話になりました。」
お母さんはボクにだけ見えるようにウインクした。
素直すぎて詐欺に合わないか心配になるレベルだけど、根が単純なのは助かります。
律儀に頭を下げて家を出て行こうとする太陽先輩に、ボクはひと言声をかけたくなった。
「先輩、待って。」
呼び止めて振り返った先輩の笑顔が眩しくて、ボクは目を細めて笑った。
「また、いつでも遊びに来てくださいね。」
太陽先輩は、ポリポリと頬をかいてからボクをまっすぐに見た。
「ああ。お前こそ、明日からちゃんと学校来いよ。
待ってるからな。」
「・・・はい!」
ボクは太陽先輩の後ろ姿が見えなくなるまで手を振った。
(これで良かったんだよね、きっと。)
※
春の訪れとともに雪が融け魔法も解けて、ボクたちの日常が戻って来た。
いつもと違う朝なのは、早起きしたボクが学校の制服に袖を通したことだ。
窓の外から小鳥のさえずりが聞こえて、ボクは新しい靴下を履くと階段を降りた。
「ねね、どこ行くの?」
いつもと違う行動をするボクに、不思議そうな顔をする萌々。
ボクはお母さんが用意してくれたサンドイッチを食べながらミルクコーヒーを飲んだ。
「学校だよ。」
「がっこう?」
「人が沢山いて、勉強したりするところ。」
急に萌々が目を輝かせた。
「お友だちいっぱいいる?
ユウくんや、太陽も??」
ボクはユウくんの名前に胸の奥がズキンとした。
萌々はユウくんのこと、大好きだったもんね。
ボクは萌々の質問をはぐらかすように大きな声で話した。
「萌々も大きくなったら、一緒に学校に行こうね。」
「ヤダ、モモはがっこう行かない!」
萌々が急に足にしがみついてきて、ボクはビックリした。
「ねね、行かないでー!」
今までお母さんの後追いをすることがあっても、ボクが恋しくて泣かれることは無かったのに。
ボクは今まで厄介者だと思っていた萌々を、急に愛おしく感じてしまったんだ。
萌々の目線に高さを合わせて屈んだボクは、萌々の頭をヨシヨシと撫でて抱きしめた。
「心配しないで。
帰ってきたら、たくさん遊ぼうね。」
ゆびきりげんまんをした萌々は、涙と鼻水でグチャグチャになりながらボクに手を振った。
※
スクールバスの頭が坂道の向こうに見えて、ボクは大きく息を吸い込んだ。
「乗りまーす!」
ボクの目の前で停車したバス。
緊張しながらタラップを一段ずつ上がると、みんなの視線がボクひとりに注がれた。
シーン。
怖ッ・・・。
思わず後ずさりしそうになったボクの名前をハスキーな声が呼んだ。
「古明地、こっちに来いよ。」
太陽先輩が自分の横の席からリュックを退かした。
「おはようございます。」
ボクが縮こまりながら横の席に座ると、先輩がニヤリと笑った。
「これから毎日、ココが古明地の指定席だから。」
ボクは太陽先輩に笑顔で頷いた。
※
ボクの千切れたブランケットのユウくんは、新品のスモーキーピンクの糸で丁寧に繕った。
人はやる気になれば、何でもできる。
早速頭からすっぽり包まれる。
前回よりも満足できる仕上がり。
でも、ボクは言いようのない寂しさを覚えた。
ボクのスパダリ彼氏は、もう二度と喋らない。
甘えた声で「くるませて」って言ったり、優しく抱きしめたりしない。
でも、今のボクを見たユウくんなら、こう言うはずだ。
「良かったね、萌音。
僕は喋れなくても、いつでもここに居るよ。」
ボクはいつの間にか泣いていた。
もう簡単には泣かないつもりだったのに、熱い涙が溢れ出す。
胸が痛くてツライ。
この気持ちに名前はないのかな。
「好きだったけど、バイバイ。」
スモーキーピンクのフランネルのパジャマに艶々したプラチナの髪、砂糖より甘いボクの大切なユウくん。
「大好きだよ、萌音。」
そんな声が聴こえた気がして、ボクは窓を開け放った。
そのとたん、林の向こうに流れ星が夜空を駆け抜けた。
その流れ星が、ボクらの未来に重なって見えた気がしたんだ。
願っていれば、夢は夢じゃなくなる。
それはユウくんが教えてくれたんだよね。
ボクは服の袖で涙をぬぐった。
またユウくんに会う時まで、笑顔でいたい。
ボクは窓の外に手を伸ばして微笑んだ。
「またいつか会おうね。」