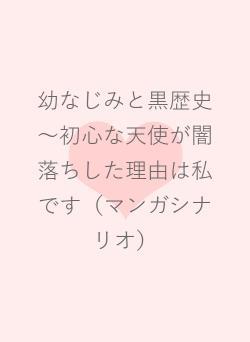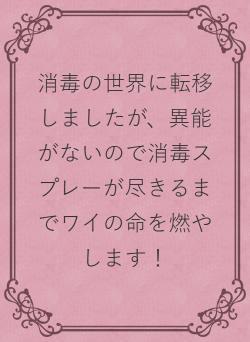マキア=おばあちゃん
ユウくんに包まれて頭の中が完璧なお花畑になっていたボクは、ユウくんの言葉を記憶の回路に紐づけするまでにやや時間がかかった。
そっか、そうだよ。
『マキア』はおばあちゃんの下の名前だった!
「ありがとうユウくん。すっかり忘れていたよ。
さすがだね!」
「でしょー。太陽より僕のほうが萌音のこと知ってるし、役に立つでしょー。」
「ハイハイハイ、充電しゅーりょー!」
「それは・・・。」
ユウくんがボクの肩に回した腕の隙間に、太陽先輩がグイグイ入り込んできた。
「ユウ、他の二人の名前には心当たりないのか?」
「わかんない。知ってても、太陽には教えないけど?」
ユウくんと太陽先輩の間に、緊張の糸が張り詰めている。
第2ラウンドのゴングがなる前に、違う話題にしなきゃ。
「あ、ちょっと待って。」
ボクはおばろげな記憶の引き出しから、ひとつの可能性を引っ張り出した。
「おばあちゃんのお葬式の時に、確かお母さんが『おばあちゃんは三姉妹』だって言ってた!」
「三姉妹? もしかしてその二人がエミとメレだったら・・・。」
「おばあちゃんたちが、運命の女神ってこと⁉」
「おい、声が大きい。シーッ!」
テンションが上がってつい大声を上げてしまったボクは、太陽先輩に咎められて我に返った。
まずい。
図書館にいるの、忘れてた!
(もしかして今、ボクひとりで叫んでる人に見えちゃってるの?)
カウンターの婦人が怪訝そうにこちらの様子をうかがっている。
周りの人たちの奇異な視線と囁き声に恥ずかしくなったボクは、太陽先輩とユウくんをつかんで逃げるように図書館を出た。
※
「ただいま。」
駐車場にお母さんの車がなかったから家には誰も居ないと思ったけど、一応、玄関で帰宅の挨拶はするのが習慣。
萌々とお母さんが居ない家は妙に静かだ。
居間のカレンダーの予定欄を確かめると、幼稚園の保護者レクと書いてある。
おばあちゃんの家に行く前に、お母さんがレクの後に給食を食べて帰ってくるって言ってたかもしれない。
給食いいなぁ。
可愛い園児たちの給食の光景を思い浮かべていたボクは、太陽先輩がキョロキョロと家の中を見まわしているのを見て、ハッとした。
「ちょっと二人ともここで待ってて。部屋片づけて来るから。」
「なんで?」
「良いって言うまで、絶対に二階に来ないでね!」
ユウくんが無邪気に聞いてきたけど、ボクは笑顔でスルーして階段を二段飛ばしで駆け上がった。
ベット周りに本やら雑貨やらを積み上げているのをなんとかしなくちゃ。
(いくら太陽先輩がブランケットだからって、ボクにも羞恥心があるんだ!)
※
物をしまったり掃除機をかけたりすると、どうしてこんなに物をため込んだのかといつも後悔することになる。
なかなかキレイにならない部屋を頑張って掃除していると、額からじんわりと汗が流れるのを感じた。
「あーあ。こんなことなら普段から掃除しておくんだった!」
無理に押し込めようとした本棚から、銀色の台紙の薄い本が飛び出した。
親戚の集合写真が収められているおばあちゃんのお葬式のメモリアルアルバムだ。
あまり親せきづきあいを好まないお母さんのせいで、ボクは親戚の名前と顏は良く知らない。
おかげで冠婚葬祭のときに不意に話しかけられると、ものすごく緊張するしうまく話を続けられなかった。
だからあまり写真を見返すことはなかったけど、今は違う。
ボクは胸が高鳴った。
(もしかしたら、この中にエミとメレが居るんじゃない?)
ドキドキしながら本を開き、見慣れない親せきの顏を一人ひとり見ていくと、喪服に身を包んだシルバーグレイの髪のおばあちゃんに目が留まった。「あれ? この人・・・。」
今日行った図書館のカウンターにいた司書の人に、雰囲気がソックリだ。
「顔も似てるかも。まさか・・・?」
ボクが記憶の映像と写真をリンクさせていると、階下から悲鳴が聞こえた。
「キャーッ!」
お母さんの声⁉
ボクは慌てて階段を駆け下りて居間のドアを開けた。
腰を抜かせているお母さんの前に、ユウくんと太陽先輩が引きつった顏をしている。
萌々は顏を輝かせて太陽先輩を指さしている。
「今動いてた! なにこれ?」
「このコ、俺が見えるのか?」
ボク以外には見えてないと思っていた太陽先輩が、慌ててテーブルの下に隠れた。
「シーッ。萌々、お喋りしないで!」
ユウくんが萌々の前に立って人差し指を口に当てたけど、遊びだと思った萌々はユウくんのマネをしている。
「ちょっと何なの、この動くタオルはッ・・・⁉」
「タオルじゃなくて、ブランケットだよー。」
「どっちでもいいわよ!」
床にへたり込んでパニックになっているお母さんの言葉に、ボクは耳を疑った。
「お母さん、もしかしてユウくんと太陽先輩が見えてるの⁉」
※
「見えてるわ。アンタのブランケットが人間の男の子になった時からね」
萌々の世話をユウくんと太陽先輩に任せて、ボクはお母さんにコーヒーを淹れてあげた。
ダイニングテーブルのベンチに腰かけたお母さんは落ち着きを取り戻している。
「ありがと。」
熱いブラックコーヒーをひと口すすってから、お母さんはほつれた髪を耳にかけた。
「魔女の力があるなら、最初から話してくれたら良かったのに。」
「ごめん。唯にはこの力が無かったし、まさか萌音に受け継がれていたなんて思いもしなかったから・・・。」
「お母さんとボクに魔女の力があるってこと?」
「あの人はそう言ってたけど、ちゃんと話し合ったことはないから実際のことはよく分からない。
ただ、あの木のボビンに触ったあとにはいつも不思議なことが起きたわ。」
「お母さんも、糸で物が人になったり人が物になったりしたことある?」
「それはないわ。私は能力を自覚してからは、あの糸に触れないようにしていたから。
この前話したぬいぐるみの夢のことくらいかしら。」
なぜだろう。
いつも大きく見えたお母さんが、今日は小さく見える。
「・・・私は、マトモな人間になりたかったの。」
語り出したお母さんの告白は、意外過ぎるものだった。
「昔から、みんなが見えないものが見えたり、聴こえないはずの声が聴こえてくるのが嫌だった。
だって、誰も信じてくれないし、頭がおかしいって思われるんだもの。
だから、見えていても見えないフリをするようになったの。」
ボクは胸がドキドキした。
ボクのお母さんは強い人なんだって思っていたけど、ぜんぜん違ったんだもん。
お母さんはため息を吐いて、震える両手を机の上で組んだ。
「萌音だけは私みたいにならないようにしたかったから、ユウくんが人間になっていても知らんぷりしていたの。
でもそれが萌音にとってはストレスになっていたようね。
病気扱いしたりして・・・本当に、ごめん。」
「謝らないでよ。」
ボクはいつもと違うお母さんの態度に胸が痛くなった。
いつもお母さんには反抗していたけど、そんな顏をさせたかったわけじゃない。
「ボクは大丈夫だから。」
そう口に出すと、深く立ち込めていた霧がスッと晴れていくみたいだった。
不思議と自分が強くなった気がする。
こんなに落ち着いてお母さんと話せたのはいつぶりだろう。
ボクは、萌々とかくれんぼをして遊んでいる黒いブランケットを一瞥してからお母さんに聞いた。
「今、ボクたちはおばあちゃんのパッチワークキルトに刺繡されていた名前について調べていたんだけど、エミとメレって誰か知ってる?」
「ああ、二人ともおばあちゃんの妹よ。」
おばあちゃんの妹ってことは、お母さんのおばさんだね。
私にとっての呼び名は・・・?
うーん。
よくわからないことを増やしてもしょうがないから、おばさんってことにしよう。
「メレおばさんとは連絡を取っていないけど、エミおばさんならおばあちゃんの家の近くの図書館で働いているはずよ。」
やっぱり!
ボクは記憶の回路がつながった気がして鳥肌が立った。
あのシルバーグレーの髪の年配の女性がエミさんだったんだ‼
ユウくんに包まれて頭の中が完璧なお花畑になっていたボクは、ユウくんの言葉を記憶の回路に紐づけするまでにやや時間がかかった。
そっか、そうだよ。
『マキア』はおばあちゃんの下の名前だった!
「ありがとうユウくん。すっかり忘れていたよ。
さすがだね!」
「でしょー。太陽より僕のほうが萌音のこと知ってるし、役に立つでしょー。」
「ハイハイハイ、充電しゅーりょー!」
「それは・・・。」
ユウくんがボクの肩に回した腕の隙間に、太陽先輩がグイグイ入り込んできた。
「ユウ、他の二人の名前には心当たりないのか?」
「わかんない。知ってても、太陽には教えないけど?」
ユウくんと太陽先輩の間に、緊張の糸が張り詰めている。
第2ラウンドのゴングがなる前に、違う話題にしなきゃ。
「あ、ちょっと待って。」
ボクはおばろげな記憶の引き出しから、ひとつの可能性を引っ張り出した。
「おばあちゃんのお葬式の時に、確かお母さんが『おばあちゃんは三姉妹』だって言ってた!」
「三姉妹? もしかしてその二人がエミとメレだったら・・・。」
「おばあちゃんたちが、運命の女神ってこと⁉」
「おい、声が大きい。シーッ!」
テンションが上がってつい大声を上げてしまったボクは、太陽先輩に咎められて我に返った。
まずい。
図書館にいるの、忘れてた!
(もしかして今、ボクひとりで叫んでる人に見えちゃってるの?)
カウンターの婦人が怪訝そうにこちらの様子をうかがっている。
周りの人たちの奇異な視線と囁き声に恥ずかしくなったボクは、太陽先輩とユウくんをつかんで逃げるように図書館を出た。
※
「ただいま。」
駐車場にお母さんの車がなかったから家には誰も居ないと思ったけど、一応、玄関で帰宅の挨拶はするのが習慣。
萌々とお母さんが居ない家は妙に静かだ。
居間のカレンダーの予定欄を確かめると、幼稚園の保護者レクと書いてある。
おばあちゃんの家に行く前に、お母さんがレクの後に給食を食べて帰ってくるって言ってたかもしれない。
給食いいなぁ。
可愛い園児たちの給食の光景を思い浮かべていたボクは、太陽先輩がキョロキョロと家の中を見まわしているのを見て、ハッとした。
「ちょっと二人ともここで待ってて。部屋片づけて来るから。」
「なんで?」
「良いって言うまで、絶対に二階に来ないでね!」
ユウくんが無邪気に聞いてきたけど、ボクは笑顔でスルーして階段を二段飛ばしで駆け上がった。
ベット周りに本やら雑貨やらを積み上げているのをなんとかしなくちゃ。
(いくら太陽先輩がブランケットだからって、ボクにも羞恥心があるんだ!)
※
物をしまったり掃除機をかけたりすると、どうしてこんなに物をため込んだのかといつも後悔することになる。
なかなかキレイにならない部屋を頑張って掃除していると、額からじんわりと汗が流れるのを感じた。
「あーあ。こんなことなら普段から掃除しておくんだった!」
無理に押し込めようとした本棚から、銀色の台紙の薄い本が飛び出した。
親戚の集合写真が収められているおばあちゃんのお葬式のメモリアルアルバムだ。
あまり親せきづきあいを好まないお母さんのせいで、ボクは親戚の名前と顏は良く知らない。
おかげで冠婚葬祭のときに不意に話しかけられると、ものすごく緊張するしうまく話を続けられなかった。
だからあまり写真を見返すことはなかったけど、今は違う。
ボクは胸が高鳴った。
(もしかしたら、この中にエミとメレが居るんじゃない?)
ドキドキしながら本を開き、見慣れない親せきの顏を一人ひとり見ていくと、喪服に身を包んだシルバーグレイの髪のおばあちゃんに目が留まった。「あれ? この人・・・。」
今日行った図書館のカウンターにいた司書の人に、雰囲気がソックリだ。
「顔も似てるかも。まさか・・・?」
ボクが記憶の映像と写真をリンクさせていると、階下から悲鳴が聞こえた。
「キャーッ!」
お母さんの声⁉
ボクは慌てて階段を駆け下りて居間のドアを開けた。
腰を抜かせているお母さんの前に、ユウくんと太陽先輩が引きつった顏をしている。
萌々は顏を輝かせて太陽先輩を指さしている。
「今動いてた! なにこれ?」
「このコ、俺が見えるのか?」
ボク以外には見えてないと思っていた太陽先輩が、慌ててテーブルの下に隠れた。
「シーッ。萌々、お喋りしないで!」
ユウくんが萌々の前に立って人差し指を口に当てたけど、遊びだと思った萌々はユウくんのマネをしている。
「ちょっと何なの、この動くタオルはッ・・・⁉」
「タオルじゃなくて、ブランケットだよー。」
「どっちでもいいわよ!」
床にへたり込んでパニックになっているお母さんの言葉に、ボクは耳を疑った。
「お母さん、もしかしてユウくんと太陽先輩が見えてるの⁉」
※
「見えてるわ。アンタのブランケットが人間の男の子になった時からね」
萌々の世話をユウくんと太陽先輩に任せて、ボクはお母さんにコーヒーを淹れてあげた。
ダイニングテーブルのベンチに腰かけたお母さんは落ち着きを取り戻している。
「ありがと。」
熱いブラックコーヒーをひと口すすってから、お母さんはほつれた髪を耳にかけた。
「魔女の力があるなら、最初から話してくれたら良かったのに。」
「ごめん。唯にはこの力が無かったし、まさか萌音に受け継がれていたなんて思いもしなかったから・・・。」
「お母さんとボクに魔女の力があるってこと?」
「あの人はそう言ってたけど、ちゃんと話し合ったことはないから実際のことはよく分からない。
ただ、あの木のボビンに触ったあとにはいつも不思議なことが起きたわ。」
「お母さんも、糸で物が人になったり人が物になったりしたことある?」
「それはないわ。私は能力を自覚してからは、あの糸に触れないようにしていたから。
この前話したぬいぐるみの夢のことくらいかしら。」
なぜだろう。
いつも大きく見えたお母さんが、今日は小さく見える。
「・・・私は、マトモな人間になりたかったの。」
語り出したお母さんの告白は、意外過ぎるものだった。
「昔から、みんなが見えないものが見えたり、聴こえないはずの声が聴こえてくるのが嫌だった。
だって、誰も信じてくれないし、頭がおかしいって思われるんだもの。
だから、見えていても見えないフリをするようになったの。」
ボクは胸がドキドキした。
ボクのお母さんは強い人なんだって思っていたけど、ぜんぜん違ったんだもん。
お母さんはため息を吐いて、震える両手を机の上で組んだ。
「萌音だけは私みたいにならないようにしたかったから、ユウくんが人間になっていても知らんぷりしていたの。
でもそれが萌音にとってはストレスになっていたようね。
病気扱いしたりして・・・本当に、ごめん。」
「謝らないでよ。」
ボクはいつもと違うお母さんの態度に胸が痛くなった。
いつもお母さんには反抗していたけど、そんな顏をさせたかったわけじゃない。
「ボクは大丈夫だから。」
そう口に出すと、深く立ち込めていた霧がスッと晴れていくみたいだった。
不思議と自分が強くなった気がする。
こんなに落ち着いてお母さんと話せたのはいつぶりだろう。
ボクは、萌々とかくれんぼをして遊んでいる黒いブランケットを一瞥してからお母さんに聞いた。
「今、ボクたちはおばあちゃんのパッチワークキルトに刺繡されていた名前について調べていたんだけど、エミとメレって誰か知ってる?」
「ああ、二人ともおばあちゃんの妹よ。」
おばあちゃんの妹ってことは、お母さんのおばさんだね。
私にとっての呼び名は・・・?
うーん。
よくわからないことを増やしてもしょうがないから、おばさんってことにしよう。
「メレおばさんとは連絡を取っていないけど、エミおばさんならおばあちゃんの家の近くの図書館で働いているはずよ。」
やっぱり!
ボクは記憶の回路がつながった気がして鳥肌が立った。
あのシルバーグレーの髪の年配の女性がエミさんだったんだ‼