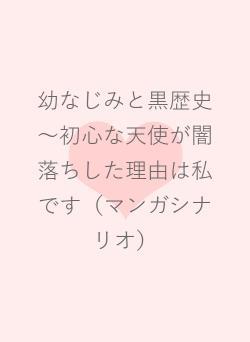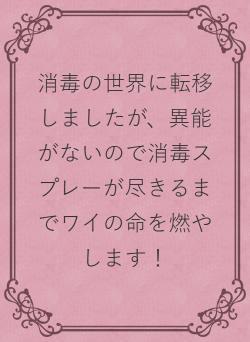「こんにちは、古明地 萌音さんですね。」
診察室の扉を少しだけ開いて中をのぞくと、笑顔の女医さんが出迎えてくれた。
その胸の名札には、精神内科医・佐藤と書いてある。
(お母さんと同じくらいの年かな?)
ボクはパーカーの帽子をキュッと被りなおして緊張する顏を覆い隠すと、診察室の丸い回転椅子に腰かけた。
佐藤先生は頭に乗せていた眼鏡を耳にかけて、机のカルテに目を通す。
「早速ですが教えてください。
今日は不登校の件で来院ということですが、それはいつ頃からなんですか?」
不登校
それを聞いた途端、胸が大きく『ドクン』と波打った。
手に汗を握っているのがバレないように、ボクはギュッと両手を握った。
「あの・・・。」
頭の中が真っ白になる。
先生はボクの様子をチラチラ見ながらカルテにペンを走らせた。
「例えば、何年前からとか何年生からとかは覚えていますか?」
「ええと・・・。」
ボクは佐藤先生と目を合わせないように、必死に壁に貼っているカレンダーを見るフリをしながら喋った。
「はじまりは、たぶん、中一のときの車酔いからだったと思います。」
「車酔い・・・おうちの車に乗ったんですか?」
ペンの動きを止めて、先生がボクを見つめた。
コミュ障な自分の説明ベタを反省しながら、ボクは話の順番を考えながら喋ることにした。
「いいえ、中学校のバスです。
うちは街を見下ろす丘の上に建っているので、スクールバスが家の前まで迎えにきてくれたんです。」
「なるほど。それで?」
佐藤先生は大きく相槌を打って、またカルテに目を向けた。
ボクはいちど息を吐いて、大きく息を吸い込んでから言葉を吐き出した。
「朝、いつものようにスクールバスに揺られていると『ガクン』とバスが急ブレーキで停車して前につんのめりました。その時に突然、胃の中から酸っぱいものがこみあげてきたんです。
ボクは慌てて口を手で押さえたんですけど、もう間に合いませんでした。
隣に座っていた幼なじみの男の先輩が「きたねー!」って叫ぶ声が頭の上に響いて、狭いバスの中はプチパニック状態になりました。」
その日の光景が目の前にフラッシュバックしてきて、ボクは言葉を詰まらせた。
※
セピア色に褪せた記憶。
バスの床に口から茶色い吐しゃ物が飛び散る。
学生たちは、スローモーションで蘇る。
「古明地が吐いた! 」
「ゲロ女、ヤバイ・・・」
「きたねー‼」
「待って、クサい!」
「こっちまで吐きそう‼」
ボクはみんなの前で嘔吐したことが、とにかくショックで恥ずかしかった。
学校に着くまでずっとバスの床に臥せっていた。
その日はいちにち保健室で過ごして、放課後は親に迎えに来てもらった。
次の日からは、朝、金縛りにあったように起きられなくなった。
どんなにお母さんが起こしに来ても、頭に霞がかかったように眠くて昼まで起きられないのだ。
それからは、まったく学校には行っていない。
ボクはまるで
中学生の幽霊だ。
※
「今日はここまでで終わりにしましょう。」
そう言って眼鏡を頭の上に戻した佐藤先生は、ボクに机の上の箱ティッシュを差し出してきた。
「あ、すみません。」
ボクはいつのまにか、鼻水が垂れるくらい泣いていた。
薬品棚のガラスに映る、涙でグチャグチャの赤い鼻の自分を横目に見ながら、ボクは思い切り鼻をかんだ。
「ありがとうございました。」
先生に会釈をしてそそくさと診察室を出ると、廊下のベンチに座っていたお母さんが足早に駆け寄ってきた。
「どうだったの?」
「ん-、ふつう。」
「ふつうって何よ。あら、目が赤くない?」
「欠伸しただけ。」
「なにか先生に言われなかったの?」
「なにかって何?」
「女の子なのに自分を『ボク』って言うこととか、アンタの病名とかよ。」
「病名? お母さんはボクが学校に行かないのは病気だと思ってるの?」
「違うわよ。私はいつも萌音のために・・・!」
その時、頭の上のスピーカーからくぐもった佐藤先生の声がした。
「古明地さん、お母さんだけ診察室へどうぞ。」
絶妙なタイミングのアナウンス。
お母さんは急いで診察室に入っていき、ボクはホッとして受付前の待合席に向かった。
(お母さんのこーゆーところ、だいきらい。)
でも、こんなところでケンカするのはみっともないし、エネルギーの無駄づかいもしたくなかった。
受付の待合席には三人の人が順番待ちをしている。
ボクはなるべく足音を立てないように一番後ろの席まで歩き、壁際のベンチに座って壁にもたれかかった。
(ハァ、早く帰りたいな。)
久しぶりの家以外の外の空気が苦い。
ボクのために会社を休んで病院の予約を取ってくれたお母さんには申し訳ないけど、正直、どうでもいいのが本音だ。
誰かに昔の話をすると頭の中がぐちゃぐちゃになるし、胸も異常にドキドキしてしまうから。
(そうだ・・・!)
ボクはリュックから大判のブランケットを取り出すと、ベンチの上に体育座りをしてすっぽりと体を包み込むようにくるまった。
「フゥ。」
いいにおい。
ボクはスモーキーピンクのブランケットの温かさにホッとして目を閉じた。
(あったかくて、モフモフで・・・しあわせ♡)
これはボクが赤ちゃんの時から使っていた、お気に入りのブランケット。
名前はユウくん。
ところどころは生地がヘタっているし、色あせもしていて年季がかっている。
成長するにしたがって、昔遊んでいたぬいぐるみを処分したり、大好きだった服や靴も親せきにあげたりした。
でも、このブランケットだけは捨てる気がしない。
唯一無二の、この世界にたった一つだけの宝物だから。
※
「またアンタは!」
鋭い金切り声が耳を貫いて、ボクは体を震わせた。
そおっとユウくんの陰から外を見ると、処方箋の紙を手にしたお母さんが怖い顔で立っている。
「またそんなものにくるまってるの? しかも人前で・・・恥ずかしいでしょ!」
まただ。
ボクの世界に、なんの断りもなく土足でズカズカと入り込んでくるお母さん。
人前で子供を叱るのは恥ずかしいことじゃないの?
こういうところが苛々するし、すごくムカつくんだよ。
(今日は、ケンカしないって決めて来たのに!)
ボクが下唇を噛んで黙っていると、お母さんが無理やりユウくんを引きはがした。
「ちょっ・・・何すんの⁉」
さすがに怒ったボクは力づくでユウくんを取り返そうとした。
でも、お母さんも布地の端を持って引っ張ってくる。
「返してよ!」
「こんなのに頼ってるから『起立めまい症』なんて病気になって、学校にも行けないのよ!」
起立めまい症?
そういう診断だったんだ。
ボクは頭だけスンと冷静になった。
(病名がつけば、お母さんも納得してボクを受け入れてくれるかと思ったけど・・・逆にストレスをかけたかな。)
ヒステリックに叫ぶお母さんに、周囲の人たちの視線がボクに集まる。
「離して。」
喉の奥から絞り出すような低い声を出すと、お母さんの苛立ちはピークに達した。
「何よ、その態度!」
お母さんが無理やりユウくんを引っ張ると、布地が耐えきれずに悲鳴をあげた。
ビリビリビリ・・・!
「アアッ‼」
ボクのユウくんは、真ん中から亀裂が入ってビリビリに破けてしまった。
「お母さんのバカー‼」
「ゴメン、萌音。わざとじゃ・・・。」
おろおろするお母さん。
ボクは周りの目もはばからず、大声をあげて泣き出した。
いろんな思い出が走馬灯のように巡って、目の前が真っ暗になる。
「信じられない・・・。お母さんなんて、大嫌い!」
診察室の扉を少しだけ開いて中をのぞくと、笑顔の女医さんが出迎えてくれた。
その胸の名札には、精神内科医・佐藤と書いてある。
(お母さんと同じくらいの年かな?)
ボクはパーカーの帽子をキュッと被りなおして緊張する顏を覆い隠すと、診察室の丸い回転椅子に腰かけた。
佐藤先生は頭に乗せていた眼鏡を耳にかけて、机のカルテに目を通す。
「早速ですが教えてください。
今日は不登校の件で来院ということですが、それはいつ頃からなんですか?」
不登校
それを聞いた途端、胸が大きく『ドクン』と波打った。
手に汗を握っているのがバレないように、ボクはギュッと両手を握った。
「あの・・・。」
頭の中が真っ白になる。
先生はボクの様子をチラチラ見ながらカルテにペンを走らせた。
「例えば、何年前からとか何年生からとかは覚えていますか?」
「ええと・・・。」
ボクは佐藤先生と目を合わせないように、必死に壁に貼っているカレンダーを見るフリをしながら喋った。
「はじまりは、たぶん、中一のときの車酔いからだったと思います。」
「車酔い・・・おうちの車に乗ったんですか?」
ペンの動きを止めて、先生がボクを見つめた。
コミュ障な自分の説明ベタを反省しながら、ボクは話の順番を考えながら喋ることにした。
「いいえ、中学校のバスです。
うちは街を見下ろす丘の上に建っているので、スクールバスが家の前まで迎えにきてくれたんです。」
「なるほど。それで?」
佐藤先生は大きく相槌を打って、またカルテに目を向けた。
ボクはいちど息を吐いて、大きく息を吸い込んでから言葉を吐き出した。
「朝、いつものようにスクールバスに揺られていると『ガクン』とバスが急ブレーキで停車して前につんのめりました。その時に突然、胃の中から酸っぱいものがこみあげてきたんです。
ボクは慌てて口を手で押さえたんですけど、もう間に合いませんでした。
隣に座っていた幼なじみの男の先輩が「きたねー!」って叫ぶ声が頭の上に響いて、狭いバスの中はプチパニック状態になりました。」
その日の光景が目の前にフラッシュバックしてきて、ボクは言葉を詰まらせた。
※
セピア色に褪せた記憶。
バスの床に口から茶色い吐しゃ物が飛び散る。
学生たちは、スローモーションで蘇る。
「古明地が吐いた! 」
「ゲロ女、ヤバイ・・・」
「きたねー‼」
「待って、クサい!」
「こっちまで吐きそう‼」
ボクはみんなの前で嘔吐したことが、とにかくショックで恥ずかしかった。
学校に着くまでずっとバスの床に臥せっていた。
その日はいちにち保健室で過ごして、放課後は親に迎えに来てもらった。
次の日からは、朝、金縛りにあったように起きられなくなった。
どんなにお母さんが起こしに来ても、頭に霞がかかったように眠くて昼まで起きられないのだ。
それからは、まったく学校には行っていない。
ボクはまるで
中学生の幽霊だ。
※
「今日はここまでで終わりにしましょう。」
そう言って眼鏡を頭の上に戻した佐藤先生は、ボクに机の上の箱ティッシュを差し出してきた。
「あ、すみません。」
ボクはいつのまにか、鼻水が垂れるくらい泣いていた。
薬品棚のガラスに映る、涙でグチャグチャの赤い鼻の自分を横目に見ながら、ボクは思い切り鼻をかんだ。
「ありがとうございました。」
先生に会釈をしてそそくさと診察室を出ると、廊下のベンチに座っていたお母さんが足早に駆け寄ってきた。
「どうだったの?」
「ん-、ふつう。」
「ふつうって何よ。あら、目が赤くない?」
「欠伸しただけ。」
「なにか先生に言われなかったの?」
「なにかって何?」
「女の子なのに自分を『ボク』って言うこととか、アンタの病名とかよ。」
「病名? お母さんはボクが学校に行かないのは病気だと思ってるの?」
「違うわよ。私はいつも萌音のために・・・!」
その時、頭の上のスピーカーからくぐもった佐藤先生の声がした。
「古明地さん、お母さんだけ診察室へどうぞ。」
絶妙なタイミングのアナウンス。
お母さんは急いで診察室に入っていき、ボクはホッとして受付前の待合席に向かった。
(お母さんのこーゆーところ、だいきらい。)
でも、こんなところでケンカするのはみっともないし、エネルギーの無駄づかいもしたくなかった。
受付の待合席には三人の人が順番待ちをしている。
ボクはなるべく足音を立てないように一番後ろの席まで歩き、壁際のベンチに座って壁にもたれかかった。
(ハァ、早く帰りたいな。)
久しぶりの家以外の外の空気が苦い。
ボクのために会社を休んで病院の予約を取ってくれたお母さんには申し訳ないけど、正直、どうでもいいのが本音だ。
誰かに昔の話をすると頭の中がぐちゃぐちゃになるし、胸も異常にドキドキしてしまうから。
(そうだ・・・!)
ボクはリュックから大判のブランケットを取り出すと、ベンチの上に体育座りをしてすっぽりと体を包み込むようにくるまった。
「フゥ。」
いいにおい。
ボクはスモーキーピンクのブランケットの温かさにホッとして目を閉じた。
(あったかくて、モフモフで・・・しあわせ♡)
これはボクが赤ちゃんの時から使っていた、お気に入りのブランケット。
名前はユウくん。
ところどころは生地がヘタっているし、色あせもしていて年季がかっている。
成長するにしたがって、昔遊んでいたぬいぐるみを処分したり、大好きだった服や靴も親せきにあげたりした。
でも、このブランケットだけは捨てる気がしない。
唯一無二の、この世界にたった一つだけの宝物だから。
※
「またアンタは!」
鋭い金切り声が耳を貫いて、ボクは体を震わせた。
そおっとユウくんの陰から外を見ると、処方箋の紙を手にしたお母さんが怖い顔で立っている。
「またそんなものにくるまってるの? しかも人前で・・・恥ずかしいでしょ!」
まただ。
ボクの世界に、なんの断りもなく土足でズカズカと入り込んでくるお母さん。
人前で子供を叱るのは恥ずかしいことじゃないの?
こういうところが苛々するし、すごくムカつくんだよ。
(今日は、ケンカしないって決めて来たのに!)
ボクが下唇を噛んで黙っていると、お母さんが無理やりユウくんを引きはがした。
「ちょっ・・・何すんの⁉」
さすがに怒ったボクは力づくでユウくんを取り返そうとした。
でも、お母さんも布地の端を持って引っ張ってくる。
「返してよ!」
「こんなのに頼ってるから『起立めまい症』なんて病気になって、学校にも行けないのよ!」
起立めまい症?
そういう診断だったんだ。
ボクは頭だけスンと冷静になった。
(病名がつけば、お母さんも納得してボクを受け入れてくれるかと思ったけど・・・逆にストレスをかけたかな。)
ヒステリックに叫ぶお母さんに、周囲の人たちの視線がボクに集まる。
「離して。」
喉の奥から絞り出すような低い声を出すと、お母さんの苛立ちはピークに達した。
「何よ、その態度!」
お母さんが無理やりユウくんを引っ張ると、布地が耐えきれずに悲鳴をあげた。
ビリビリビリ・・・!
「アアッ‼」
ボクのユウくんは、真ん中から亀裂が入ってビリビリに破けてしまった。
「お母さんのバカー‼」
「ゴメン、萌音。わざとじゃ・・・。」
おろおろするお母さん。
ボクは周りの目もはばからず、大声をあげて泣き出した。
いろんな思い出が走馬灯のように巡って、目の前が真っ暗になる。
「信じられない・・・。お母さんなんて、大嫌い!」