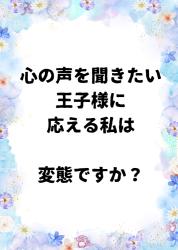彼女の横に座ると、驚いた顔をされた。
「仲よくなりましょうか、チェルシーさん。そうすれば、いずれ変わっていくわよ。周りの目も」
「……ありがとうございます。私の幻覚でないのなら……この世界はなんなのかなってずっと考えていたんです」
「そうね。それは気になるわ」
「現実でないことは明らかです。誰かがつくったゲームの人たちがいる世界なんて……クラスに山田太郎が三十人集まるよりあり得ないですよね」
……すごい例えだけど、確かにそうだ。今の例えに女の子がいないのが気になるわね。男子校を想定して言ったのかな。
「だから幻覚なのは当然で、それなのに他にこのゲームを知る人が現れた。そうですよね」
「……そうね。あなたの幻覚ってだけではないわ。私にも明確な意志があるし、前の世界の記憶もあるの」
「とすると、この世界はあの世でしかないですよね」
「まぁ……そうね」
やっぱり私は死んだのかな。大学生活にはもう戻れないのか……残念だ……。
「私には心残りがありました。彼氏が一度もできなかったことです。私、喪女なんです」
ええー……、いきなり何。
「誰かに告白とか考えられませんよね。何をどうしたらそんな流れになるんですか。そもそも告白できるくらいに仲のいい男性ってどーやったらできるんですか。どっかに気の合う男が落ちてくるガチャガチャとかあるんですか。無理ですよ。休日に一緒に遊びに行く男友達なんて都市伝説としか思えません。だからといって、よく知りもしない人に告白しようとも思えないし、絶対フラれるじゃないですか」
う……分かりみがすぎる……。
「――という喪女が転生する場所が、ここかもしれないって思うんです。18禁の乙女ゲーですし」
なに……その喪女のためのネバーランド。いきなりここが痛々しい場所に思えてきたわ。
残念ながら反論ができない。私も年齢イコール彼氏いない歴だ。大学デビューにも失敗し、男友達は皆無だ。私の表情から彼女もそれを察したようで、力なく微笑んだ。
「自分の言葉で話して好きになってもらえる自信がない。だから全てをあのゲームの通りになぞりました。アーロン様の台詞を直で聞きたかったから。そうでなければ、この幸せな幻覚が消えてしまうかとも思いました」
「仲よくなりましょうか、チェルシーさん。そうすれば、いずれ変わっていくわよ。周りの目も」
「……ありがとうございます。私の幻覚でないのなら……この世界はなんなのかなってずっと考えていたんです」
「そうね。それは気になるわ」
「現実でないことは明らかです。誰かがつくったゲームの人たちがいる世界なんて……クラスに山田太郎が三十人集まるよりあり得ないですよね」
……すごい例えだけど、確かにそうだ。今の例えに女の子がいないのが気になるわね。男子校を想定して言ったのかな。
「だから幻覚なのは当然で、それなのに他にこのゲームを知る人が現れた。そうですよね」
「……そうね。あなたの幻覚ってだけではないわ。私にも明確な意志があるし、前の世界の記憶もあるの」
「とすると、この世界はあの世でしかないですよね」
「まぁ……そうね」
やっぱり私は死んだのかな。大学生活にはもう戻れないのか……残念だ……。
「私には心残りがありました。彼氏が一度もできなかったことです。私、喪女なんです」
ええー……、いきなり何。
「誰かに告白とか考えられませんよね。何をどうしたらそんな流れになるんですか。そもそも告白できるくらいに仲のいい男性ってどーやったらできるんですか。どっかに気の合う男が落ちてくるガチャガチャとかあるんですか。無理ですよ。休日に一緒に遊びに行く男友達なんて都市伝説としか思えません。だからといって、よく知りもしない人に告白しようとも思えないし、絶対フラれるじゃないですか」
う……分かりみがすぎる……。
「――という喪女が転生する場所が、ここかもしれないって思うんです。18禁の乙女ゲーですし」
なに……その喪女のためのネバーランド。いきなりここが痛々しい場所に思えてきたわ。
残念ながら反論ができない。私も年齢イコール彼氏いない歴だ。大学デビューにも失敗し、男友達は皆無だ。私の表情から彼女もそれを察したようで、力なく微笑んだ。
「自分の言葉で話して好きになってもらえる自信がない。だから全てをあのゲームの通りになぞりました。アーロン様の台詞を直で聞きたかったから。そうでなければ、この幸せな幻覚が消えてしまうかとも思いました」