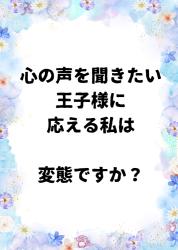「えっと……いるだけでいいのなら参加させていただきますわ。本当に面白いことは言えないのですが……」
「そこは気にしなくていいわ」
私の言葉にアーロンも賛同する。
「ああ、レイナがいてほしいと言うのなら僕も君を信用しよう」
「そうだな。レイナ嬢が君をご指名した。そこに意味はあると思っている。兄上を落としてくれてもいいよ。移り気のようだけどね」
「く……っ」
アーロンが言い返せなくて困っている。やっぱり国王陛下は腹黒いレヴィアスの方が向いていると思う。でも、私は王妃なんかになりたくないしなー……面倒くさそう。
ブレンダがぽわんとした顔をしながら小さな声で言う。
「私にそのような気立てはありませんわ。ただ……お飾りの妻がどうしてもご入用になりましたら私でよければ……」
「「「「「え」」」」」
五人ではもっちゃったよ……。
「ご、ごめんなさい。なんでもないですわ」
テレテレしながら慌てて誤魔化しているけれど、この視線……やっぱりそっちの趣味だ。自分を隠れ蓑にして王子同士でくっついてもいいです的ソレだ。
「すまない。僕の出自に気を遣ってくれているのか。君のことはよく知らないが、魅力的な女性だと思うよ。そんなに自分を卑下することはない」
そっか……そうとるのか。
愛人の子だもんね。アーロンからすれば、愛のために父親と同じことをしてもいいと言われたと思っているわけか。
「ありがとうございます……」
あれ、少しときめいちゃってる?
さっきよりも顔が赤い。
そういえばココ、喪女のためのネバーランドなんだっけ?
「ふぅん、今回のレイナ嬢の選択は悪くはなかったようだね」
「……あなたはよくないことを考えているでしょう、レヴィアス様。そんな顔をしているわ」
「人聞きが悪いな」
状況を見て、この二人の噂を流すくらいはしそうだ。うーん、婚約破棄未遂もあったことだし、噂を流すならどんなストーリーにするつもりだろう。
「それじゃ、気を取り直してお茶会を再開しよう。今日はマカロンを多く用意してもらった。どの味が君の好みかな」
基本的に優しいアーロンがややアウェーなブレンダに話を振る。
「そこは気にしなくていいわ」
私の言葉にアーロンも賛同する。
「ああ、レイナがいてほしいと言うのなら僕も君を信用しよう」
「そうだな。レイナ嬢が君をご指名した。そこに意味はあると思っている。兄上を落としてくれてもいいよ。移り気のようだけどね」
「く……っ」
アーロンが言い返せなくて困っている。やっぱり国王陛下は腹黒いレヴィアスの方が向いていると思う。でも、私は王妃なんかになりたくないしなー……面倒くさそう。
ブレンダがぽわんとした顔をしながら小さな声で言う。
「私にそのような気立てはありませんわ。ただ……お飾りの妻がどうしてもご入用になりましたら私でよければ……」
「「「「「え」」」」」
五人ではもっちゃったよ……。
「ご、ごめんなさい。なんでもないですわ」
テレテレしながら慌てて誤魔化しているけれど、この視線……やっぱりそっちの趣味だ。自分を隠れ蓑にして王子同士でくっついてもいいです的ソレだ。
「すまない。僕の出自に気を遣ってくれているのか。君のことはよく知らないが、魅力的な女性だと思うよ。そんなに自分を卑下することはない」
そっか……そうとるのか。
愛人の子だもんね。アーロンからすれば、愛のために父親と同じことをしてもいいと言われたと思っているわけか。
「ありがとうございます……」
あれ、少しときめいちゃってる?
さっきよりも顔が赤い。
そういえばココ、喪女のためのネバーランドなんだっけ?
「ふぅん、今回のレイナ嬢の選択は悪くはなかったようだね」
「……あなたはよくないことを考えているでしょう、レヴィアス様。そんな顔をしているわ」
「人聞きが悪いな」
状況を見て、この二人の噂を流すくらいはしそうだ。うーん、婚約破棄未遂もあったことだし、噂を流すならどんなストーリーにするつもりだろう。
「それじゃ、気を取り直してお茶会を再開しよう。今日はマカロンを多く用意してもらった。どの味が君の好みかな」
基本的に優しいアーロンがややアウェーなブレンダに話を振る。