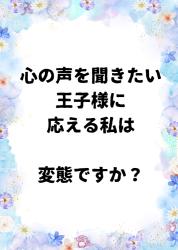「そんな勝手に――」
「根回しもそれまでに済ませる。もう決めたんだ。それまでに君も頑張りなよ。私を愛して、私に愛される努力をすればいい。兄上も納得させればいい。全て無理だったとしても、私は私のやりたいようにする。ああ、もしその気になってくれたのなら、すぐにでも話を進めるよ。安心するといい」
これは……微ヤンデレ系エス寄り第二王子との結婚しかないのか……なんという……。ま、まぁ喪女として、誰と何もできないよりかはいいかもしれないけど……でも……。
「現状、愛は……」
「今のところ、ないかな」
「やっぱり……」
ガックリしてしまう。
いつか誰かと好き合ってイチャイチャしてみたかったのに。
「でも、私には君がちょーどいいかとも思ったんだ」
「……私が嘘つきだから?」
あの場で嘘だとすぐに見抜いたんだろうか。
「ああ。嘘つきの相手は嘘つきの方がいいだろう?」
「……私のこと、優しくて慈悲深いなんて言っていたものね」
「ふっ……君はその言葉に嫌悪感を抱いていたようだけど」
見抜かれていたようだ。こいつ、聡いのよね……。周囲の人の感情の変化に敏感だ。嘘をついているのは私なのにという罪悪感をもったことに、あの場で気付いたのかな。
「あなたは望んでいないでしょうけど……国王陛下にはきっとあなたが相応しいわ。そして私は王妃に相応しくない」
「へ……え。つまり兄上がいいって?」
「それも嫌ね」
「我儘だな。愛なんてものがあるのかは分からないけど、兄上よりかはマシだと思ってもらいたいね。それを私は頑張るとしよう」
手を差し出され、すっと握る。
「……寮の屋上で、お茶会をするのよね?」
「なんでそれを――」
「ふふ、言ったじゃない。あなたを好きになる日がきたら教えてあげる。頑張りなさいな」
「……まいったな」
関係者しか上れない階段を進めば、広がるのは青い空と屋上のテラス。この世界で私を待ち受ける未来は――、エス寄りの彼とのエロエンドしかないのだろうか。
鬱エンドの回避だけは何がなんでもしなければと、決意を固くした。
「根回しもそれまでに済ませる。もう決めたんだ。それまでに君も頑張りなよ。私を愛して、私に愛される努力をすればいい。兄上も納得させればいい。全て無理だったとしても、私は私のやりたいようにする。ああ、もしその気になってくれたのなら、すぐにでも話を進めるよ。安心するといい」
これは……微ヤンデレ系エス寄り第二王子との結婚しかないのか……なんという……。ま、まぁ喪女として、誰と何もできないよりかはいいかもしれないけど……でも……。
「現状、愛は……」
「今のところ、ないかな」
「やっぱり……」
ガックリしてしまう。
いつか誰かと好き合ってイチャイチャしてみたかったのに。
「でも、私には君がちょーどいいかとも思ったんだ」
「……私が嘘つきだから?」
あの場で嘘だとすぐに見抜いたんだろうか。
「ああ。嘘つきの相手は嘘つきの方がいいだろう?」
「……私のこと、優しくて慈悲深いなんて言っていたものね」
「ふっ……君はその言葉に嫌悪感を抱いていたようだけど」
見抜かれていたようだ。こいつ、聡いのよね……。周囲の人の感情の変化に敏感だ。嘘をついているのは私なのにという罪悪感をもったことに、あの場で気付いたのかな。
「あなたは望んでいないでしょうけど……国王陛下にはきっとあなたが相応しいわ。そして私は王妃に相応しくない」
「へ……え。つまり兄上がいいって?」
「それも嫌ね」
「我儘だな。愛なんてものがあるのかは分からないけど、兄上よりかはマシだと思ってもらいたいね。それを私は頑張るとしよう」
手を差し出され、すっと握る。
「……寮の屋上で、お茶会をするのよね?」
「なんでそれを――」
「ふふ、言ったじゃない。あなたを好きになる日がきたら教えてあげる。頑張りなさいな」
「……まいったな」
関係者しか上れない階段を進めば、広がるのは青い空と屋上のテラス。この世界で私を待ち受ける未来は――、エス寄りの彼とのエロエンドしかないのだろうか。
鬱エンドの回避だけは何がなんでもしなければと、決意を固くした。