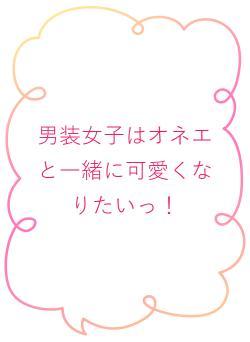前回までのあらすじ。
社員旅行に社長がついてきた。
社長はヘヴィーなメタルが好きだった。
あと女子社員をフッた。
「カードゲーム、あんなにいた女子が来なくなりましたね……」
喫煙室の常連だった男性社員が寂しそうに独りごちた。
会議室には男性社員数人と、私と、社長だけ。あんなににぎやかだった会議室はがらんとしている。
「わたくしの歌に引かれたんでしょうね……」
社長はあの社員旅行から、女子社員に囲まれることがなくなった。
一応挨拶とか、お土産を持ってきたときに軽く世間話をするくらいはあるが、ガチ恋勢はたしかに少なくなったように感じる。
多分歌だけじゃなくて、女子社員をフッたあの件もあるんだろうな、と私は思った。
社長が「こずえさんしか愛せない」「こずえさんに手荒な真似をしたらわたくしが許さない」と発言したことは大きな影響を与えたように思う。
噂は真実として伝わり、私たちは会社公認のカップルとなっていた。
「まあ、結局は出会い目的でカードゲームをしていた、ということなのでしょう」
社長は悲しそうに言った。そういえば、喫煙室でカードゲームをしていたときも、「出会い目的でのカードゲームは見過ごせない」と言っていた気がする。
なんだか、女子社員たちにカードゲームを教えた私が申し訳なくなってしまう。
「しっかし、まさか能登原さんがマジで社長の彼女になってしまうとは……」
男性社員は未だに信じられないといった様子で言う。
「まあ、喫煙室に連れてきたときから仲いいなとは思ってたけどな」
別の男性社員がそう返す。
「社長、どうします? 会議室使う意味なくなりましたし、また喫煙室に戻ります?」
「いえ、こずえさんに副流煙を吸わせるのはちょっと」
「ハハッ、大事にされてるなあ、能登原さん」
「か、からかわないでください……」
男性社員に茶化されて、私は頬を染める。
「そうだ、こないだ言ってたレアカード、見せてよ。たしか『悪魔の証明』と『神殺しのニーチェ』引いたんでしょ?」
「うっそ、マジすか!? ホント能登原さん持ってるなあ」
男性社員がそう言いながら自らの腕を叩く。「持ってるなあ」というのは強運を持っているという意味だ。
実際私も運がいいほうだと思う。今、『マジック&サマナーズ』では無料で毎日10枚ずつカードパックが引けるキャンペーンをやっているのだが、結構レアカードが引けた。無課金でも課金勢に対抗できる手札が増えたのは純粋に嬉しい。
「えっ、『神殺しのニーチェ』なんてわたくしも持っていませんよ? ちょっと見せていただいても?」
「あ、はい」
『マジック&サマナーズ』にけっこうな大金をつぎこんでいると噂の社長が持ってないカードがあるなんて意外だ。まあカードパックは現実のカードと同じで運次第なところはある。スマホ版は現物と違ってネットオークションで買えたりはしないし。
「能登原さん、神の指でも持ってるんじゃないの?」
「あ、じゃあ今度からカードパック引く時、能登原さんにスマホタップしてもらおうかな」
「それで外れても文句言わないでくださいよ?」
もうこのくらいの付き合いになると、私もだいぶ慣れてきて、男性社員に冗談めいたことも言えるようになってきた。
「じゃあそろそろ昼休みも終わるし、解散しますか~」
「お疲れ様でした、また明日」
「能登原さん、明日は日曜日だから会社来ちゃダメだよ」
「あ、そうでした」
男性社員はハハハと笑いながら去っていった。
社長と私は並んで廊下を歩く。昼休みを終えると社長が私を総務部まで送ってくれるのはもはや日課となっていた。
「こずえさん、明日はご予定ありますか?」
「社長、会社では名字で呼んでください」
「もういい加減いいと思うんですけどねえ……」
わたくしたちの仲はもう公認でしょう? と社長が笑う。
「仕事とプライベートの線引きはきっちりしておきたいので」
「わかりました。能登原さん、明日はご予定ありますか?」
社長は名字で私を呼んで、同じ質問を繰り返す。
「予定……はないですね」
家でプラモを作ろうと思っていたが、予定ではないな、うん。
「お花見デートとか、いかがでしょうか」
お花見デート。デート。デートかあ……。
いかにも恋人っぽい単語を脳内で反復する。
「プライベートでは外に出たがらない社長が珍しいですね」
「ええ、本当は能登原さんを家の中で独占したいのですが、いかんせんわたくしの家の庭に桜はないもので」
ど、独占って……。
社長はときどき恥ずかしいことを平気で口にする。
「それに、たまにはふたりで散歩などするのもいいかな、と思いまして。……いかが、でしょうか?」
社長は小首をかしげて私を見る。
まあ、断る理由はない。桜は私も見たいと思っていた。それにしても桜は何故あんなにも日本人を惹きつけてやまないのだろうか。
「お弁当、作りますか?」
「作ってくださるんですか?」
社長がぱあっと目を輝かせる。くっ……可愛い……。
社長と付き合う前はひたすらかっこいい王子様キャラだと思っていたが、付き合うようになってからはだんだん可愛い側面も見えるようになってきた。
「では、場所と日時はのちほどLIMEでお伝えします。当日お迎えに上がりますね」
ちょうど総務部の部屋に着いて、社長はそう言い残して去った。
お弁当かあ、何作ればいいんだろう。やっぱり唐揚げとか卵焼きとかが定番かな。
最近の私はわりと心身ともに調子が良くて、書類作成もスムーズに進む。
キーボードを叩きながら、お弁当の献立を考えるのはとても楽しい時間だった。
***
お花見デート当日。
LIMEで伝えられた時間きっかりに、社長は車で迎えに来た。
助手席に乗り込んで、連れてこられた場所は、都内の広い公園。土を盛って芝生を植えた丘や人工的なレンガの小道などがある。今日は天気もよく、日曜日なので家族連れやカップルが多い。
「行きましょうか」
車を駐車場に停めて、ふたりで車を降りる。社長――スバルさんは、私の手を取って、指を絡める。なるほど、これが恋人繋ぎってやつですね。わかります。
冷静なふりをしているが、内心、すでに脈拍がバクバク言っている。恋人繋ぎだけで私は瀕死である。心臓がもたない。
「こちらです」
スバルさんは私の手を引いて導いてくれる。
散歩、と言っていたが、まさしくそんな感じで、私の歩幅に合わせてゆっくり歩いてくれる。スバルさんは足が長いし普段は結構歩くスピードも速いんだけど、私と一緒のときはゆっくり歩いてくれて、それがとても嬉しい。
公園の小道を歩いていくと途中から花壇が小道の両脇にあって、色んな花が咲き乱れている。まさに春って感じだ。私は花に詳しくないからチューリップくらいしか分からないけど。
「きれいですね」
「そうですね。でもまだ主役が登場していませんよ」
スバルさんが私と繋いでいる手とは反対の手を口に当ててクスリと笑う。
「――着きました」
「……わぁ……!」
しばらく小道を歩いて公園の端っこまで来ただろうか。ちょうど丘の裏側だ。
桜がいくつも並んで咲き誇る光景はまさしく絶景というやつだろう。
「秘書の方に教えていただいたんですが、ここは穴場らしいですよ」
たしかに、こんなにきれいなのに人はいないようだ。公園の端っこまでかなり歩くのでここまで辿り着く人もいないのだろう。
ちょうど桜に囲まれた場所にぽつんとベンチが置いてあったので、ふたりで並んで座る。
「お口に合うといいのですが……」
私はショルダーバッグからお弁当の包みを取り出す。あまり激しく動いてないとはいえ、中身崩れてないといいんだけど。
弁当箱を開くと、中身は崩れてなくて安心した。とりあえず唐揚げとか、卵焼きとか、おにぎりとか、定番のものを入れておいた。
「美味しそうですね」
社長は心底嬉しそうに言う。美味しそうだなんて、シェフを雇って料理を食べているような人が、買いかぶり過ぎではないのか。
「食べてもいいですか?」
「どうぞ。そのために作ったので」
私はスバルさんに割り箸を渡す。
スバルさんは割り箸を割って、唐揚げを口に入れる。
「――美味しい。これ、手作りなんですか?」
「まあ、自分で作れる料理なので」
私はしれっとした顔をしたが、その実、スバルさんに喜んでほしくて全部頑張って手作りしたのは内緒の話である。
しかし、スバルさんの口にあったようで本当によかった、と密かに安堵する。
「……こずえさん、あーんしてください」
「え?」
スバルさんが唐揚げを箸で持って私の目の前に差し出す。
「わ、私が食べるんですか?」
「ふふ、一度こういうのやってみたかったんですよね」
……。
私は顔が熱くなるのを感じながら、おずおずと口を開ける。
唐揚げが口の中に入って、それを幸せごと噛みしめる。
なんだかすっごく恋人っぽいことをしている。いや、恋人だった。
「美味しいですか?」
「……美味しいです」
一応味見はしたんだけど、冷めても美味しいのが確認できた。
「でも、こういうのって普通逆っていうか……女性が男性に食べさせるものでは……」
「え? やってくださるんですか?」
しまった、罠だ!
スバルさんはその言葉を待っていたと言わんばかりに、目を細めて弧を描いた。
「是非お願いいたします」
そう言って、スバルさんは「あ」の形に口を開けて待っている。やるしかない雰囲気。
私は震える手で卵焼きを割り箸でつまみ、スバルさんの口に入れる。
スバルさんはゆっくり咀嚼し、飲み込んだ。喉仏が動くその様子さえ目をそらせないほど見入ってしまう。
「……やっぱり、こういうのはいいですね」
スバルさんは妖しげな笑みを浮かべる。
「……率直に言っていいですか」
「なんです?」
私の言葉に、スバルさんは首を傾ける。
「ひな鳥にご飯をあげる親鳥の気分でした」
「……ふっ、くくっ」
私の感想に、スバルさんは腹の底からおかしそうにふき出す。
「手厳しいですね、こずえさんは」
「もともとはこういう性格なんです」
「ふふ、隠さなくなったのは嬉しいですよ」
スバルさんのおかげだ、と私は思う。
スバルさんは自分を偽ったりしない。会社でも堂々とカードゲームをするし、オタク趣味を隠さない。それでも彼は社員たちから愛された。そんな彼がまぶしかった。
そう伝えると、「わたくしもこずえさんのおかげで救われましたよ」と言われて耳を疑った。
「こずえさんだけはわたくしに幻滅しないと信じていたから、わたくしの本当に好きな歌を歌うことが出来たんです」
それは、社員旅行での宴会の話か。
「わたくしがああいった歌を歌うと、女性はみんな離れていきました。みんな勝手に勘違いして集まってきたくせに、『イメージと違う』と去っていくのです」
スバルさんは悲しそうだった。
「スバルさん……」
「でも、こずえさんは『かっこいい』と言ってくれましたよね」
男性社員の大歓声で聞こえたはずがないのに、伝わっていた、のか。
「それに、結果的にはこれでよかったのかもしれません。こずえさんは、女性たちの攻撃を受けるのが怖かったんでしょう?」
スバルさんは、私の悩んでいた内容を知っていたのか。びっくりして、声が詰まった。
「わたくしは、他の女性に嫌われても、こずえさんさえいてくだされば、それでいいんです」
スバルさんは、はっきりそう言った。桜が舞い散る中で、スバルさんの清々しい笑顔が美しかった。
「――そろそろ帰りましょうか。お弁当、作ってくださってありがとうございます。ごちそうさまでした」
弁当をぺろりと平らげて、スバルさんはベンチから立ち上がる。
私も、弁当の包みをバッグにしまい、スバルさんに手を取られて立ち上がった。
私たちは、車の中で無言だった。
私の家に着いて、助手席から降りようとすると、スバルさんが手首を握った。
もう「なんですか」とは訊かない。あのときと同じ、また唇が重なった。
「――次の約束をしても、いいですか」
スバルさんは、真剣な表情で訊ねる。
「夏になったら、花火大会を見に行きませんか」
「随分先の約束をするんですね」
今はまだ桜が散り始めたくらいの季節だ。ギリギリ花見ができるくらいの。
「こずえさんとこうして未来の話をして、こずえさんが肯定してくださったら、わたくしはそれだけで満たされるんです」
「……はい。行きましょうね、花火」
私たちは、子供のように指切りをする。……もしスバルさんと小学生の時に一緒のクラスだったりしたら、他の男子が遊んでくれなくても、私の相手をしてくれただろうか。
私のほうこそ、スバルさんに救われている。子供の頃のひとりぼっちだった私の心の傷を、スバルさんが癒やしてくれているのだ。
スバルさんは名残惜しそうにそっと私の頬を撫でてから、車を走らせて去っていくのだった。
〈続く〉
社員旅行に社長がついてきた。
社長はヘヴィーなメタルが好きだった。
あと女子社員をフッた。
「カードゲーム、あんなにいた女子が来なくなりましたね……」
喫煙室の常連だった男性社員が寂しそうに独りごちた。
会議室には男性社員数人と、私と、社長だけ。あんなににぎやかだった会議室はがらんとしている。
「わたくしの歌に引かれたんでしょうね……」
社長はあの社員旅行から、女子社員に囲まれることがなくなった。
一応挨拶とか、お土産を持ってきたときに軽く世間話をするくらいはあるが、ガチ恋勢はたしかに少なくなったように感じる。
多分歌だけじゃなくて、女子社員をフッたあの件もあるんだろうな、と私は思った。
社長が「こずえさんしか愛せない」「こずえさんに手荒な真似をしたらわたくしが許さない」と発言したことは大きな影響を与えたように思う。
噂は真実として伝わり、私たちは会社公認のカップルとなっていた。
「まあ、結局は出会い目的でカードゲームをしていた、ということなのでしょう」
社長は悲しそうに言った。そういえば、喫煙室でカードゲームをしていたときも、「出会い目的でのカードゲームは見過ごせない」と言っていた気がする。
なんだか、女子社員たちにカードゲームを教えた私が申し訳なくなってしまう。
「しっかし、まさか能登原さんがマジで社長の彼女になってしまうとは……」
男性社員は未だに信じられないといった様子で言う。
「まあ、喫煙室に連れてきたときから仲いいなとは思ってたけどな」
別の男性社員がそう返す。
「社長、どうします? 会議室使う意味なくなりましたし、また喫煙室に戻ります?」
「いえ、こずえさんに副流煙を吸わせるのはちょっと」
「ハハッ、大事にされてるなあ、能登原さん」
「か、からかわないでください……」
男性社員に茶化されて、私は頬を染める。
「そうだ、こないだ言ってたレアカード、見せてよ。たしか『悪魔の証明』と『神殺しのニーチェ』引いたんでしょ?」
「うっそ、マジすか!? ホント能登原さん持ってるなあ」
男性社員がそう言いながら自らの腕を叩く。「持ってるなあ」というのは強運を持っているという意味だ。
実際私も運がいいほうだと思う。今、『マジック&サマナーズ』では無料で毎日10枚ずつカードパックが引けるキャンペーンをやっているのだが、結構レアカードが引けた。無課金でも課金勢に対抗できる手札が増えたのは純粋に嬉しい。
「えっ、『神殺しのニーチェ』なんてわたくしも持っていませんよ? ちょっと見せていただいても?」
「あ、はい」
『マジック&サマナーズ』にけっこうな大金をつぎこんでいると噂の社長が持ってないカードがあるなんて意外だ。まあカードパックは現実のカードと同じで運次第なところはある。スマホ版は現物と違ってネットオークションで買えたりはしないし。
「能登原さん、神の指でも持ってるんじゃないの?」
「あ、じゃあ今度からカードパック引く時、能登原さんにスマホタップしてもらおうかな」
「それで外れても文句言わないでくださいよ?」
もうこのくらいの付き合いになると、私もだいぶ慣れてきて、男性社員に冗談めいたことも言えるようになってきた。
「じゃあそろそろ昼休みも終わるし、解散しますか~」
「お疲れ様でした、また明日」
「能登原さん、明日は日曜日だから会社来ちゃダメだよ」
「あ、そうでした」
男性社員はハハハと笑いながら去っていった。
社長と私は並んで廊下を歩く。昼休みを終えると社長が私を総務部まで送ってくれるのはもはや日課となっていた。
「こずえさん、明日はご予定ありますか?」
「社長、会社では名字で呼んでください」
「もういい加減いいと思うんですけどねえ……」
わたくしたちの仲はもう公認でしょう? と社長が笑う。
「仕事とプライベートの線引きはきっちりしておきたいので」
「わかりました。能登原さん、明日はご予定ありますか?」
社長は名字で私を呼んで、同じ質問を繰り返す。
「予定……はないですね」
家でプラモを作ろうと思っていたが、予定ではないな、うん。
「お花見デートとか、いかがでしょうか」
お花見デート。デート。デートかあ……。
いかにも恋人っぽい単語を脳内で反復する。
「プライベートでは外に出たがらない社長が珍しいですね」
「ええ、本当は能登原さんを家の中で独占したいのですが、いかんせんわたくしの家の庭に桜はないもので」
ど、独占って……。
社長はときどき恥ずかしいことを平気で口にする。
「それに、たまにはふたりで散歩などするのもいいかな、と思いまして。……いかが、でしょうか?」
社長は小首をかしげて私を見る。
まあ、断る理由はない。桜は私も見たいと思っていた。それにしても桜は何故あんなにも日本人を惹きつけてやまないのだろうか。
「お弁当、作りますか?」
「作ってくださるんですか?」
社長がぱあっと目を輝かせる。くっ……可愛い……。
社長と付き合う前はひたすらかっこいい王子様キャラだと思っていたが、付き合うようになってからはだんだん可愛い側面も見えるようになってきた。
「では、場所と日時はのちほどLIMEでお伝えします。当日お迎えに上がりますね」
ちょうど総務部の部屋に着いて、社長はそう言い残して去った。
お弁当かあ、何作ればいいんだろう。やっぱり唐揚げとか卵焼きとかが定番かな。
最近の私はわりと心身ともに調子が良くて、書類作成もスムーズに進む。
キーボードを叩きながら、お弁当の献立を考えるのはとても楽しい時間だった。
***
お花見デート当日。
LIMEで伝えられた時間きっかりに、社長は車で迎えに来た。
助手席に乗り込んで、連れてこられた場所は、都内の広い公園。土を盛って芝生を植えた丘や人工的なレンガの小道などがある。今日は天気もよく、日曜日なので家族連れやカップルが多い。
「行きましょうか」
車を駐車場に停めて、ふたりで車を降りる。社長――スバルさんは、私の手を取って、指を絡める。なるほど、これが恋人繋ぎってやつですね。わかります。
冷静なふりをしているが、内心、すでに脈拍がバクバク言っている。恋人繋ぎだけで私は瀕死である。心臓がもたない。
「こちらです」
スバルさんは私の手を引いて導いてくれる。
散歩、と言っていたが、まさしくそんな感じで、私の歩幅に合わせてゆっくり歩いてくれる。スバルさんは足が長いし普段は結構歩くスピードも速いんだけど、私と一緒のときはゆっくり歩いてくれて、それがとても嬉しい。
公園の小道を歩いていくと途中から花壇が小道の両脇にあって、色んな花が咲き乱れている。まさに春って感じだ。私は花に詳しくないからチューリップくらいしか分からないけど。
「きれいですね」
「そうですね。でもまだ主役が登場していませんよ」
スバルさんが私と繋いでいる手とは反対の手を口に当ててクスリと笑う。
「――着きました」
「……わぁ……!」
しばらく小道を歩いて公園の端っこまで来ただろうか。ちょうど丘の裏側だ。
桜がいくつも並んで咲き誇る光景はまさしく絶景というやつだろう。
「秘書の方に教えていただいたんですが、ここは穴場らしいですよ」
たしかに、こんなにきれいなのに人はいないようだ。公園の端っこまでかなり歩くのでここまで辿り着く人もいないのだろう。
ちょうど桜に囲まれた場所にぽつんとベンチが置いてあったので、ふたりで並んで座る。
「お口に合うといいのですが……」
私はショルダーバッグからお弁当の包みを取り出す。あまり激しく動いてないとはいえ、中身崩れてないといいんだけど。
弁当箱を開くと、中身は崩れてなくて安心した。とりあえず唐揚げとか、卵焼きとか、おにぎりとか、定番のものを入れておいた。
「美味しそうですね」
社長は心底嬉しそうに言う。美味しそうだなんて、シェフを雇って料理を食べているような人が、買いかぶり過ぎではないのか。
「食べてもいいですか?」
「どうぞ。そのために作ったので」
私はスバルさんに割り箸を渡す。
スバルさんは割り箸を割って、唐揚げを口に入れる。
「――美味しい。これ、手作りなんですか?」
「まあ、自分で作れる料理なので」
私はしれっとした顔をしたが、その実、スバルさんに喜んでほしくて全部頑張って手作りしたのは内緒の話である。
しかし、スバルさんの口にあったようで本当によかった、と密かに安堵する。
「……こずえさん、あーんしてください」
「え?」
スバルさんが唐揚げを箸で持って私の目の前に差し出す。
「わ、私が食べるんですか?」
「ふふ、一度こういうのやってみたかったんですよね」
……。
私は顔が熱くなるのを感じながら、おずおずと口を開ける。
唐揚げが口の中に入って、それを幸せごと噛みしめる。
なんだかすっごく恋人っぽいことをしている。いや、恋人だった。
「美味しいですか?」
「……美味しいです」
一応味見はしたんだけど、冷めても美味しいのが確認できた。
「でも、こういうのって普通逆っていうか……女性が男性に食べさせるものでは……」
「え? やってくださるんですか?」
しまった、罠だ!
スバルさんはその言葉を待っていたと言わんばかりに、目を細めて弧を描いた。
「是非お願いいたします」
そう言って、スバルさんは「あ」の形に口を開けて待っている。やるしかない雰囲気。
私は震える手で卵焼きを割り箸でつまみ、スバルさんの口に入れる。
スバルさんはゆっくり咀嚼し、飲み込んだ。喉仏が動くその様子さえ目をそらせないほど見入ってしまう。
「……やっぱり、こういうのはいいですね」
スバルさんは妖しげな笑みを浮かべる。
「……率直に言っていいですか」
「なんです?」
私の言葉に、スバルさんは首を傾ける。
「ひな鳥にご飯をあげる親鳥の気分でした」
「……ふっ、くくっ」
私の感想に、スバルさんは腹の底からおかしそうにふき出す。
「手厳しいですね、こずえさんは」
「もともとはこういう性格なんです」
「ふふ、隠さなくなったのは嬉しいですよ」
スバルさんのおかげだ、と私は思う。
スバルさんは自分を偽ったりしない。会社でも堂々とカードゲームをするし、オタク趣味を隠さない。それでも彼は社員たちから愛された。そんな彼がまぶしかった。
そう伝えると、「わたくしもこずえさんのおかげで救われましたよ」と言われて耳を疑った。
「こずえさんだけはわたくしに幻滅しないと信じていたから、わたくしの本当に好きな歌を歌うことが出来たんです」
それは、社員旅行での宴会の話か。
「わたくしがああいった歌を歌うと、女性はみんな離れていきました。みんな勝手に勘違いして集まってきたくせに、『イメージと違う』と去っていくのです」
スバルさんは悲しそうだった。
「スバルさん……」
「でも、こずえさんは『かっこいい』と言ってくれましたよね」
男性社員の大歓声で聞こえたはずがないのに、伝わっていた、のか。
「それに、結果的にはこれでよかったのかもしれません。こずえさんは、女性たちの攻撃を受けるのが怖かったんでしょう?」
スバルさんは、私の悩んでいた内容を知っていたのか。びっくりして、声が詰まった。
「わたくしは、他の女性に嫌われても、こずえさんさえいてくだされば、それでいいんです」
スバルさんは、はっきりそう言った。桜が舞い散る中で、スバルさんの清々しい笑顔が美しかった。
「――そろそろ帰りましょうか。お弁当、作ってくださってありがとうございます。ごちそうさまでした」
弁当をぺろりと平らげて、スバルさんはベンチから立ち上がる。
私も、弁当の包みをバッグにしまい、スバルさんに手を取られて立ち上がった。
私たちは、車の中で無言だった。
私の家に着いて、助手席から降りようとすると、スバルさんが手首を握った。
もう「なんですか」とは訊かない。あのときと同じ、また唇が重なった。
「――次の約束をしても、いいですか」
スバルさんは、真剣な表情で訊ねる。
「夏になったら、花火大会を見に行きませんか」
「随分先の約束をするんですね」
今はまだ桜が散り始めたくらいの季節だ。ギリギリ花見ができるくらいの。
「こずえさんとこうして未来の話をして、こずえさんが肯定してくださったら、わたくしはそれだけで満たされるんです」
「……はい。行きましょうね、花火」
私たちは、子供のように指切りをする。……もしスバルさんと小学生の時に一緒のクラスだったりしたら、他の男子が遊んでくれなくても、私の相手をしてくれただろうか。
私のほうこそ、スバルさんに救われている。子供の頃のひとりぼっちだった私の心の傷を、スバルさんが癒やしてくれているのだ。
スバルさんは名残惜しそうにそっと私の頬を撫でてから、車を走らせて去っていくのだった。
〈続く〉