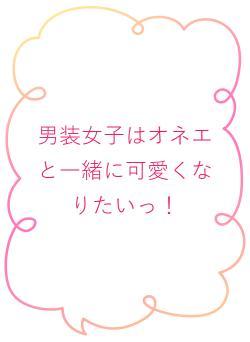忙しく日々を過ごして、気づけば春もとっくに終わり、いつの間にか約束の夏、花火大会の開催される八月になっていました。
こずえさんは「随分先の約束をするんですね」なんて笑っていらっしゃいましたが、社会人をなめてはいけません。本当に時間がいくらあっても足りませんね。
まあその間もこずえさんと会議室に行ってカードゲームをしたり、家に招待したりと趣味やプライベートも満喫していたのですが。
社会人たるもの、仕事と趣味、プライベートを両立してこそ充実した生活を送れるのです。
ところで、家の中でくつろいでいるとき、こずえさんに『そういうこと』をしないのか? と訊かれたことがありました。
「したいんですか?」
「いえ、別に」
「わたくしは婚前交渉はしない主義ですので、決してこずえさんに魅力がないわけではありません。誤解なきよう」
本当は今すぐにでもしたいですけどね、といたずらっぽく笑うと、こずえさんは顔を真赤にして「い、いえ! まだ早いと思います!」と慌てて言っていたのを思い出すと今でも笑みがこぼれてしまいます。わたくしの恋人、可愛い。可愛すぎる。
「わたくしは自分がこんなに独占欲が強いとは思っていませんでした。今もカードゲーム仲間と笑顔でお話しているこずえさんを見ると嫉妬心がわきます。きっと、こずえさんが初めて本当に好きになった方だから、でしょうね」
そう言うと、こずえさんはさらに顔を真赤にしてうつむくのでした。これ以上顔を赤くしたら熱が出てしまいそうです。
ああもう、こずえさんは本当にもう。
「まあそれはともかく。明日の約束、忘れておりませんよね?」
「もう明日ですか。あっという間ですね」
こずえさんは感慨深そうな声を出しました。
「また車でお迎えに上がりますね」
「でも花火大会はけっこう混み合いますし、車を停める場所もないのでは?」
「ご心配なく。運転手を用意しております」
父から運転手の影山を借りたいと申し出た時、
「そうか、スバルも好きな人ができたか。今度、紹介してくれ」
と朗らかに笑われました。家族に恋人を紹介するというのは、なんだか気恥ずかしいような、くすぐったいような気持ちでした。
「お抱えの運転手とかいるんですね……」
こずえさんが惚けたような声を出したのを覚えております。
花火大会当日、ちょうど会社は休みの日でした。
準備をしていると、こずえさんからLIMEで「今日は浴衣を着ていきますね」と連絡が来ました。
わたくしもせっかくなので浴衣を着ることにして、こずえさんに返信しました。
まだ時間はあったので急遽家にあった浴衣を用意し、着付けてから待たせていた影山に車を運転させて、こずえさんの住むアパートへ向かいました。
こずえさんはどんな浴衣を着るのか、想像しながら車に揺られる時間は有意義なものでした。
影山に運転させた車は、時間ぴったりにアパートに到着しました。影山は、昔から時間をきっちり守る男でした。わたくしの運転技術も、影山に影響されている部分は少なからずあったと思います。
「こずえさん、素敵な浴衣ですね」
こずえさんはすでに外で待っていました。車の後部座席から降りたわたくしは、まぶしいものを見る気分で目を細めました。
彼女の着ている浴衣は白地に青や紫の朝顔の花と緑の葉が染め抜かれた、彩りがありながらも落ち着きを感じさせる柄でした。わたくしは彼女らしいと思いました。
「スバルさんこそ……」
こずえさんは恥ずかしそうにうつむき、わたくしを直視できない様子でした。少し地味な浴衣を着てきてしまったかな、と思っていたので、彼女が喜んでくれたならそれはとても喜ばしいことです。
わたくしはこずえさんの手を取り、一緒に後部座席に乗り込みました。
「影山、出してください」
「はい」
影山は制帽をかぶり直し、車を出しました。わたくしよりもずっと年上でしたが、彼はとても忠実にわたくしの父に、そしてわたくしに仕えておりました。たしか物心がつく前からずっと傍にいたと思います。
わたくしが家を出るときには潤んだ目で見送ってくれたのを、今でも覚えています。
影山の運転はあの頃と変わらず丁寧で、こずえさんも不安を感じることはなかったと思います。とてもリラックスした様子でわたくしと話を弾ませていました。
「花火の前に、屋台でも回ってみますか?」
わたくしがそう提案し、こずえさんも同意して、わたくしたち二人は屋台の立ち並ぶエリアで降ろしてもらいました。
「わたくしたちは歩いていきますので、影山はわたくしの家に戻って待機していてください。迎えが必要になったら電話します」
「かしこまりました」
影山はそう言って、車で去っていきました。
「スバルさんって、こういうお祭りとか来たことあります?」
「いえ、アニメなどで知識はありますが、実際に来るのは初めてです。いろいろとご教授ください」
ちなみに、我が家ではアニメが禁止されるということもなく、わたくしは様々なアニメに慣れ親しんできました。なので小さい頃から『ダンガンロボッツ』などを見ることができたというわけです。
勉学やするべきことをきちんとしていれば、アニメでもゲームでも好きにやればいい、というのが我が家の家訓でした。
しかし、お祭りについては、恥ずかしながら前述したとおり、わたくしは人と接するのが苦手で、人混みに入りたがりませんでした。
何度か女性に誘われたこともありましたが、何故わざわざ人混みに紛れて割高な食事や娯楽をしなければいけないのか、などと侮っておりました。
今回はこずえさんのためなら! と一念発起しましたが、やはり花火はひとけのないところで見るべきでしょう。すでに準備は整えてありました。
「あれがわたあめですか、実際に作っているところが見られるのですね」とか、「金魚すくいに興味があるのですが、水槽を用意しないといけませんね……」とか、こずえさんとそんな話をしながら屋台を覗いて歩きました。見るもの全てがアニメのとおりで、とても面白く感じられました。まるでアニメの世界に飛び込んだような、夢でも見ているような気持ちです。しかも隣には浴衣を着た可愛らしいこずえさん。はあ……好き……。
冷静な顔をしていましたが、内心語彙力が溶けていくようでした。
「あ、あれやってみたいです」
わたくしはごまかすようにある店に指をさしました。射的屋、というやつです。
「こずえさんは、何か欲しい商品ありますか?」
「じゃあ、あのぬいぐるみを」
「わかりました」
BB弾を撃ち出すタイプの拳銃を構えて、こずえさんの欲しがっているぬいぐるみに狙いを定め、撃ちました。
弾はぬいぐるみの頭に命中し、バランスを崩して棚から落ちました。一発で決まって気持ちがよく、わたくしは心のなかでガッツポーズをしました。
「えっ」
こずえさんは驚いているようでした。わたくしも、こずえさんにかっこいいところを見せたかったので、その顔を見て満足しました。
「ふふっ、ハワイで射撃訓練を受けたことがあるのですよ」
しかし、BB弾を使って一撃でかっこよく落とせるか不安要素もあったので、内心わたくしはホッとしていました。
「こずえさんもやってみたらいかがですか? 撃ち方お教えしますよ」
と提案し、こずえさんに拳銃の撃ち方を教えることになりました。
「身体を軽く前に傾けて……肘と膝は軽く曲げて……利き手のほうの足を少し下げて外側に向けて……」
文字通り、手取り足取り。合法的にこずえさんと密着しておりました。
……いやまあ、恋人同士なので合法もなにもないんですが。
「銃の前と後ろの出っ張りを合わせるようにして……そう。それで撃ってみてください」
パァン。
拳銃の反動のせいか、弾は狙いをそれてしまいましたが、こずえさんはなかなか覚えが早そうな気がしました。
新婚旅行でハワイに行くとしたら、こうやって二人で射撃訓練を受けるのも楽しいかもなあ、なんて思ってしまいました。
「惜しいですね」
とわたくしが笑いかけますが、こずえさんはどこか落ち着かない様子でした。
周りを見ると、どうやらわたくしたちは目立ってしまっているようで、いつの間にか人だかりができていました。
「す、スバルさん、そろそろ行きましょうか」
「まだ回数残ってますよ?」
「もうぬいぐるみはいただいたからいいんです」
こずえさんはここから逃げ出したいのでしょう、わたくしの手を引いて、人混みを抜けました。
そういえば。
「――そういえば、こずえさんから手を握ってくださったのは初めてですね」
わたくしは振り向いたこずえさんに幸せな笑顔を浮かべました。
***
屋台の立ち並ぶ通りを抜けると、そこは港でした。
夜の黒い海が月明かりを反射して、キラキラと光っています。
「ここらへんで花火を見るんですか?」
「もっといいものを用意しております」
今度はわたくしがこずえさんの手を引く番でした。
わたくしが指定した場所に、ちゃんとそのクルーザーはありました。
こずえさんはそれを見て驚きのあまり呆然としておりました。
「クルーザーに乗って花火を見れば人混みを回避できるでしょう?」
このために準備してきたものです。このクルーザーも操縦士も、父に頼んで借りてきたものでした。
「花火が始まる前に船を出してしまいましょう。乗って」
こずえさんが海に落ちないよう、慎重にクルーザーに乗せました。
クルーザーの中のソファに二人で座ると、見計らったように船が出港しました。クルーザーは沖を目指して、速度を上げました。
花火がよく見えるポイントにたどり着き、船は少し揺れて、止まりました。
「そろそろ時間ですね」
腕時計を見て時間を確認していると、ちょうど花火大会が始まったようでした。
ヒュー……ドーン。パラパラパラ。
その音を繰り返し、花火が夜空に咲いては散ってゆきます。
「きれい……」
独り言のようにそうつぶやくこずえさんの横顔を、わたくしはじっと眺めておりました。
花火の色とりどりの光ですらも、こずえさんの前ではわたくしにとってはこずえさんを彩るための添え物にしか過ぎませんでした。
ふと、こずえさんがわたくしのほうを見ました。
「あ、あの、花火始まってますよ……」
こずえさんはわたくしがじっと見つめていることに少し戸惑っているようでした。
「花火なんかより、こずえさんを見ているほうがずっといいです」
こずえさんのほうが、花火なんかよりもずっときれいで。
「何のために花火大会誘ったんです……?」
こずえさんの疑問はもっともです。
わたくしは浴衣の袖に隠し持っていた小さな箱を取り出しました。
こずえさんに向けてそっと開くと、銀色に光る指輪は、ちゃんとそこにありました。
「こずえさん。わたくしと、婚約していただけませんか?」
とうとうわたくしはプロポーズしました。
こずえさんは額に手の甲を当てて、今にも気絶しそうでした。
「え、と、あの、……ふつつかものですが、よろしくおねがいします……」
彼女は顔を真っ赤に染めていました。
わたくしはプロポーズが成功したことに、ほぅと息をつきました。
こずえさんの左手をそっと持ち上げて、薬指に指輪を通して。
「絶対、ずっと、幸せにしますから……どうか、わたくしのそばを離れないでください」
わたくしは祈りを込めて、指輪にそっと口づけました。
こずえさんの顔を見上げると、じわりと涙がにじんでいました。
それを舌で舐め取って、そのまま、まぶたに、額に、頬に、唇に、自らの唇を寄せました。
気づけば、わたくしはこずえさんをソファに横たえて、その上に覆いかぶさっていました。
「は……っ、こずえさん、こずえさん……」
口づけをしながら、何度もこずえさんの名前を呼ぶわたくしは、まるで助けを求める子供のようでした。
「スバルさん、私はちゃんと、ここにいますよ」
目を細めるこずえさんは、わたくしの頬を撫でました。わたくしは泣くのをこらえて顔を歪ませました。
こずえさんの顔に、窓から入る花火の光が色を付けました。花火を見るために照明を消した部屋の中に、花火の鮮やかな光がわたくしたちを照らすように差し込んでは消えて。
――その夜のことは、今も忘れられません。
〈続く〉
こずえさんは「随分先の約束をするんですね」なんて笑っていらっしゃいましたが、社会人をなめてはいけません。本当に時間がいくらあっても足りませんね。
まあその間もこずえさんと会議室に行ってカードゲームをしたり、家に招待したりと趣味やプライベートも満喫していたのですが。
社会人たるもの、仕事と趣味、プライベートを両立してこそ充実した生活を送れるのです。
ところで、家の中でくつろいでいるとき、こずえさんに『そういうこと』をしないのか? と訊かれたことがありました。
「したいんですか?」
「いえ、別に」
「わたくしは婚前交渉はしない主義ですので、決してこずえさんに魅力がないわけではありません。誤解なきよう」
本当は今すぐにでもしたいですけどね、といたずらっぽく笑うと、こずえさんは顔を真赤にして「い、いえ! まだ早いと思います!」と慌てて言っていたのを思い出すと今でも笑みがこぼれてしまいます。わたくしの恋人、可愛い。可愛すぎる。
「わたくしは自分がこんなに独占欲が強いとは思っていませんでした。今もカードゲーム仲間と笑顔でお話しているこずえさんを見ると嫉妬心がわきます。きっと、こずえさんが初めて本当に好きになった方だから、でしょうね」
そう言うと、こずえさんはさらに顔を真赤にしてうつむくのでした。これ以上顔を赤くしたら熱が出てしまいそうです。
ああもう、こずえさんは本当にもう。
「まあそれはともかく。明日の約束、忘れておりませんよね?」
「もう明日ですか。あっという間ですね」
こずえさんは感慨深そうな声を出しました。
「また車でお迎えに上がりますね」
「でも花火大会はけっこう混み合いますし、車を停める場所もないのでは?」
「ご心配なく。運転手を用意しております」
父から運転手の影山を借りたいと申し出た時、
「そうか、スバルも好きな人ができたか。今度、紹介してくれ」
と朗らかに笑われました。家族に恋人を紹介するというのは、なんだか気恥ずかしいような、くすぐったいような気持ちでした。
「お抱えの運転手とかいるんですね……」
こずえさんが惚けたような声を出したのを覚えております。
花火大会当日、ちょうど会社は休みの日でした。
準備をしていると、こずえさんからLIMEで「今日は浴衣を着ていきますね」と連絡が来ました。
わたくしもせっかくなので浴衣を着ることにして、こずえさんに返信しました。
まだ時間はあったので急遽家にあった浴衣を用意し、着付けてから待たせていた影山に車を運転させて、こずえさんの住むアパートへ向かいました。
こずえさんはどんな浴衣を着るのか、想像しながら車に揺られる時間は有意義なものでした。
影山に運転させた車は、時間ぴったりにアパートに到着しました。影山は、昔から時間をきっちり守る男でした。わたくしの運転技術も、影山に影響されている部分は少なからずあったと思います。
「こずえさん、素敵な浴衣ですね」
こずえさんはすでに外で待っていました。車の後部座席から降りたわたくしは、まぶしいものを見る気分で目を細めました。
彼女の着ている浴衣は白地に青や紫の朝顔の花と緑の葉が染め抜かれた、彩りがありながらも落ち着きを感じさせる柄でした。わたくしは彼女らしいと思いました。
「スバルさんこそ……」
こずえさんは恥ずかしそうにうつむき、わたくしを直視できない様子でした。少し地味な浴衣を着てきてしまったかな、と思っていたので、彼女が喜んでくれたならそれはとても喜ばしいことです。
わたくしはこずえさんの手を取り、一緒に後部座席に乗り込みました。
「影山、出してください」
「はい」
影山は制帽をかぶり直し、車を出しました。わたくしよりもずっと年上でしたが、彼はとても忠実にわたくしの父に、そしてわたくしに仕えておりました。たしか物心がつく前からずっと傍にいたと思います。
わたくしが家を出るときには潤んだ目で見送ってくれたのを、今でも覚えています。
影山の運転はあの頃と変わらず丁寧で、こずえさんも不安を感じることはなかったと思います。とてもリラックスした様子でわたくしと話を弾ませていました。
「花火の前に、屋台でも回ってみますか?」
わたくしがそう提案し、こずえさんも同意して、わたくしたち二人は屋台の立ち並ぶエリアで降ろしてもらいました。
「わたくしたちは歩いていきますので、影山はわたくしの家に戻って待機していてください。迎えが必要になったら電話します」
「かしこまりました」
影山はそう言って、車で去っていきました。
「スバルさんって、こういうお祭りとか来たことあります?」
「いえ、アニメなどで知識はありますが、実際に来るのは初めてです。いろいろとご教授ください」
ちなみに、我が家ではアニメが禁止されるということもなく、わたくしは様々なアニメに慣れ親しんできました。なので小さい頃から『ダンガンロボッツ』などを見ることができたというわけです。
勉学やするべきことをきちんとしていれば、アニメでもゲームでも好きにやればいい、というのが我が家の家訓でした。
しかし、お祭りについては、恥ずかしながら前述したとおり、わたくしは人と接するのが苦手で、人混みに入りたがりませんでした。
何度か女性に誘われたこともありましたが、何故わざわざ人混みに紛れて割高な食事や娯楽をしなければいけないのか、などと侮っておりました。
今回はこずえさんのためなら! と一念発起しましたが、やはり花火はひとけのないところで見るべきでしょう。すでに準備は整えてありました。
「あれがわたあめですか、実際に作っているところが見られるのですね」とか、「金魚すくいに興味があるのですが、水槽を用意しないといけませんね……」とか、こずえさんとそんな話をしながら屋台を覗いて歩きました。見るもの全てがアニメのとおりで、とても面白く感じられました。まるでアニメの世界に飛び込んだような、夢でも見ているような気持ちです。しかも隣には浴衣を着た可愛らしいこずえさん。はあ……好き……。
冷静な顔をしていましたが、内心語彙力が溶けていくようでした。
「あ、あれやってみたいです」
わたくしはごまかすようにある店に指をさしました。射的屋、というやつです。
「こずえさんは、何か欲しい商品ありますか?」
「じゃあ、あのぬいぐるみを」
「わかりました」
BB弾を撃ち出すタイプの拳銃を構えて、こずえさんの欲しがっているぬいぐるみに狙いを定め、撃ちました。
弾はぬいぐるみの頭に命中し、バランスを崩して棚から落ちました。一発で決まって気持ちがよく、わたくしは心のなかでガッツポーズをしました。
「えっ」
こずえさんは驚いているようでした。わたくしも、こずえさんにかっこいいところを見せたかったので、その顔を見て満足しました。
「ふふっ、ハワイで射撃訓練を受けたことがあるのですよ」
しかし、BB弾を使って一撃でかっこよく落とせるか不安要素もあったので、内心わたくしはホッとしていました。
「こずえさんもやってみたらいかがですか? 撃ち方お教えしますよ」
と提案し、こずえさんに拳銃の撃ち方を教えることになりました。
「身体を軽く前に傾けて……肘と膝は軽く曲げて……利き手のほうの足を少し下げて外側に向けて……」
文字通り、手取り足取り。合法的にこずえさんと密着しておりました。
……いやまあ、恋人同士なので合法もなにもないんですが。
「銃の前と後ろの出っ張りを合わせるようにして……そう。それで撃ってみてください」
パァン。
拳銃の反動のせいか、弾は狙いをそれてしまいましたが、こずえさんはなかなか覚えが早そうな気がしました。
新婚旅行でハワイに行くとしたら、こうやって二人で射撃訓練を受けるのも楽しいかもなあ、なんて思ってしまいました。
「惜しいですね」
とわたくしが笑いかけますが、こずえさんはどこか落ち着かない様子でした。
周りを見ると、どうやらわたくしたちは目立ってしまっているようで、いつの間にか人だかりができていました。
「す、スバルさん、そろそろ行きましょうか」
「まだ回数残ってますよ?」
「もうぬいぐるみはいただいたからいいんです」
こずえさんはここから逃げ出したいのでしょう、わたくしの手を引いて、人混みを抜けました。
そういえば。
「――そういえば、こずえさんから手を握ってくださったのは初めてですね」
わたくしは振り向いたこずえさんに幸せな笑顔を浮かべました。
***
屋台の立ち並ぶ通りを抜けると、そこは港でした。
夜の黒い海が月明かりを反射して、キラキラと光っています。
「ここらへんで花火を見るんですか?」
「もっといいものを用意しております」
今度はわたくしがこずえさんの手を引く番でした。
わたくしが指定した場所に、ちゃんとそのクルーザーはありました。
こずえさんはそれを見て驚きのあまり呆然としておりました。
「クルーザーに乗って花火を見れば人混みを回避できるでしょう?」
このために準備してきたものです。このクルーザーも操縦士も、父に頼んで借りてきたものでした。
「花火が始まる前に船を出してしまいましょう。乗って」
こずえさんが海に落ちないよう、慎重にクルーザーに乗せました。
クルーザーの中のソファに二人で座ると、見計らったように船が出港しました。クルーザーは沖を目指して、速度を上げました。
花火がよく見えるポイントにたどり着き、船は少し揺れて、止まりました。
「そろそろ時間ですね」
腕時計を見て時間を確認していると、ちょうど花火大会が始まったようでした。
ヒュー……ドーン。パラパラパラ。
その音を繰り返し、花火が夜空に咲いては散ってゆきます。
「きれい……」
独り言のようにそうつぶやくこずえさんの横顔を、わたくしはじっと眺めておりました。
花火の色とりどりの光ですらも、こずえさんの前ではわたくしにとってはこずえさんを彩るための添え物にしか過ぎませんでした。
ふと、こずえさんがわたくしのほうを見ました。
「あ、あの、花火始まってますよ……」
こずえさんはわたくしがじっと見つめていることに少し戸惑っているようでした。
「花火なんかより、こずえさんを見ているほうがずっといいです」
こずえさんのほうが、花火なんかよりもずっときれいで。
「何のために花火大会誘ったんです……?」
こずえさんの疑問はもっともです。
わたくしは浴衣の袖に隠し持っていた小さな箱を取り出しました。
こずえさんに向けてそっと開くと、銀色に光る指輪は、ちゃんとそこにありました。
「こずえさん。わたくしと、婚約していただけませんか?」
とうとうわたくしはプロポーズしました。
こずえさんは額に手の甲を当てて、今にも気絶しそうでした。
「え、と、あの、……ふつつかものですが、よろしくおねがいします……」
彼女は顔を真っ赤に染めていました。
わたくしはプロポーズが成功したことに、ほぅと息をつきました。
こずえさんの左手をそっと持ち上げて、薬指に指輪を通して。
「絶対、ずっと、幸せにしますから……どうか、わたくしのそばを離れないでください」
わたくしは祈りを込めて、指輪にそっと口づけました。
こずえさんの顔を見上げると、じわりと涙がにじんでいました。
それを舌で舐め取って、そのまま、まぶたに、額に、頬に、唇に、自らの唇を寄せました。
気づけば、わたくしはこずえさんをソファに横たえて、その上に覆いかぶさっていました。
「は……っ、こずえさん、こずえさん……」
口づけをしながら、何度もこずえさんの名前を呼ぶわたくしは、まるで助けを求める子供のようでした。
「スバルさん、私はちゃんと、ここにいますよ」
目を細めるこずえさんは、わたくしの頬を撫でました。わたくしは泣くのをこらえて顔を歪ませました。
こずえさんの顔に、窓から入る花火の光が色を付けました。花火を見るために照明を消した部屋の中に、花火の鮮やかな光がわたくしたちを照らすように差し込んでは消えて。
――その夜のことは、今も忘れられません。
〈続く〉