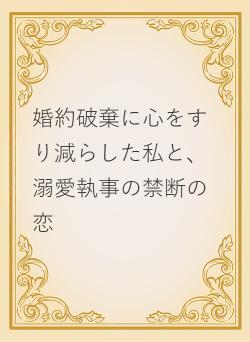あの厳しくて冷たい声を放つ零様にも、綾芽様にしか見せない顔がある。
当たり前だが、そのことに気づき、綾芽様が羨ましくて憎くくさえ思ってしまう自分が嫌になった。
「凛……?」
「い、いえ! なんでもございません! 美味しかったです。私がいただいてしまって、よかったのでしょうか」
その言葉を聞いて綾芽様が少し俯く。
そうして、金平糖の入った小物入れを私に握らせてくださった。
「それはきっと本当はあなたのもの」
「……え?」
綾芽様はじっと私を見つめる。
優しくて温かいその手に、私の両手は包まれた。
「零様はあなたを見てる。誰よりもあなたを信頼して、あなたを……いえ、なんでもないわ」
「綾芽様……──っ!!」
その時、突然背中がぞくりとして、とても嫌な気配がした。
綾芽様もそれに気づいたようで、二人で目を合わせる。
それは間違いなく、妖魔の気配だった──
当たり前だが、そのことに気づき、綾芽様が羨ましくて憎くくさえ思ってしまう自分が嫌になった。
「凛……?」
「い、いえ! なんでもございません! 美味しかったです。私がいただいてしまって、よかったのでしょうか」
その言葉を聞いて綾芽様が少し俯く。
そうして、金平糖の入った小物入れを私に握らせてくださった。
「それはきっと本当はあなたのもの」
「……え?」
綾芽様はじっと私を見つめる。
優しくて温かいその手に、私の両手は包まれた。
「零様はあなたを見てる。誰よりもあなたを信頼して、あなたを……いえ、なんでもないわ」
「綾芽様……──っ!!」
その時、突然背中がぞくりとして、とても嫌な気配がした。
綾芽様もそれに気づいたようで、二人で目を合わせる。
それは間違いなく、妖魔の気配だった──