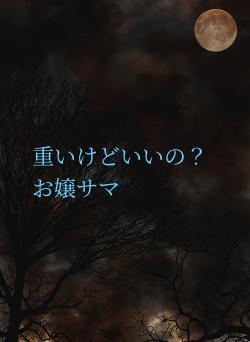たい焼きを食べながら、おいかけっこするように私たちは寮へ戻った──
「んで、依頼主から仮でも彼氏にぐんと昇格した。なのに……これ、このままなの?」
部屋に着くなり、これ、と部屋を仕切る線をさす比江島くんに私は迷いなく頷く。
「当然」
「ちぇ、残念。でもま、これからは俺らしく凛といるから、よろしく」
「わ、私も多少は素直になる努力をしようと思う……」
「俺としてはそのままでもいんだけどね。ツンツンが凛って感じだし。デレは俺が引き出すから」
「引き出すってどうやって?」
尋ねれば、比江島くんは目を丸くした。
だけどすぐ、私の手を取り薄く笑みを浮かべる。
「こうやって……」
そのまま引き寄せられ、頬に当たった感触に思いきり肩が跳ねた。
「い、いい今っ……!?」
頬に……き──キス……!?
「はははっ、動揺すごいな。わりと照れ屋なの自分で気づいてないでしょ?赤いよ?」
「うるさ……ちょっと、びっくりしただけだもん」
「ははっ可愛い」
「可愛くないし」
ふいっと顔をそむければ、比江島くんが顔を寄せてきた。
「──もっかいする?」
「なっ……!」
なんか、この比江島くんに振り回され過ぎ。鵜呑みにしちゃだめよ、凛。
あぁ、もう顔あっついし。
「い、いらない」
「いらないって……ははっ本当ツンデレ」
楽しそうに笑う比江島くん。
本当勝てる気しないんだけど。
「でもそんな余裕も今のうち。明日は覚悟しといた方がいいよ」
「明日?なんかあったっけ?」
「お疲れパーティー。お重3個になってるかも」
「あ……」
ほらねやっぱり、忘れてたでしょ?
「ま……まあ、お重もだけど、仮をとれるよう、強瀾のたて直しと一緒に頑張りますかね。俺の彼女さん?」
「うん……だからこれからも」
どうぞよろしく──
私たちはそっと額を合わせ、笑いあった──