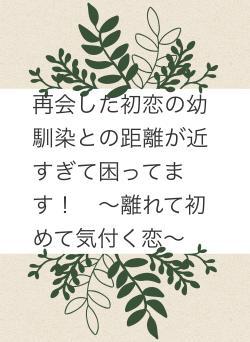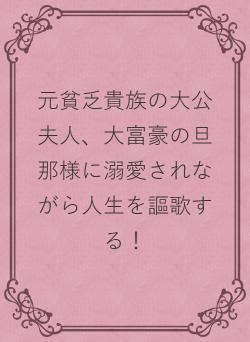火照って熱を帯びてしまった顔に手をパタパタと仰ぎ冷ましながら、二階にある私の部屋に足を進めた。
どうしたらいいかな。と、悩みつつも階段を一段一段上がっていたけれど、結局私に勇気がないだけだという答えに辿り着きため息を吐いてしまった。
まずは、帰ってお風呂に入って一旦頭をリセットしないと。そう思い、玄関前で鍵を開け、入った。
そして、気が付いた。
「……あっ」
目の前には、部屋に続くキッチンを兼ねた廊下。その先にある、奥の部屋の電気がついている。
消し忘れたのだろうか。消したつもりだったんだけどな。
けれど、おかしい。どうして、匂いが違うんだろう。家の匂いって、そんなに変わるものなのだろうか。だって、誰もこの部屋の鍵を持っていない。蒸発した母だって、ここの鍵は置いていった。今は部屋の引き出しに仕舞ってあるはずだ。
母がいた頃は、こんな匂いはしなかった。
いや、まさか。
少しだけ、怖くなった。部屋に続く扉を、開けるのが怖かった。
先ほどまで熱かった顔が、今はすでに冷めてしまっていた。
けれど、さっき私は鍵を開けて部屋に入った。ちゃんと鍵はかかっていた。ゴミとか、そういうものから出た匂いなんじゃないだろうか。そう自分に言い聞かせてから靴を脱ぎ、ゆっくりとした足取りで進み、ドアに手をかけた。
そして、ゆっくりとドアを開いた。
「おかえりなさい、瑠奈ちゃん」