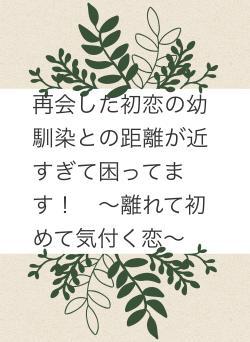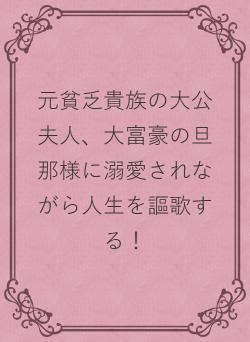聞こえてくるパトカーのサイレンの音。そして、トレンチコートの男は駆け付けた警察官達に引き渡されたのだった。
一瞬見えた、マスクの下の顔。
「……えっ」
「チッ」
この人、私が今働いているカフェの、常連さんだ。いつも、テーブル席に座ってはコーヒー一杯を頼んで何時間も滞在している方。
知ってるやつかと湊さんに聞かれ、頷いた。でも、この人はそんなに親しい人ではない。そもそも、私はあのカフェで働き始めて1週間経ったくらいだ。
「アンタがいつもあの客の男と楽しく話してたからだろっ!! それにこの男誰だよっ!! 俺というものがいながらっ!!」
「えっ……」
「あんなに笑顔を見せてくれてたんだ、俺の事が好きなんだろっ!! だったらもっと俺に尽くすべきだろっ!!」
この人のでたらめな発言に、私は寒気を覚えた。私は、そんな事をしただろうか。ただ、店員として客に接してきたはずだ。もちろん、この人に対する好意は一切ない。
あの客の男、というのは……いつもカウンターに座るあのお客様の事だろうか。これはとんだ誤解だ。
すると、腕を引っ張られて一歩下げられ、代わりに湊さんが前に出る。
「それ、瑠奈にはっきり言われたのか? それとも自分の妄想か?」
いきなり口に出したその声に、また、寒気を覚えた。そして、湊さんは男の胸ぐらを掴んだ。いつもよりも低い声で、男にこう言った。
「お前の勝手な妄想を、瑠奈に押し付けるな」
「っ……てめぇ!!」
「さっさと連れていけ」
「はいっ!」
湊さんはくるっと私の方に向き、抱きしめてきたのだ。どうしてこんな事になっているのだろうと混乱してしまう。
「震えてるぞ」
「……」
「ナイフが出てきたんだ。普通そうなる」
湊さんがさっき冷ややかだったのもある……わけではないか。確かに、あれは生きた心地がしなかった。けれど、刺されそうになっていたのは私ではなく湊さんだ。それなのに、こうも平然として私を気にかけてくれている。
警察官というのは危険がつきものだと何となく理解しているけれど……やっぱり強いな、と思った。
そんな強い彼に抱きしめられているからか、さっきまで寒さを感じていた身体が温まっていくのを感じる。すぐそこで警察の方達がいるのに、離してくださいと声をかけたくないと思ってしまう。
……けど。
「あの、湊さん、恥ずかしいのですが」
「離してほしい?」
「はい」
あっさりと、解いてくれた。向こうにいらっしゃる警察官さん達の方へ視線は向けられないけれど、これ以上恥ずかしい思いはしたくない。