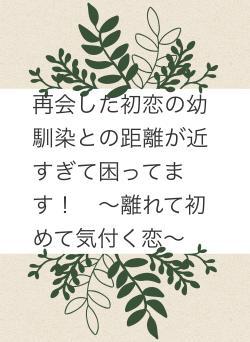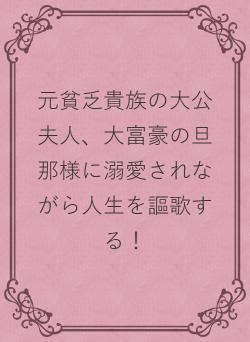気が抜けたのか、トイレの座面に座り込んでしまった。手の力が抜け、スマホを落としかけてしまった。
後悔した。
忙しい人なのに、どうして彼に電話をかけてしまったのだろうか。
彼は、エリートの警察官だ。あの上司が言っていた通り、私のような一般人が関わっちゃいけない人だ。私はただの元アルバイト。だから、もう関係ないはずだったのに。
けれど、思った。なかなか話さない私に、すぐに理解してくれた。待ってろ、と言ってくれた。もしこれが110番だったら、どうしましたかと聞かれたはずだ。その時、私はちゃんと伝えられただろうか。
そんな疑問の中、また電話がかかってきた。相手は、先ほど電話した相手だ。
『駐車場まで来た』
「あ……あの、今、トイレに、いて……」
『ストーカーか?』
「……はい」
何故、分かったのだろうか。私は居場所しか言ってないのに。流石エリート警視だ。まぁ、電話での私の態度もヒントになったのだろうな。
『トレンチコートとマスクのやつか』
「た、たぶん……」
駐車場にいる湊さんが見ているということは、トイレの前にはいないということだ。その事実に少しだけホッとした。
トイレの水を流してから出てこいと指示され、電話をかけたまま従いトイレから出た。店内に続くドアを開けるのをためらったけれど、窓からコンビニエンスストアの出入り口が見えて、電話の相手を見つけることが出来た。
そして、雑誌コーナーに立つあの男の姿も。
ドアを開けていいのかためらったけれど、湊さんは私に気が付き通話を切りつつも自然な動きでこちらに向かってきた。出てこい、という視線を向けられたような気がして、静かにドアを開ける。
「いたいた、悪いな遅くなって」
「あ、の……」
「何だよ、怒ってるのか? 悪かったって。コンビニスイーツ奢るから、それでいいか?」
私の手を握り、飲み物コーナーへ曲がる。湊さんと他愛のない話をしていると、彼が私達の後ろに視線を一瞬向けて私に直した。
「みたらし団子食いたいな。そっちはどうする?」
「えぇと……プリン?」
「一つでいいのか? ミルクレープ、二つ入ってたやつあったよな。好きだろ? 半分こしないか?」
「……」
「何、今食べたら太るって? 今日ぐらいいだろ。俺は見てないふりするからさ」
そう笑顔を見せてくれる湊さんに、何となく安心感を覚えた。
スイーツコーナーに辿り着き、会話に出てきたものを手にして会計へ。そして、何事もなく二人で店を出た。