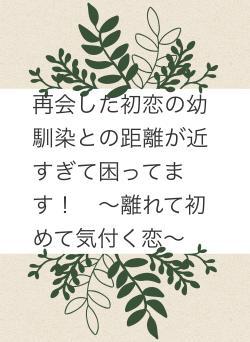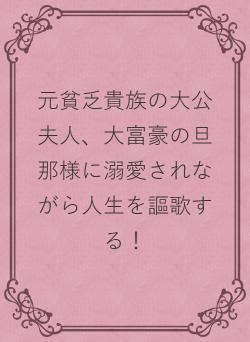ようやく、コンビニエンスストアの自動ドアをくぐることが出来た。中にはお客さんが何人かいるようで、店員も二人見える。人の目があるのだから流石についてこないだろう、と思いつつも外を確認するために雑誌コーナーに向かった。
雑誌を一つ手に取り開き、視線をそっと外に向けると……誰かが来店してくる音が鳴る。
心臓の音が、一気に大きくなってくる。脈が速くなってきて、早く逃げろと言われているような警告音が鳴り響く。けれど、ここから逃げろと言ってもどこに逃げていいのか分からない。自宅に逃げたら特定されてしまうし、他に思いつくところもない。
入ってきたのはトレンチコートを着たマスクをしている男性。その男は私から二人分くらい開けたところに立ち雑誌を手に取った。そして……こちらを、見た。
私は、すぐに視線を雑誌に戻した。何となく、誰かに似ているような気もするけれど……それどころじゃない。すぐに雑誌を元あった場所に戻し、トイレに逃げ込んだ。
「っ……はぁ……はぁ……」
早く家に帰りたい。でも家に帰ったら自宅を知られてしまう。このままじゃ帰れない。じゃあ、どうする? ここには近くに交番はない。じゃあ、110番?
すぐにスマホを取り出し、警察に電話をかけようとした。けれど、一番最初に目に入ったのは……履歴にいくつも並んでいる、彼の名前。
……いや、でも、もうアルバイト期間は終わった。私はもう被雇用者ではない。それに、彼はエリートの警視だ。そんな人に助けを求める事なんて間違ってる。忙しい人なんだから、迷惑だってかけられない。
そう、思っていたけれど……トイレの前まであの男が来てしまったらと思うと、トイレに長時間引きこもり店員が声をかけてきて出ないといけなくなってしまったらと思うと、何とかしないと、という焦りを感じる。
私は、一番上の名前に視線を向け、震える指で、その名前に触れてしまった。
ワンコールで、呼び出し音が止まる。
『もしもし、瑠奈』
懐かしい声が、私の名を呼んだ。けれど、声が出ない。
もしかしたらトイレ前まで来てしまっているかもしれない。この扉を開けたら目の前に立っているかもしれないと思うと、怖かった。
じゃあ、これをどう説明した方がいいだろうか。何と言えば、いいのだろうか。混乱する頭では、全く整理がつかなかった。
『ようやく電話に出たな。そんなに出たくなかったか』
「……」
『俺の事、そんなに嫌いか?』
「……」
『……何かあったのか』
いつもの私だったら、そんな事ありませんとすぐに否定する。それを分かっていたのか、黙ったままの私をおかしく思いそう言ってくる。私は、どう言ったらいいのか言葉を探してはいるものの、ちょうどいい言葉が見つからない。
『今、どこだ』
「いつも行く、スーパーの、近くの、コンビニ、です」
小さな声で、そう伝えた。少し、声が震えてしまったけれど、彼には十分聞こえていたようだ。
『分かった。待ってろ』
その言葉を残して、電話は切れてしまった。