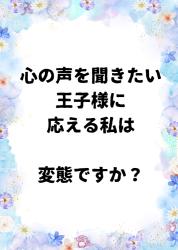――やっと見つけた。
彼に気づかれないよう、すぐに姿隠しの魔法を使う。
人間には使えない魔法だ。
当然だろう。使える者が多ければ、盗みや強姦といった類の犯罪が数十倍に増えるはずだ。
私のような魔女という種族……バグのような存在にしか使えない。寿命が長く種族維持にも興味が湧かない。人間の男性と生殖行為を行い子が産まれれば、魔女の素質は受け継がれずただの人間にしかならない。
『私たちはきっと神か妖のようなものね。増えすぎたら困るバグ』
母がそう言っていた。
『……神と妖、違いすぎない?』
『たぶん神ね。人間とまぐわえば人間が産み落とされるのに、自分は神のまま。最初はきっとヒトをそうやって増やしたのよ』
けらけら笑っていたから、冗談だったのか本気だったのかは分からないけど……私はバグの中でもバグなのだろう。
だって――あの人を愛したから。あの人との子供が欲しいと望み、孫もいる。
『私はもうすぐ死ぬだろうから忠告しておくわね。ヒトと必要以上に関わるのはやめなさい。老いないからと面倒事を全部押し付けられるわよ。人間って自分勝手な生き物だもの』
魔女は滅ぶだけ。
終わりを待つだけの種族だ。
母親以外の他の魔女に会ったこともない。魔女が魔女を産む条件はシンプルだ。「継ぐ者が欲しい」と強く望み自らの魔力を腹に注ぐ。胎芽が現れると魔女の力はなくなり、子が成人の姿になった頃に死ぬ。
長く生きて寿命が尽きるのを待つか、子をたった一人でなして死ぬか。自死を選ばないなら、どちらかしかない。
彼は害獣退治ギルドの前で、木の葉を集めている。箒で一つにまとめると空中でジリジリと燃やし、周辺を浄化魔法で清めている。害獣の血をしたたらせながら運んできた輩がいたのかもしれない。道の先の方まで既に浄化は終わっているようだ。
彼が汗をタオルで吹いてベンチの前に座った。普通の……白髪混じりのおじさんだ。ブラウンの優しそうな瞳はずっと変わらない。あの頃のまま。
『どの魔道具も面白いですね!』
キラキラした瞳で私の売るガラクタを見るのが印象的だった。大体の人は説明を聞くとため息をついて私を一瞥して出て行くのに。優しい男の子だなと思った。何もかもを楽しめる子なのかなとも。
魔道具屋と適当にペンキで書いて、道楽で開いていた店。
王家との秘密の取引が収入源で、店はただの暇つぶし。いつもなら一度来た人間は店を認識できないようにするのに、私はそのままにした。王家にもしばらくこの街に留まると伝えた。
彼に気づかれないよう、すぐに姿隠しの魔法を使う。
人間には使えない魔法だ。
当然だろう。使える者が多ければ、盗みや強姦といった類の犯罪が数十倍に増えるはずだ。
私のような魔女という種族……バグのような存在にしか使えない。寿命が長く種族維持にも興味が湧かない。人間の男性と生殖行為を行い子が産まれれば、魔女の素質は受け継がれずただの人間にしかならない。
『私たちはきっと神か妖のようなものね。増えすぎたら困るバグ』
母がそう言っていた。
『……神と妖、違いすぎない?』
『たぶん神ね。人間とまぐわえば人間が産み落とされるのに、自分は神のまま。最初はきっとヒトをそうやって増やしたのよ』
けらけら笑っていたから、冗談だったのか本気だったのかは分からないけど……私はバグの中でもバグなのだろう。
だって――あの人を愛したから。あの人との子供が欲しいと望み、孫もいる。
『私はもうすぐ死ぬだろうから忠告しておくわね。ヒトと必要以上に関わるのはやめなさい。老いないからと面倒事を全部押し付けられるわよ。人間って自分勝手な生き物だもの』
魔女は滅ぶだけ。
終わりを待つだけの種族だ。
母親以外の他の魔女に会ったこともない。魔女が魔女を産む条件はシンプルだ。「継ぐ者が欲しい」と強く望み自らの魔力を腹に注ぐ。胎芽が現れると魔女の力はなくなり、子が成人の姿になった頃に死ぬ。
長く生きて寿命が尽きるのを待つか、子をたった一人でなして死ぬか。自死を選ばないなら、どちらかしかない。
彼は害獣退治ギルドの前で、木の葉を集めている。箒で一つにまとめると空中でジリジリと燃やし、周辺を浄化魔法で清めている。害獣の血をしたたらせながら運んできた輩がいたのかもしれない。道の先の方まで既に浄化は終わっているようだ。
彼が汗をタオルで吹いてベンチの前に座った。普通の……白髪混じりのおじさんだ。ブラウンの優しそうな瞳はずっと変わらない。あの頃のまま。
『どの魔道具も面白いですね!』
キラキラした瞳で私の売るガラクタを見るのが印象的だった。大体の人は説明を聞くとため息をついて私を一瞥して出て行くのに。優しい男の子だなと思った。何もかもを楽しめる子なのかなとも。
魔道具屋と適当にペンキで書いて、道楽で開いていた店。
王家との秘密の取引が収入源で、店はただの暇つぶし。いつもなら一度来た人間は店を認識できないようにするのに、私はそのままにした。王家にもしばらくこの街に留まると伝えた。