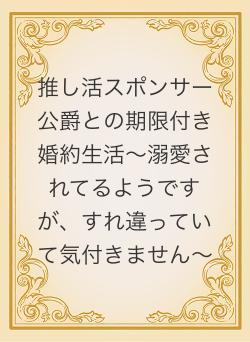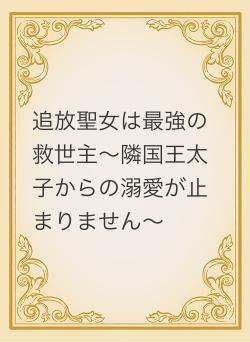見覚えのある城の廊下にメイジーは立っていた。
目の前にはジャシンスと王妃の姿がある。
(これは…………メイジーの記憶?)
振り上げらた彼女の腕にメイジーは瞼を閉じた。
鋭い痛みに小さな声を上げる。
「この役立たずが……っ!」
「……痛っ」
「目障りなのよ」
頬を扇子で叩かれたメイジーは床に倒れ込んだ。
「お母様、扇子が可哀想だわ。それにゴミは踏み潰すのよ! こうやってね……っ!」
ジャシンスは尖ったヒールで勢いよくメイジーの手のひらの甲を踏み潰す。
メイジーが声を出さずに身悶える様子を見て、彼女たちは嗤うのだ。
反応したら、もっとやられてしまうとわかっていた。
これがメイジーの日常。
誰もが見て見ぬふりを続けていた。
助けてくれる人は誰もいない……それはわかってる。
様子を見ている周りの人たちも同じ。
関わって怒りの矛先を向けられたくないのだろう。
(どうしてわたしは生きているんだろう……何のためにここにいるの?)
傷つきすぎた心は鈍って何も感じない。
感じないけれど奥底ではまだ僅かな期待が捨てきれないのだ。
物語のようにいつか王子様が助けてくれるかもしれない。
誰かがメイジーを救い出してくれたら……。
だけど現実はそううまくはいかない。
メイジーは役立たずとして、狭い狭い部屋で生きていくしかないのだから。
踏んでも叩かれても無反応なメイジーを見て、二人はつまらないと言いたげに暴言を吐きながら去っていく。
メイジーに駆け寄ってくるのは侍女のリディだけだ。