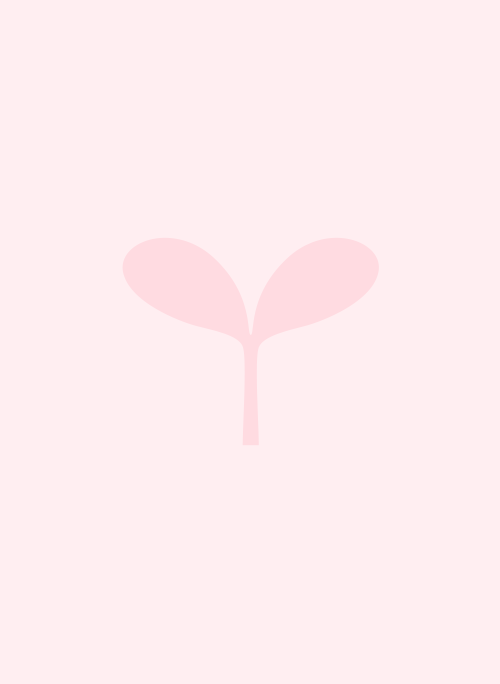三日の水曜日、俺は久しぶりに美和と会うことになってフェアレディーが走ってくるのを待っている。 昨日メールが来たんだ。
『今まで連絡しなくてごめんね。 明日やっと暇になったから遊びに来ない?』
『ほんとにいいの? 嫌われたかと思って心配したよ。』
『嫌ってなんか無いわよ。 あんまり忙しくて関われなかっただけ。』
『それならいいんだけど、何時に待合せればいい?』
『10時に迎えに行くわよ。 前みたいに待ってて。』
そんなわけで商店街の片隅で待っているのであります。 10時まであと15分。
母ちゃんたちにはもちろん内緒にしてある。 騒がれるとまずいからね。
だって香澄のことも有るんだし、あいつの親父さんにばれたらどんな顔で怒鳴り込んでくるか分からないし。
そりゃそうだよ。 親父さんは俺が香澄と結婚するもんだって本気で思ってるらしい。 厄介だよなあ。
魚は嫌いじゃないけど魚屋の主人になるのはちょっとねえ。
商店街の片隅にはアイドルが握手会なんかで使ったと思われるお立ち台が今もそのままに設置されている。 取り外す予定は無いらしい。
(相当に賑やかだったんだろうなあ。 あの頃はまだ人口も多かったから。) その隣はレコード屋だった。
チェッカーズだ、おニャン子クラブだ、南野陽子だって朝に晩に賑わってたんだろう。 今はその面影すら無いけど。
あの頃、アイドルだった人たちはそれぞれにおじさん おばさんになってあの頃の雰囲気は無い。 長く活動してきた人たちも引退したりして聞かなくなってきている。
俺たちだっていずれはそうなるのかなあ? 寂しい気もするけど、、、。
そこへ真っ赤なフェアレディーが走ってきた。 「待った?」
美和がウィンドウを開けて手を振っている。 助手席のドアを開けた。
「さあ行くわよ。」 アクセルを踏み込む。
これから美和が住んでいるマンションへ直行だ。 「今日は正面の玄関から入ってね。」
「ああ、そうだったね。」 「緊張してるの?」
「だって、ここしばらく話すことも無かったからさ。」 「そうよね。 ごめんなさいね。」
「忙しかったんでしょう?」 「新任だからやることが多くてさ。 それにバレー部の顧問もやってるから、、、。」
「バレー やったことが有るの?」 「中学生の時にやってたんだ。 試合にも出たんだけどさあ、、、。」
電車通りからマンションへ向かう一本道に入ると俄然美和はアクセルを踏み込んだ。 この辺りは擦れ違う車もあんまり居ないらしい。
その一本道を真っ赤なフェアレディーが爆走していく。 何か痺れるよね。
マンションに着くと俺は正面の玄関前で車を降りた。 「待っててね。 車を止めたら来るから。」
美和がそう言って地下駐車場へ下りていく。 かっこいいもんだなあ。
フェアレディーが地下へ消えてしまうとオートロックのドアが開いて住民らしいおばさんが出て行った。 「オートロックか、、、。」
最近では全く安全とは言えなくなったオートロックである。 中に入った瞬間に刺された人も居るらしい。
ということはさあ、出入りする人を四六時中カメラで監視してないといけないってわけか? 面倒くさい世の中だよなあ。
これじゃあ安心して週刊誌も読めないじゃないか。 ポケットに手を突っ込んでるだけで警察にマークされたりしてなあ。
それじゃあ南極に行っても手袋すら出来ないじゃないか。 冗談やめてくれ。
「入っていいわよ。」 美和が声を掛けてきた。
「顔は隠さないでね。 疑われるから。」 「面倒だなあ。」
「しょうがないの。 このマンションでも事件は起きたんだから。」 「そうなの?」
「2年前だったかなあ。 私みたいに新任だった中学校の先生がオートロックを入った瞬間に殴られて倒されて絞殺されたのよ。」 「そんな事件が有ったの?」
「それ以来、出入りする人には厳しくなったのよ。」 「そっか。」
管理人室の前を通ってエレベーターに乗る。 前回よりなんか緊張するなあ。
「エレベーターホールには監視カメラが有るから気を付けてね。」 「そんなこと言っちゃっていいの?」
「私が知ってる人だから覚えといてほしいのよ。」 「そっか。 そうなのか。」
知らないやつだったらどうしたんだろうなあ? まあ、そんなやつを中に入れるわけが無いか。
「オートロックだからって安心できないのよねえ。 玄関前に交番でも作ってほしいくらいだわ。」 エレベーターの中でそんなことを話しながらドアが開くのを待っている。 「やっぱり高いなあ ここ。」
「でしょう? 見下ろしてもいいけど飛び降りないでね。 マンションに居られなくなるから。」 美和は涼しい顔で笑っている。
だってパトカーでさえミニカーよりも小さく見えるんだぜ。 おっかねえよなあ。
以前のようにドアを開けて中に入る。 「なんかスッキリしたね。」
「分かる? あれからさあ要らない物をゴミに出したのよ。」 「呼んでくれたら手伝うのに。」
「若い女の一人暮らしだもん。 見られたくない物だって有るからさあ、、、。」 美和はキッチンに入るとお湯を沸かし始めた。
「コーヒー飲むでしょう?」 「う、うん。」
「素直なのねえ。」 「美和ちゃんにはね。」
「ねえねえ、弘明君。 美和って呼んでもいいのよ。 二人しか居ないんだから。」 「いやいやまだ美和なんて、、、。」
「私はいいのよ。 お母さんもお姉さんも知ってるんだから。」 「そりゃそうかもだけど、、、。」
「いいわ。 呼びたくなったら美和って呼んでね。」 そう言ってウインクするもんだから俺は舞い上がっちまった。
俺がコーヒーを飲んでいると美和は寝室へ入っていった。 (何をしてるんだろう?)
気にはなるけどだからって覗く気にもなれない。 「若い女の一人暮らし、、、か。」
美和がさっき言った言葉が頭を駆け巡っていく。 (見られたくない物って何なんだろう?)
考えても今の俺に分かるはずも無く、コーヒーを飲みながら美和が出てくるのを待っている。 30分ほどして出てきた美和に俺は驚いた。
「どうしたの? 驚いた顔して。」 「だってだってだって、水着じゃん。」
「刺激強過ぎたかな? 可愛いと思ったんだけど、、、。」 「でもでもでも、、、。」
「そっか。 まだ早かったか。」 美和は残念そうな顔で寝室へ戻っていった。
(あんなさあ、胸もお尻もクッキリな女にビキニなんか着られたら吹っ飛んじまうぜ。) 再びドアが開いて美和が出てきた。
今度はおとなしいブラウスとスカートにしたらしい。 ホッと溜息を吐いていると、、、。
「いつかさあ弘明君にも見てほしいなあ。 私の水着姿を。」 「分かったけど、、、。」
「怖いの?」 「いや、何となく、、、。」
「そっか。 まだまだ純粋なんだなあ。」 美和はそう言うと椅子に座ってコーヒーを飲んで笑った。
隅っこに置いてあるオーディオコンポからは古そうなジャズが聞こえている。 レコードジャケットには60年代のジャズって書いてある。
「私さあ、こういう古いジャズって好きなのよ。」 「そうなの?」
「うん。 それをね、こういう古いプレーヤーで聞くのが好きなの。」 「へえ、、、。」
分かるような分からないような話。 俺の頭の中はさっきの水着姿でいっぱいなのに、、、。
(今頃、香澄たちは何をしてるんだろうなあ?) 天井にはおしゃれな蛍光灯が揺れている。
美和は物思いに耽っている俺を見ながら静かにコーヒーを飲んでいる。 物音の無い静かな時間がそこに有った。
『今まで連絡しなくてごめんね。 明日やっと暇になったから遊びに来ない?』
『ほんとにいいの? 嫌われたかと思って心配したよ。』
『嫌ってなんか無いわよ。 あんまり忙しくて関われなかっただけ。』
『それならいいんだけど、何時に待合せればいい?』
『10時に迎えに行くわよ。 前みたいに待ってて。』
そんなわけで商店街の片隅で待っているのであります。 10時まであと15分。
母ちゃんたちにはもちろん内緒にしてある。 騒がれるとまずいからね。
だって香澄のことも有るんだし、あいつの親父さんにばれたらどんな顔で怒鳴り込んでくるか分からないし。
そりゃそうだよ。 親父さんは俺が香澄と結婚するもんだって本気で思ってるらしい。 厄介だよなあ。
魚は嫌いじゃないけど魚屋の主人になるのはちょっとねえ。
商店街の片隅にはアイドルが握手会なんかで使ったと思われるお立ち台が今もそのままに設置されている。 取り外す予定は無いらしい。
(相当に賑やかだったんだろうなあ。 あの頃はまだ人口も多かったから。) その隣はレコード屋だった。
チェッカーズだ、おニャン子クラブだ、南野陽子だって朝に晩に賑わってたんだろう。 今はその面影すら無いけど。
あの頃、アイドルだった人たちはそれぞれにおじさん おばさんになってあの頃の雰囲気は無い。 長く活動してきた人たちも引退したりして聞かなくなってきている。
俺たちだっていずれはそうなるのかなあ? 寂しい気もするけど、、、。
そこへ真っ赤なフェアレディーが走ってきた。 「待った?」
美和がウィンドウを開けて手を振っている。 助手席のドアを開けた。
「さあ行くわよ。」 アクセルを踏み込む。
これから美和が住んでいるマンションへ直行だ。 「今日は正面の玄関から入ってね。」
「ああ、そうだったね。」 「緊張してるの?」
「だって、ここしばらく話すことも無かったからさ。」 「そうよね。 ごめんなさいね。」
「忙しかったんでしょう?」 「新任だからやることが多くてさ。 それにバレー部の顧問もやってるから、、、。」
「バレー やったことが有るの?」 「中学生の時にやってたんだ。 試合にも出たんだけどさあ、、、。」
電車通りからマンションへ向かう一本道に入ると俄然美和はアクセルを踏み込んだ。 この辺りは擦れ違う車もあんまり居ないらしい。
その一本道を真っ赤なフェアレディーが爆走していく。 何か痺れるよね。
マンションに着くと俺は正面の玄関前で車を降りた。 「待っててね。 車を止めたら来るから。」
美和がそう言って地下駐車場へ下りていく。 かっこいいもんだなあ。
フェアレディーが地下へ消えてしまうとオートロックのドアが開いて住民らしいおばさんが出て行った。 「オートロックか、、、。」
最近では全く安全とは言えなくなったオートロックである。 中に入った瞬間に刺された人も居るらしい。
ということはさあ、出入りする人を四六時中カメラで監視してないといけないってわけか? 面倒くさい世の中だよなあ。
これじゃあ安心して週刊誌も読めないじゃないか。 ポケットに手を突っ込んでるだけで警察にマークされたりしてなあ。
それじゃあ南極に行っても手袋すら出来ないじゃないか。 冗談やめてくれ。
「入っていいわよ。」 美和が声を掛けてきた。
「顔は隠さないでね。 疑われるから。」 「面倒だなあ。」
「しょうがないの。 このマンションでも事件は起きたんだから。」 「そうなの?」
「2年前だったかなあ。 私みたいに新任だった中学校の先生がオートロックを入った瞬間に殴られて倒されて絞殺されたのよ。」 「そんな事件が有ったの?」
「それ以来、出入りする人には厳しくなったのよ。」 「そっか。」
管理人室の前を通ってエレベーターに乗る。 前回よりなんか緊張するなあ。
「エレベーターホールには監視カメラが有るから気を付けてね。」 「そんなこと言っちゃっていいの?」
「私が知ってる人だから覚えといてほしいのよ。」 「そっか。 そうなのか。」
知らないやつだったらどうしたんだろうなあ? まあ、そんなやつを中に入れるわけが無いか。
「オートロックだからって安心できないのよねえ。 玄関前に交番でも作ってほしいくらいだわ。」 エレベーターの中でそんなことを話しながらドアが開くのを待っている。 「やっぱり高いなあ ここ。」
「でしょう? 見下ろしてもいいけど飛び降りないでね。 マンションに居られなくなるから。」 美和は涼しい顔で笑っている。
だってパトカーでさえミニカーよりも小さく見えるんだぜ。 おっかねえよなあ。
以前のようにドアを開けて中に入る。 「なんかスッキリしたね。」
「分かる? あれからさあ要らない物をゴミに出したのよ。」 「呼んでくれたら手伝うのに。」
「若い女の一人暮らしだもん。 見られたくない物だって有るからさあ、、、。」 美和はキッチンに入るとお湯を沸かし始めた。
「コーヒー飲むでしょう?」 「う、うん。」
「素直なのねえ。」 「美和ちゃんにはね。」
「ねえねえ、弘明君。 美和って呼んでもいいのよ。 二人しか居ないんだから。」 「いやいやまだ美和なんて、、、。」
「私はいいのよ。 お母さんもお姉さんも知ってるんだから。」 「そりゃそうかもだけど、、、。」
「いいわ。 呼びたくなったら美和って呼んでね。」 そう言ってウインクするもんだから俺は舞い上がっちまった。
俺がコーヒーを飲んでいると美和は寝室へ入っていった。 (何をしてるんだろう?)
気にはなるけどだからって覗く気にもなれない。 「若い女の一人暮らし、、、か。」
美和がさっき言った言葉が頭を駆け巡っていく。 (見られたくない物って何なんだろう?)
考えても今の俺に分かるはずも無く、コーヒーを飲みながら美和が出てくるのを待っている。 30分ほどして出てきた美和に俺は驚いた。
「どうしたの? 驚いた顔して。」 「だってだってだって、水着じゃん。」
「刺激強過ぎたかな? 可愛いと思ったんだけど、、、。」 「でもでもでも、、、。」
「そっか。 まだ早かったか。」 美和は残念そうな顔で寝室へ戻っていった。
(あんなさあ、胸もお尻もクッキリな女にビキニなんか着られたら吹っ飛んじまうぜ。) 再びドアが開いて美和が出てきた。
今度はおとなしいブラウスとスカートにしたらしい。 ホッと溜息を吐いていると、、、。
「いつかさあ弘明君にも見てほしいなあ。 私の水着姿を。」 「分かったけど、、、。」
「怖いの?」 「いや、何となく、、、。」
「そっか。 まだまだ純粋なんだなあ。」 美和はそう言うと椅子に座ってコーヒーを飲んで笑った。
隅っこに置いてあるオーディオコンポからは古そうなジャズが聞こえている。 レコードジャケットには60年代のジャズって書いてある。
「私さあ、こういう古いジャズって好きなのよ。」 「そうなの?」
「うん。 それをね、こういう古いプレーヤーで聞くのが好きなの。」 「へえ、、、。」
分かるような分からないような話。 俺の頭の中はさっきの水着姿でいっぱいなのに、、、。
(今頃、香澄たちは何をしてるんだろうなあ?) 天井にはおしゃれな蛍光灯が揺れている。
美和は物思いに耽っている俺を見ながら静かにコーヒーを飲んでいる。 物音の無い静かな時間がそこに有った。