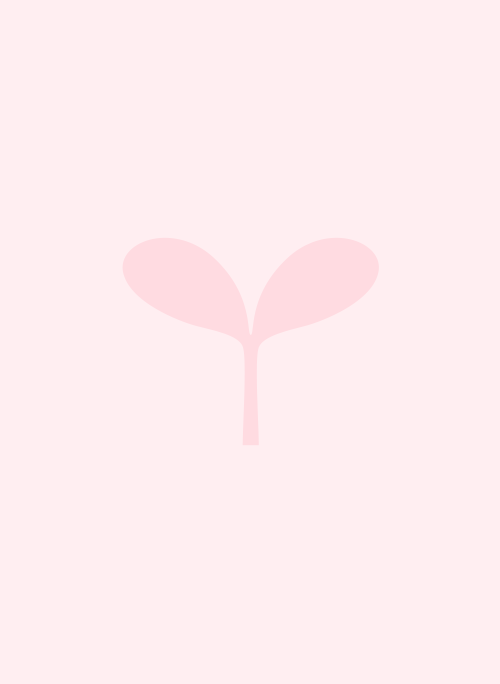「そういえばさあ、りっちゃんはどうしたの?」 床の掃除をしていた香澄が聞いてきた。
「あいつなら先に帰っちゃったよ。」 「ひどいなあ。 私と一緒にやれって言われてるのに。」
「お前が怒らせたからなあ。」 「それは弘明君がチクったからでしょう?」
「なになに? 俺のせいだってか?」 「そうよ。 違うの?」
「お前が言わなかったら俺だって言わないよ。」
「ひどーーーい。 また私なのね? 泣いてやるーーーーー。」 そう言ってトイレの中で香澄は泣き始めた。
「お前、女優になれるぞ。」 「だって、、、。」
「さっさと終わらせないと校門が閉まっちまうぞ。」 「やばいやばい。 どうしようどうしよう?」
「迷ってないでやれよ。」 「ひどいなあ。 ちょっとくらい手伝ってよ。」
「女子トイレには入れませんから。」 「見なかったことにするから手伝ってよ。」
「しゃあねえなあ。 手伝ってやるか。 でも内緒だぜ。」 「分かった分かった。」
俺はブラシを取ると便器を洗い始めた。 昔は全部和式だったのに今はみんな洋式なんだよなあ。
香澄も隣の個室で掃除をしている。 時々「フー、、、。」とか「もう、、、。」とか言うのが聞こえる。
まだまだ3階のトイレが残っている。 さっさと終わらせなきゃなあ。
「よし。 終わった。」 俺が個室から出てくると香澄が俺のほうを振り向いた。
俺は窓のほうを向いてたからそんな香澄には気付かなくて正面から突っ込んでしまった。 「あったかーーーい。 弘明君あったかーい。」
「おいおい、トイレの中でこれは無いだろう。」 「いいの。 何処だっていいの。」
「幸せなやつだなあ。」 珍しく俺は香澄の頭を撫でてみた。
「優しいのねえ。 弘明君?」 「今だけね。」
「何よ? 今だけって何よ?」 「だから今だけなの。」
「ああ、待ってよーーー。 ずるーーーい。」 「さっさと来ねえと終わんねえぞ。」
またまたここでも追いかけっこをする二人なのでありました。
それでまあトイレ掃除が終わったのは5時を過ぎてから。 それで教室に戻ると荷物を持ってバタバタと昇降口まで猛ダッシュ!
「いやあ疲れた疲れた。」 「私もよ。 こんなに走らせるんだから、、、。」
「急がねえと閉まるだろうがよ。」 「だからってここまでダッシュすることも無いんじゃないの?」
「いいじゃんか。 日頃の運動不足の解消だ。」 「へえ。 そうなんだ。」
「何か文句でも?」 「有りませんことよ。」
駅まで行く途中で律子から電話が掛かってきた。 「ねえねえ、トイレ掃除は終わった?」
「俺も手伝ったからさっき終わったところだよ。」 「なあんだ、弘明君が手伝ったのか。」
「お前が逃げ出すからこうなったんだぞ。」 「しょうがないじゃない。 側溝に嵌ったんだから。」
「それとこれは別の話だと思うけどなあ。」 「いいからいいから。 香澄に謝っといてね。」
「何で俺が謝るんだよ?」 反論したけど律子は電話を切ってしまった。
「何だって?」 「サボったこと香澄に謝っといてねエ。だって。」 「ひどーーーい。 私には1日許さないって言っといて。」
膨れっ面で香澄は歩いていく。 俺はコンビニに飛び込んだ。
「弘明君、、、。 あれ? 居ないや。」 香澄は俺が居なくなったのを不思議に思ったのか交差点にまで舞い戻ってきた。
俺はというとコンビニでまたまたアイス最中を買っている最中。 「これでも食わせて黙らせるしかないな。」
店を出ると駐車場で香澄がボーっとしているのが見えた。 「ほら、これ。」
「ワーーーー、ありがとねえ。」 「調子いいんだからなあ、お前は。」
「いいの。 弘明君さえ居てくれたらそれでいいの。」 「また始まった。」
「またって何よ? またって?」 「夢見る少女じゃ居られないのよ。」
「いいんだもん。 私は夢見る少女なんだもん。」 「お前はどう見ても夢に浮かされる高校生おばさんだけどなあ。」
「何だって? もう一回言ってみなさいよ。」 「ほらほら始まった。 高校生おばさんだ。」
「高校生おばさん? 何それ?」 「お前だよ。 お前。」
「私はおばさんじゃないから。」 「どっからどう見てもおばさんだけど。」
「何をどう見たらおばさんなのよ? ねえ弘明君?」 「そうやってわざわざ突っ込んでくるからおばさんなんだよ。 分かってねえなあ。」
「私はまだまだ少女ですから。」 「はいはい。 少女の皮をかぶったおばさんですこと。」
「いいんだもん。 弘明君なんか知らないんだから。」 「5分と無視できないお前が何を言う?」
「何を言う?」 「ほら1分も経たないうちに絡んできやがった。」
「だって気になるんだもん。」 「へえ、そんなに俺が気になるか?」
「だってだって小学生の頃から知ってるのよ。 気にならないほうがおかしいわよ。」 「へえ、百合たちは全く気にもしてないのにか?」
「あの人たちは別。 私は違うの。」 「都合がいいなあ。 お前の解釈は。」
そこへ電車が入ってきた。 「行くぞ。」
香澄はまたまた俺に引っ付いて走っている。 このままで今年も終わるのかな?
去年だってさんざんに喧嘩したけど最後にはこうしてくっ付いてたんだ。 飽きないやつだよなあ。
それもさあ「弘明君は私の気持ちなんてまるで分かってくれない。」とかってブーブー言いながらくっ付いてくるんだぜ。 やってらんねえよなあ。
「ねえねえ弘明君 何してんの?」 「見れば分かるだろう? 何にもしてねえよ。」
「あっそう。」 「冷たいやつだなあ。 人に聞いといてあっそうは無いだろう?」
「弘明君だってよくやるじゃん。」 「俺がやるからって真似しなくてもいいの。」
「つまんないなあ。 真似したっていいじゃない。」 「またまた、私の彼氏だからって言いたいんだろう?」
「よくお分かりで。」 「お前のことだ。 それくらいは読めるよ。」
「何だって? 私が単細胞とでも言いたいの?」 「お前の行動は単純だからなあ。」
「悪かったわね。 単純で。」 「怒っても可愛くねえぞ。」
「いいですよーーーーーーーだ。 どうせ可愛くないんだもん。」 「その顔で近付いてくるなっての。」
「またまた私を馬鹿にしたわね? 許さないんだから。」 「一日に何回同じことを言うんだろうねえ? このお嬢様は。」
「いいんだもん。 何回でも言ってやるもん。」 「一回言ったら終わりやと思いますけどなあ。」
「何回でも使えるのよ。 オホホ。」 「きもっ。」
「きもって言ったわよね? ねえ弘明君?」 「だからその顔で載ってくるなっての。 重たいんだから。」
「えーーーーー? 今度は重たいって言ったわね? 許さないんだから。」 「おいおい、怒ってる間に駅を通り過ぎたようですぞ。 お嬢様。」
「うわうわうわ、、、どうしよう?」 「知らねえぞ。 自分でやったんだからな。」
「いいや。 弘明君の家に泊めてもらおうっと。」 「何で俺なんだよ?」
「彼女ですから。」 「いつからだよ?」
「生まれる前からよ。」 「あっそう。 好きにしてろや。」
「分かった。 好きにする。」 そう言って香澄は俺の家にまで付いてきた。
「あらあら香澄ちゃん よく来たねえ。」 「喧嘩してたら降り損ねちゃってさあ。」
「言わないでーーーーー。」 「たぶんそうだろうなって思ったわよ。 香澄ちゃん。」
「ばれちゃった。」 「やることが単純なんだよ。 お前は。」
「どうもすいません。 単細胞で。」 「ここで謝られても困るんだけどなあ。」
「弘明、今夜は焼き肉にするわ。」 「あいよ。」
そんなわけでちゃっかりと香澄は夕食にまで有り付けたのでありました。 トントン。
「あいつなら先に帰っちゃったよ。」 「ひどいなあ。 私と一緒にやれって言われてるのに。」
「お前が怒らせたからなあ。」 「それは弘明君がチクったからでしょう?」
「なになに? 俺のせいだってか?」 「そうよ。 違うの?」
「お前が言わなかったら俺だって言わないよ。」
「ひどーーーい。 また私なのね? 泣いてやるーーーーー。」 そう言ってトイレの中で香澄は泣き始めた。
「お前、女優になれるぞ。」 「だって、、、。」
「さっさと終わらせないと校門が閉まっちまうぞ。」 「やばいやばい。 どうしようどうしよう?」
「迷ってないでやれよ。」 「ひどいなあ。 ちょっとくらい手伝ってよ。」
「女子トイレには入れませんから。」 「見なかったことにするから手伝ってよ。」
「しゃあねえなあ。 手伝ってやるか。 でも内緒だぜ。」 「分かった分かった。」
俺はブラシを取ると便器を洗い始めた。 昔は全部和式だったのに今はみんな洋式なんだよなあ。
香澄も隣の個室で掃除をしている。 時々「フー、、、。」とか「もう、、、。」とか言うのが聞こえる。
まだまだ3階のトイレが残っている。 さっさと終わらせなきゃなあ。
「よし。 終わった。」 俺が個室から出てくると香澄が俺のほうを振り向いた。
俺は窓のほうを向いてたからそんな香澄には気付かなくて正面から突っ込んでしまった。 「あったかーーーい。 弘明君あったかーい。」
「おいおい、トイレの中でこれは無いだろう。」 「いいの。 何処だっていいの。」
「幸せなやつだなあ。」 珍しく俺は香澄の頭を撫でてみた。
「優しいのねえ。 弘明君?」 「今だけね。」
「何よ? 今だけって何よ?」 「だから今だけなの。」
「ああ、待ってよーーー。 ずるーーーい。」 「さっさと来ねえと終わんねえぞ。」
またまたここでも追いかけっこをする二人なのでありました。
それでまあトイレ掃除が終わったのは5時を過ぎてから。 それで教室に戻ると荷物を持ってバタバタと昇降口まで猛ダッシュ!
「いやあ疲れた疲れた。」 「私もよ。 こんなに走らせるんだから、、、。」
「急がねえと閉まるだろうがよ。」 「だからってここまでダッシュすることも無いんじゃないの?」
「いいじゃんか。 日頃の運動不足の解消だ。」 「へえ。 そうなんだ。」
「何か文句でも?」 「有りませんことよ。」
駅まで行く途中で律子から電話が掛かってきた。 「ねえねえ、トイレ掃除は終わった?」
「俺も手伝ったからさっき終わったところだよ。」 「なあんだ、弘明君が手伝ったのか。」
「お前が逃げ出すからこうなったんだぞ。」 「しょうがないじゃない。 側溝に嵌ったんだから。」
「それとこれは別の話だと思うけどなあ。」 「いいからいいから。 香澄に謝っといてね。」
「何で俺が謝るんだよ?」 反論したけど律子は電話を切ってしまった。
「何だって?」 「サボったこと香澄に謝っといてねエ。だって。」 「ひどーーーい。 私には1日許さないって言っといて。」
膨れっ面で香澄は歩いていく。 俺はコンビニに飛び込んだ。
「弘明君、、、。 あれ? 居ないや。」 香澄は俺が居なくなったのを不思議に思ったのか交差点にまで舞い戻ってきた。
俺はというとコンビニでまたまたアイス最中を買っている最中。 「これでも食わせて黙らせるしかないな。」
店を出ると駐車場で香澄がボーっとしているのが見えた。 「ほら、これ。」
「ワーーーー、ありがとねえ。」 「調子いいんだからなあ、お前は。」
「いいの。 弘明君さえ居てくれたらそれでいいの。」 「また始まった。」
「またって何よ? またって?」 「夢見る少女じゃ居られないのよ。」
「いいんだもん。 私は夢見る少女なんだもん。」 「お前はどう見ても夢に浮かされる高校生おばさんだけどなあ。」
「何だって? もう一回言ってみなさいよ。」 「ほらほら始まった。 高校生おばさんだ。」
「高校生おばさん? 何それ?」 「お前だよ。 お前。」
「私はおばさんじゃないから。」 「どっからどう見てもおばさんだけど。」
「何をどう見たらおばさんなのよ? ねえ弘明君?」 「そうやってわざわざ突っ込んでくるからおばさんなんだよ。 分かってねえなあ。」
「私はまだまだ少女ですから。」 「はいはい。 少女の皮をかぶったおばさんですこと。」
「いいんだもん。 弘明君なんか知らないんだから。」 「5分と無視できないお前が何を言う?」
「何を言う?」 「ほら1分も経たないうちに絡んできやがった。」
「だって気になるんだもん。」 「へえ、そんなに俺が気になるか?」
「だってだって小学生の頃から知ってるのよ。 気にならないほうがおかしいわよ。」 「へえ、百合たちは全く気にもしてないのにか?」
「あの人たちは別。 私は違うの。」 「都合がいいなあ。 お前の解釈は。」
そこへ電車が入ってきた。 「行くぞ。」
香澄はまたまた俺に引っ付いて走っている。 このままで今年も終わるのかな?
去年だってさんざんに喧嘩したけど最後にはこうしてくっ付いてたんだ。 飽きないやつだよなあ。
それもさあ「弘明君は私の気持ちなんてまるで分かってくれない。」とかってブーブー言いながらくっ付いてくるんだぜ。 やってらんねえよなあ。
「ねえねえ弘明君 何してんの?」 「見れば分かるだろう? 何にもしてねえよ。」
「あっそう。」 「冷たいやつだなあ。 人に聞いといてあっそうは無いだろう?」
「弘明君だってよくやるじゃん。」 「俺がやるからって真似しなくてもいいの。」
「つまんないなあ。 真似したっていいじゃない。」 「またまた、私の彼氏だからって言いたいんだろう?」
「よくお分かりで。」 「お前のことだ。 それくらいは読めるよ。」
「何だって? 私が単細胞とでも言いたいの?」 「お前の行動は単純だからなあ。」
「悪かったわね。 単純で。」 「怒っても可愛くねえぞ。」
「いいですよーーーーーーーだ。 どうせ可愛くないんだもん。」 「その顔で近付いてくるなっての。」
「またまた私を馬鹿にしたわね? 許さないんだから。」 「一日に何回同じことを言うんだろうねえ? このお嬢様は。」
「いいんだもん。 何回でも言ってやるもん。」 「一回言ったら終わりやと思いますけどなあ。」
「何回でも使えるのよ。 オホホ。」 「きもっ。」
「きもって言ったわよね? ねえ弘明君?」 「だからその顔で載ってくるなっての。 重たいんだから。」
「えーーーーー? 今度は重たいって言ったわね? 許さないんだから。」 「おいおい、怒ってる間に駅を通り過ぎたようですぞ。 お嬢様。」
「うわうわうわ、、、どうしよう?」 「知らねえぞ。 自分でやったんだからな。」
「いいや。 弘明君の家に泊めてもらおうっと。」 「何で俺なんだよ?」
「彼女ですから。」 「いつからだよ?」
「生まれる前からよ。」 「あっそう。 好きにしてろや。」
「分かった。 好きにする。」 そう言って香澄は俺の家にまで付いてきた。
「あらあら香澄ちゃん よく来たねえ。」 「喧嘩してたら降り損ねちゃってさあ。」
「言わないでーーーーー。」 「たぶんそうだろうなって思ったわよ。 香澄ちゃん。」
「ばれちゃった。」 「やることが単純なんだよ。 お前は。」
「どうもすいません。 単細胞で。」 「ここで謝られても困るんだけどなあ。」
「弘明、今夜は焼き肉にするわ。」 「あいよ。」
そんなわけでちゃっかりと香澄は夕食にまで有り付けたのでありました。 トントン。