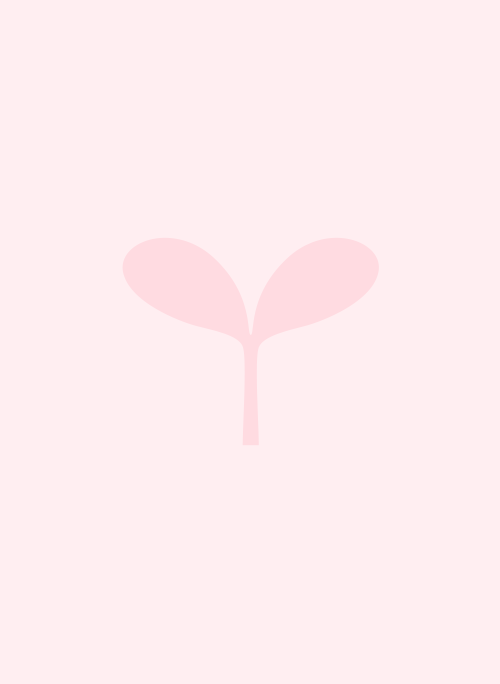真昼の電車はそんなに混雑も無くて座ろうと思えば何処にでも座れる。 俺は香澄の隣に座ってみた。
「珍しいのねえ?」 「何がだよ?」
「私の隣に座るなんて、、、。」 「まあいいじゃん。 たまにはこういうことも有るよ。」
「たまには、、、か。」 香澄は寂しそうな顔をして窓の外に目をやった。
ガタンゴトン、電車はいつものように同じリズムで走っている。 日差しも暖かくてまた寝ちまいそうだな。
「寝ちゃダメだからね。」 香澄がそう言って脇を突いてくる。
ボーっとしていると不意に突いてくるから目が覚めてしまう。 まあいいか。
いつものように電車を降りると静かな商店街を歩く。 (昔は賑やかだったんだろうなあ。)
昭和の頃には人気歌手を呼んで握手会とかサイン会もやったって言うから相当に賑やかだったんだろう。 よく見るとすみっこにお立ち台が残っている。
ブラブラと商店街を抜けて供養塔を真正面に見ながら歩いてくる。 もちろんパンダ焼も買ってね。
家に戻ってくると居間のテーブルにパンダ焼を置いて俺は部屋に引っ込む。 そしたら呼ぶ声が聞こえた。
「美和ちゃんが来たよ。」 旅行から帰ってきたらしい姉ちゃんだ。 俺はまたまたドキッとした。
姉ちゃんと美和は友達だったっけ? 兎にも角にも半信半疑で階段を駆け下りる。
「どうしたの? そんなに慌てちゃって、、、。」 「いやいや、美和先生が来たって言うからさ、、、。」
「こんにちは。」 玄関に立っていたのは紛れもなく美和だった。
「私ね、お姉さんと友達だったの。 知らなかったわよね?」 「そりゃあまあ、、、。」
「あんた、何緊張してるの?」 「いや、その、別に、、、。」
「あんたらしくないわよ。 しっかりしなさい。」 「そうは言うけど、、、。」
何の用事で来たのかは知らない。 別に知る必要も無いと思っている。
姉ちゃんと美和先生は楽しそうに話し込んでいる。 俺は一人ぼっちだ。
まあいいんだけどなあ。 子供の頃からそうだったから。
だってさあ、姉ちゃんが相手じゃあ遊べないよ。 姉ちゃんは読書家だったしね。
でもその頃から美和先生とは友達だったのかなあ? その辺は分かんない。
母ちゃんが事務所で働き始めたのが10年前だから、、、。 それにしても分かんない。
「天気いいなあ。」 「遊びにでも行ってくれば?」
「冷たいなあ。」 「退屈そうなんだもん。」
「そりゃさあ、、、。」 「分かった。 美和ちゃんを取られたから妬いてるんでしょう?」
「そんなんじゃないってば。」 そう言ってすっ飛んでいった俺を見て姉ちゃんたちは爆笑している。
(そんなに笑わなくてもいいだろうに、、、。) 何となく俺は立場を失ってしまった。
そこへ母ちゃんが帰ってきた。 「あらあら美和ちゃんも来てたの?」
居間では3人が盛り上がっている。 姉ちゃんが俺を呼んだ。
「へ。 行くかってんだ。」 部屋に籠った俺はラジオのボリュームを上げた。
そこへ香澄から電話が掛かってきた。 「ねえねえ、面白い物を見付けたから来ない?」
「ラッキー! 感謝します 香澄ちゃん。」 「何だよ 気持ち悪いなあ。」
電話を切った俺は靴を履くと玄関から飛び出していった。 「美和ちゃんが来たから妬いてるのねえ。」
「そうかなあ?」 「たぶんね、美和ちゃんのことが好きなんだよ。」
「えーーーー? まさか。」 「まさかかもしれないよ。」
母ちゃんは真面目な顔で美和を見詰めた。
香澄の家は魚屋なんだ。 たまに生きた蛸も仕入れるって言ってたっけ。
ここからだとバスで15分くらい。 バスを降りると目の前が店だ。
分かりやすい〈魚屋〉って看板がデカデカと建っているからすぐに分かる。 「こんちはーーー!」
店から奥に声を掛ける。 「もう来たの? 速いなあ。」
「そりゃそうだよ。 家には居づらくて、、、。」 「何か有ったの?」
「美和先生が遊びに来てるんだ。 母ちゃんも姉ちゃんも知り合いだから3人で盛り上がっちゃって、、、。」 「そりゃ大変だ。 まあ上がってよ。」
この店、〈魚屋〉はおじいさんの頃からやってたんだって。 「気の利いた名前は無いのか?」っておばあさんにも言われたらしいんだけど「これでいい。」って譲らなかったんだって。
確かに〈魚屋〉は分かりやすい。 でもなんかちょっとなあ、、、。
魚屋っていう魚屋も無いだろうなあ。 香澄のお父さんは魚屋で働いてた人だった。
お母さんはおじいさんの娘さん。 だからお父さんは婿なんだね。
「面白い物って何だよ?」 「まあまあ慌てない慌てない。 すぐ見せるから。」
香澄はそう言うと冷蔵ケースを開いた。 「見てよ。 これ。」
「何だ?」 「エビに入ってたカニの子供。」
「ちっちぇえなあ。 こんなにちっちぇえのか?」 「そうなんだって。 殻の隙間に入り込んでたんだってよ。」
「ホタテや何かに入り込んでるのは聞いたことが有るけど、まさかエビにまで入り込んでるとはねえ。」 「珍しいんだって。 お父さんもびっくりしてた。」
「だろうなあ。 聞いたことも見たことも無いよ。」 「あらあら、遊びに来たの?」
俺たちの話し声を聞いたのか、お母さんがお茶とお菓子を持ってきた。 「いや、ちょっと用事が有ったんで来ただけです。」
「まあまあ、香澄も用事が多いからねえ。 これからもよろしくね。」 ペコリと頭を下げたお母さんは店のほうに行ってしまった。
ここからはまた二人きりだ。 なんか緊張するなあ。
「弘明君さあ、何緊張してるの?」 (ギク、気付いてやがる。)
「気付いてるって思ったでしょう?」 「いやいや、その、、、。」
「いいんだよ。 そういう所が私は好きなの。」 「香澄がか?」
「ずーーーーーっと好きなのに気付いてくれないんだよなあ。 意地悪。」 「そんなこと言っても、、、。」
「まあいいや。 高橋先生に振られるまで私は待ってまーす。」 「嫌なやつだなあ。」
「女ですから。」 「気取っても可愛くないぞ。」
「いいもん。 高橋先生より可愛くなってやるんだもん。」 「どうぞどうぞ。 三橋にでも告ってもらえよ。」
「やだやだ。 私は弘明君一択なの。」 「ごちそうさまでした。」
「えーーーーーー? こんな女の子の気持ちを無駄にしないでよ。」 「いつか縁が有ったら考えてやるよ。 じゃあな。」
しばらく香澄と話し込んでから俺は家を出た。 「もうそろそろ帰ってるよなあ?」
そんなことを考えながらバス通りを歩いていく。 行き過ぎるバスを横目で見ながら、、、。
もう5時を過ぎていつもなら母ちゃんも夕食の支度を始める頃だ。 バス通りを歩くのもいいなあ。
駅前通りも少しずつ賑やかになってきてる。 仕事帰りの人たちなのかな?
ブラブラと商店街を歩いて供養塔を見ながら歩いている。 救急車が走り過ぎていった。
やっと家に着いてドアを開けてみると、、、。 まだまだ美和たちの笑い声が聞こえてくる。
「ゲ、、、まだ居るじゃん。」 「おー、お帰り。 美和ちゃんと話さないのか?」
「い、いやいいよ。 用事が有るから。」 「まあ、いいじゃない。 話して行きなさいよ。」
姉ちゃんまでがニコニコしながら俺を誘ってくる。 「お腹も空いたろう? 夕食作るからおいでよ。」
夕食とまで言われたら行かないわけにいかなくなる。 それでも俺は何とかならないものかと思案を巡らせている。
食堂に入ってみると姉ちゃんが美和の隣に俺を座らせた。 (緊張しちまうなあ。)
「珍しいのねえ?」 「何がだよ?」
「私の隣に座るなんて、、、。」 「まあいいじゃん。 たまにはこういうことも有るよ。」
「たまには、、、か。」 香澄は寂しそうな顔をして窓の外に目をやった。
ガタンゴトン、電車はいつものように同じリズムで走っている。 日差しも暖かくてまた寝ちまいそうだな。
「寝ちゃダメだからね。」 香澄がそう言って脇を突いてくる。
ボーっとしていると不意に突いてくるから目が覚めてしまう。 まあいいか。
いつものように電車を降りると静かな商店街を歩く。 (昔は賑やかだったんだろうなあ。)
昭和の頃には人気歌手を呼んで握手会とかサイン会もやったって言うから相当に賑やかだったんだろう。 よく見るとすみっこにお立ち台が残っている。
ブラブラと商店街を抜けて供養塔を真正面に見ながら歩いてくる。 もちろんパンダ焼も買ってね。
家に戻ってくると居間のテーブルにパンダ焼を置いて俺は部屋に引っ込む。 そしたら呼ぶ声が聞こえた。
「美和ちゃんが来たよ。」 旅行から帰ってきたらしい姉ちゃんだ。 俺はまたまたドキッとした。
姉ちゃんと美和は友達だったっけ? 兎にも角にも半信半疑で階段を駆け下りる。
「どうしたの? そんなに慌てちゃって、、、。」 「いやいや、美和先生が来たって言うからさ、、、。」
「こんにちは。」 玄関に立っていたのは紛れもなく美和だった。
「私ね、お姉さんと友達だったの。 知らなかったわよね?」 「そりゃあまあ、、、。」
「あんた、何緊張してるの?」 「いや、その、別に、、、。」
「あんたらしくないわよ。 しっかりしなさい。」 「そうは言うけど、、、。」
何の用事で来たのかは知らない。 別に知る必要も無いと思っている。
姉ちゃんと美和先生は楽しそうに話し込んでいる。 俺は一人ぼっちだ。
まあいいんだけどなあ。 子供の頃からそうだったから。
だってさあ、姉ちゃんが相手じゃあ遊べないよ。 姉ちゃんは読書家だったしね。
でもその頃から美和先生とは友達だったのかなあ? その辺は分かんない。
母ちゃんが事務所で働き始めたのが10年前だから、、、。 それにしても分かんない。
「天気いいなあ。」 「遊びにでも行ってくれば?」
「冷たいなあ。」 「退屈そうなんだもん。」
「そりゃさあ、、、。」 「分かった。 美和ちゃんを取られたから妬いてるんでしょう?」
「そんなんじゃないってば。」 そう言ってすっ飛んでいった俺を見て姉ちゃんたちは爆笑している。
(そんなに笑わなくてもいいだろうに、、、。) 何となく俺は立場を失ってしまった。
そこへ母ちゃんが帰ってきた。 「あらあら美和ちゃんも来てたの?」
居間では3人が盛り上がっている。 姉ちゃんが俺を呼んだ。
「へ。 行くかってんだ。」 部屋に籠った俺はラジオのボリュームを上げた。
そこへ香澄から電話が掛かってきた。 「ねえねえ、面白い物を見付けたから来ない?」
「ラッキー! 感謝します 香澄ちゃん。」 「何だよ 気持ち悪いなあ。」
電話を切った俺は靴を履くと玄関から飛び出していった。 「美和ちゃんが来たから妬いてるのねえ。」
「そうかなあ?」 「たぶんね、美和ちゃんのことが好きなんだよ。」
「えーーーー? まさか。」 「まさかかもしれないよ。」
母ちゃんは真面目な顔で美和を見詰めた。
香澄の家は魚屋なんだ。 たまに生きた蛸も仕入れるって言ってたっけ。
ここからだとバスで15分くらい。 バスを降りると目の前が店だ。
分かりやすい〈魚屋〉って看板がデカデカと建っているからすぐに分かる。 「こんちはーーー!」
店から奥に声を掛ける。 「もう来たの? 速いなあ。」
「そりゃそうだよ。 家には居づらくて、、、。」 「何か有ったの?」
「美和先生が遊びに来てるんだ。 母ちゃんも姉ちゃんも知り合いだから3人で盛り上がっちゃって、、、。」 「そりゃ大変だ。 まあ上がってよ。」
この店、〈魚屋〉はおじいさんの頃からやってたんだって。 「気の利いた名前は無いのか?」っておばあさんにも言われたらしいんだけど「これでいい。」って譲らなかったんだって。
確かに〈魚屋〉は分かりやすい。 でもなんかちょっとなあ、、、。
魚屋っていう魚屋も無いだろうなあ。 香澄のお父さんは魚屋で働いてた人だった。
お母さんはおじいさんの娘さん。 だからお父さんは婿なんだね。
「面白い物って何だよ?」 「まあまあ慌てない慌てない。 すぐ見せるから。」
香澄はそう言うと冷蔵ケースを開いた。 「見てよ。 これ。」
「何だ?」 「エビに入ってたカニの子供。」
「ちっちぇえなあ。 こんなにちっちぇえのか?」 「そうなんだって。 殻の隙間に入り込んでたんだってよ。」
「ホタテや何かに入り込んでるのは聞いたことが有るけど、まさかエビにまで入り込んでるとはねえ。」 「珍しいんだって。 お父さんもびっくりしてた。」
「だろうなあ。 聞いたことも見たことも無いよ。」 「あらあら、遊びに来たの?」
俺たちの話し声を聞いたのか、お母さんがお茶とお菓子を持ってきた。 「いや、ちょっと用事が有ったんで来ただけです。」
「まあまあ、香澄も用事が多いからねえ。 これからもよろしくね。」 ペコリと頭を下げたお母さんは店のほうに行ってしまった。
ここからはまた二人きりだ。 なんか緊張するなあ。
「弘明君さあ、何緊張してるの?」 (ギク、気付いてやがる。)
「気付いてるって思ったでしょう?」 「いやいや、その、、、。」
「いいんだよ。 そういう所が私は好きなの。」 「香澄がか?」
「ずーーーーーっと好きなのに気付いてくれないんだよなあ。 意地悪。」 「そんなこと言っても、、、。」
「まあいいや。 高橋先生に振られるまで私は待ってまーす。」 「嫌なやつだなあ。」
「女ですから。」 「気取っても可愛くないぞ。」
「いいもん。 高橋先生より可愛くなってやるんだもん。」 「どうぞどうぞ。 三橋にでも告ってもらえよ。」
「やだやだ。 私は弘明君一択なの。」 「ごちそうさまでした。」
「えーーーーーー? こんな女の子の気持ちを無駄にしないでよ。」 「いつか縁が有ったら考えてやるよ。 じゃあな。」
しばらく香澄と話し込んでから俺は家を出た。 「もうそろそろ帰ってるよなあ?」
そんなことを考えながらバス通りを歩いていく。 行き過ぎるバスを横目で見ながら、、、。
もう5時を過ぎていつもなら母ちゃんも夕食の支度を始める頃だ。 バス通りを歩くのもいいなあ。
駅前通りも少しずつ賑やかになってきてる。 仕事帰りの人たちなのかな?
ブラブラと商店街を歩いて供養塔を見ながら歩いている。 救急車が走り過ぎていった。
やっと家に着いてドアを開けてみると、、、。 まだまだ美和たちの笑い声が聞こえてくる。
「ゲ、、、まだ居るじゃん。」 「おー、お帰り。 美和ちゃんと話さないのか?」
「い、いやいいよ。 用事が有るから。」 「まあ、いいじゃない。 話して行きなさいよ。」
姉ちゃんまでがニコニコしながら俺を誘ってくる。 「お腹も空いたろう? 夕食作るからおいでよ。」
夕食とまで言われたら行かないわけにいかなくなる。 それでも俺は何とかならないものかと思案を巡らせている。
食堂に入ってみると姉ちゃんが美和の隣に俺を座らせた。 (緊張しちまうなあ。)