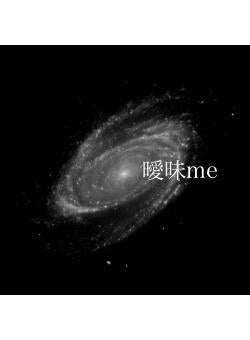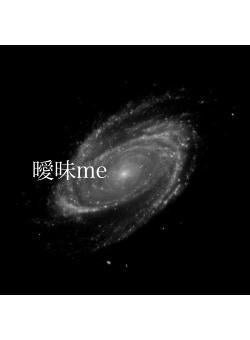キィ、という音の次に、パタンとドアが閉まる。
夏の陽射しに照らされながら、ただ重たい足を運び学校へ向かう。
十五年間過ごしてきても、ずっと代わり映えのない光景。細い道で、緑に囲まれていて、田舎さが滲み出ている。炎天下に響くセミの声が、頭の中まで染み込んできそうだ。
朝から暑くて喉が渇いてきたから、カバンから水筒を取ろうとした。
あれ、ない。足を止めて、教科書を退けて探してみる。それでも、水筒は見当たらなかった。
あ、そうだ。そういえば、家に置きっぱなしだ。
お母さんの一言に苛立ち、そのまま水筒を持たずに家を出てしまったのだ。でも、来た道をわざわざ戻るのもめんどくさいし、戻ったらお母さんにもごちゃごちゃ言われそうだ。
私は家に戻ることなく歩き進み、近くにあった自動販売機で天然水を買った。冷たい水を口に含むと、少しだけ体が冷えた。
この町は田舎で人も車も少ないから、小銭の音や、歩いているときの足音ですらハッキリと響いてくる。今みたいな真夏は、セミたちの厄介な声で埋め尽くされているけど。
こんな町で生きていると、都会に生まれていたらどうなっていたんだろう、という考えが何度も思い浮かんでくる。私は都会に行ったことがない。そもそも、旅行に行ったこともない。