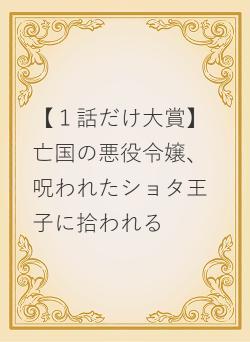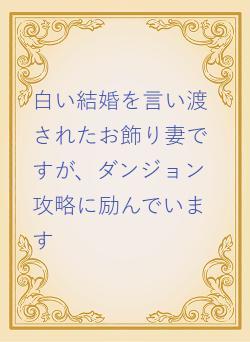「ごめん」
たっぷり10秒ほどの沈黙の後、司はいつものなにを考えているのか読み取りにくい無表情のままそう言った。
「え……」
なんで? と思わず漏らしたつぶやきよりも、無意識に一歩下げた靴のかかとが地面をこするジャリッという音のほうが耳についた。
たぶん、正面に立つ司にもわたしの問いかけが聞こえなかったのだろう。
「でも俺さ……」
「待って!」
足を踏ん張り、なにか言おうとしている翼に向かって手をあげ待ったをかける。
でも、ってなによ?
わたしの一世一代の告白を断った直後に「でも、このまま仲良く幼馴染でいよう」とか言いたいわけ?
冗談じゃない。
「バカ! 聞きたくない!」
いきなり怒り出したわたしの剣幕に司が眉をひそめる。
この表情はたいてい「怒っている」「ムッとしている」と受け取られてしまうんだけど、司がこの顔をした時は「困っている」「戸惑っている」が正解だ。
わたしは司の一番の理解者のつもりでいた。これまでも、これからも――。
感情があまり表に出ない司の気持ちの揺れに気づいたからって、もう何の役にも立たない。
たったいま、わたしは振られたんだから。
鼻の奥がツンと痛んで視界がゆがんできた。
「司なんてもう大っ嫌い!」
泣き顔を見られたくなくて、背中を向けながらそんな捨て台詞を吐いて駆け出した。
中学校の卒業式の前日。
義務教育の終わりとともに、わたしの長い初恋も終わったのだった。
******
我が野瀬家と永山家は仲のいいお隣同士で、わたしと翼は年齢も同じだったため物心つくころには家族同然に司ともいつも一緒にいた。
互いのことを「司」「遥香」と下の名前で呼び合い、同じ幼稚園・小中学校に通った。
クラスは一緒になることもあれば離れ離れになることもあったけれど、登下校はいつも一緒だったし、中学の部活も同じ卓球部だった。
一応、男子卓球部・女子卓球部と別れてはいたけど、練習や試合はいつも一緒だった。
おまけに塾まで同じ。
うちのお母さんはよく、
「司くんが一緒だから塾の帰りが遅くなっても安心だわあ」
と言って笑っていた。
どうしてそんなにいつもべったり一緒にいるのかと聞かれても、それが当たり前だからとしか答えようがなくて、たぶんそれは司も同じだったと思う。
それでも中学校に入学する頃には、わたしは異性として司を意識するようになっていた。
司も同じようにわたしのことを女の子として意識してくれているはずだと思っていたのは、どうやら勘違いだったらしい。
高校受験を終えて、ずっと一緒だったわたしと司がついに離れ離れになってしまう日が近づいていた。
わたしの進学先は自宅から自転車で15分の距離にある公立高校だ。
かたや司の進学先は、電車に乗って1時間かかる毎年T大に何十人も合格者を出す名門男子校。
しかもその特進クラスに合格し学費は全額免除だというのだから、合格の知らせを聞いた時にはわたしもお母さんもまるで自分のことのように大喜びしながら司のを「よく頑張った! おめでとう!」と称えた。
「離れ離れになる前にふたりの関係をはっきりさせておかないと、後悔することになるよ」
「そうだよ、永山くんモテるじゃん。捕まえとかないとヤバいって」
萌絵と綾美にせっつかれるまでもなく、そうしようと思っていた。
司は中学の3年間でぐっと背が伸びて、もともと整っていた顔立ちはすっかり大人びた雰囲気になった。
スポーツは万能というほどではないけれど何でもそつなくこなすし、学力は常に学年トップ。
無口で気が利かないことですら「クール」と、好意的に肯定されている。
そんな司は女子生徒たちの憧れの存在だったようだ。
何度か告白されていたことも知っている。
それを無表情で「興味ないから」「一緒に下校? 遥香と帰るから無理」とバッサリ断っていたことも。
わたしは司の容姿なんてどうでもよかった。
むしろブサイクだったら、ほかの女子たちに見向きもされなかったのにとすら思う。
そしてとうとう卒業式の前日となり、親友ふたりに怖い顔で迫られた。
「遥香、もう崖っぷちだよ。今日告白して明日の卒業式で恋人宣言しておかないと、玉砕覚悟で永山くんに告白する子がいるかもよ」
「体当たりの告白を受けて、永山くん思わず頷いちゃうかもよ!?」
さすがにそれはないだろうと思いつつ、万が一ってこともある……? と一抹の不安が頭をよぎった。
そして、親友にけしかけられたからという言い訳を自分自身にしながら、下校前に司を人影のない体育館の裏へとわざわざ連れて行って告白したのだ。
「わたしたち、これからは幼馴染じゃなくて恋人同士にならない?」って。
その返事がまさか「ごめん」だとは……。
何度思い返しても、いたたまれなくなって死にたくなる。
卒業式の当日の朝も、司は当然のようにわたしを迎えに来たらしい。
前日にわたしのことを振っておきながら、なんて野暮な男なんだろうか。
しかしそれも想定の範囲内だ。朴念仁の司ならやりかねない。
それを見越していつもより早く家を出て正解だった。
司が翌日の卒業式で体当たり告白を受けたのか否かは定かではないし、知りたくもない。
司の本性を知っているのは、わたしだけだ。
クールだと勘違いされているのは表情筋がうまく機能していないだけ。
実は微妙な目の動きや口元の変化で感情が目まぐるしく動いていることに気付けるのは、司の家族以外ではわたししかいない。
司が腹痛を訴えたときのこと。
「ケロッとした顔しているから大丈夫そうね」
そう言って、保健室の先生はただ胃腸薬を飲ませて終わらせようとしていた。
「とっても痛がっているじゃないですか!」
わたしが食ってかかったことで、ようやく病院に連れて行ってもらったところ虫垂炎だった、なんてこともあった。
うちのお母さんは、部活の試合で知らない場所に行くときも塾の帰りが遅くなったときも、司が一緒だから安心と言っていたけど、とんでもない!
司が大の方向音痴である上に、夜道では側溝に落ちたりするものだから、面倒をみてやったのはこっちのほうだ。
あんなに世話を焼いたっていうのに!
日常生活がポンコツな男に甲斐甲斐しく付き添ってやったというのに、ヤツは一体どういうつもりでいたんだろうか。
オカンだとでも思っていたのか。
一緒にいるのが当たり前。世話するのが当たり前。世話されるのが当たり前。
ただそれだけだったのかと思うと、なんだか虚しすぎる。
返せ!
わたしの労力と時間と初恋を!
司のバカヤロ~~~っ!
******
「それで? そのあと永山くんとはどんな感じなの?」
萌絵がスマホをいじる合間に目だけこちらにちらりと向ける。
食べかけのポテトをコーラで喉の奥に流し込み一呼吸置くと、わたしもスマホを取りだして画面のロックを解除しながら答える。
「さあ、知らない。死んだって聞いてないから、生きてるんじゃない?」
「やだ遥香、めっちゃ冷めてるじゃん、ウケる」
萌絵の横で綾美がケラケラ笑った。
卒業式の翌週、わたしは仲の良い萌絵と綾美を誘って駅前のファーストフード店で待ち合わせた。
「ほんとよ、あれだけ司、司って言ってた遥香なのにね」
スマホをテーブルに置いた萌絵が頬杖をついて、くるっとした可愛い瞳にわたしの姿を収めた。
「もう立ち直った?」
「うん。あの時はごめんね。よく考えたら、わざわざ学校で告白なんかしなきゃよかったんだって気づいたよ、家が隣なのにさ」
司がオッケーしてくれたら遠巻きに見守ってくれている友人ふたりに笑顔でピースサインを送ろう――あの時のわたしは、告白が成功することしか考えていなかった。
なんという自信過剰。振られることを想定していなかっただなんて!
自嘲しながら、なんとなくスマホの画面を親指でスクロールしていく。
「けしかけたのはうちらだもん、こっちこそごめん!」
「まさか永山くんが断るなんて思ってなかったよ、ごめんね」
ふたり同時に手を合わせて謝罪してくれて、逆にこっちのほうが申し訳なくなる。
だからわざと明るい声を出した。
「ねえ! 今のわたしのスマホのいじり方、サマになってた!?」
綾美がプッと笑う。
「うん! バッチリ!」
萌絵も少し呆れたように笑った。
「昨日初めてスマホを手に入れた人とは思えないよ」
高校で新しくできるであろう友人たちに、スマホ操作が不慣れだと悟られたくないという、なんともちっぽけな見栄だ。
よっしゃ! と小さくガッツポーツをしておどけてみせると、3人であははっと笑った。
高校生になるにあたり、わたしにはとても楽しみにしていることがあった。
卒業式が終わったらスマホを買ってもらう約束を親としていたことだ。
中学のお友達はもうみんなスマホを持っていると親に何度訴えても、必要ないの一点張りで首を縦に振ってはもらえなかった。
それに「みんな」と言いながら司は持っていないだろうと言われてしまえばその通りで反論できなかったし、塾で帰りが遅くなった時の防犯用にと言っても司と一緒に帰ってくれば問題ないと一蹴された。
こういうとき、うちの両親と翼の両親は結託して足並みをそろえるのだ。
じゃあこちらも子供同士で足並みをそろえて反論……はできなかった。
ふたりで一緒にスマホの必要性を親に訴えようと言うわたしに、司はいつもの飄々とした顔で、
「あったら便利だなって思うことはたまにあるけど、そんなに必要性を感じないから遥香とおんなじ熱量で訴えるのは無理だと思う」
と言いやがったのだ。
SNSのメッセージのやり取りで盛り上がって気づいたら深夜2時だった――萌絵と綾美からそんな話を聞くたびにうらやましさと疎外感で泣きたくなっていたわたしの気持ちなんて、誰も理解も共感もしてくれない。
そうボヤくたびに司は苦笑しながらなぐさめてくれた。
「じゃあ卒業したら、春休みに毎晩俺が深夜まで付き合ってやるから今は我慢しろって」
萌絵と綾美と遊んだ帰り道、ふと司のその言葉と笑顔を思い出した。
「……嘘つき」
夕焼け空が涙で滲んだ。
たっぷり10秒ほどの沈黙の後、司はいつものなにを考えているのか読み取りにくい無表情のままそう言った。
「え……」
なんで? と思わず漏らしたつぶやきよりも、無意識に一歩下げた靴のかかとが地面をこするジャリッという音のほうが耳についた。
たぶん、正面に立つ司にもわたしの問いかけが聞こえなかったのだろう。
「でも俺さ……」
「待って!」
足を踏ん張り、なにか言おうとしている翼に向かって手をあげ待ったをかける。
でも、ってなによ?
わたしの一世一代の告白を断った直後に「でも、このまま仲良く幼馴染でいよう」とか言いたいわけ?
冗談じゃない。
「バカ! 聞きたくない!」
いきなり怒り出したわたしの剣幕に司が眉をひそめる。
この表情はたいてい「怒っている」「ムッとしている」と受け取られてしまうんだけど、司がこの顔をした時は「困っている」「戸惑っている」が正解だ。
わたしは司の一番の理解者のつもりでいた。これまでも、これからも――。
感情があまり表に出ない司の気持ちの揺れに気づいたからって、もう何の役にも立たない。
たったいま、わたしは振られたんだから。
鼻の奥がツンと痛んで視界がゆがんできた。
「司なんてもう大っ嫌い!」
泣き顔を見られたくなくて、背中を向けながらそんな捨て台詞を吐いて駆け出した。
中学校の卒業式の前日。
義務教育の終わりとともに、わたしの長い初恋も終わったのだった。
******
我が野瀬家と永山家は仲のいいお隣同士で、わたしと翼は年齢も同じだったため物心つくころには家族同然に司ともいつも一緒にいた。
互いのことを「司」「遥香」と下の名前で呼び合い、同じ幼稚園・小中学校に通った。
クラスは一緒になることもあれば離れ離れになることもあったけれど、登下校はいつも一緒だったし、中学の部活も同じ卓球部だった。
一応、男子卓球部・女子卓球部と別れてはいたけど、練習や試合はいつも一緒だった。
おまけに塾まで同じ。
うちのお母さんはよく、
「司くんが一緒だから塾の帰りが遅くなっても安心だわあ」
と言って笑っていた。
どうしてそんなにいつもべったり一緒にいるのかと聞かれても、それが当たり前だからとしか答えようがなくて、たぶんそれは司も同じだったと思う。
それでも中学校に入学する頃には、わたしは異性として司を意識するようになっていた。
司も同じようにわたしのことを女の子として意識してくれているはずだと思っていたのは、どうやら勘違いだったらしい。
高校受験を終えて、ずっと一緒だったわたしと司がついに離れ離れになってしまう日が近づいていた。
わたしの進学先は自宅から自転車で15分の距離にある公立高校だ。
かたや司の進学先は、電車に乗って1時間かかる毎年T大に何十人も合格者を出す名門男子校。
しかもその特進クラスに合格し学費は全額免除だというのだから、合格の知らせを聞いた時にはわたしもお母さんもまるで自分のことのように大喜びしながら司のを「よく頑張った! おめでとう!」と称えた。
「離れ離れになる前にふたりの関係をはっきりさせておかないと、後悔することになるよ」
「そうだよ、永山くんモテるじゃん。捕まえとかないとヤバいって」
萌絵と綾美にせっつかれるまでもなく、そうしようと思っていた。
司は中学の3年間でぐっと背が伸びて、もともと整っていた顔立ちはすっかり大人びた雰囲気になった。
スポーツは万能というほどではないけれど何でもそつなくこなすし、学力は常に学年トップ。
無口で気が利かないことですら「クール」と、好意的に肯定されている。
そんな司は女子生徒たちの憧れの存在だったようだ。
何度か告白されていたことも知っている。
それを無表情で「興味ないから」「一緒に下校? 遥香と帰るから無理」とバッサリ断っていたことも。
わたしは司の容姿なんてどうでもよかった。
むしろブサイクだったら、ほかの女子たちに見向きもされなかったのにとすら思う。
そしてとうとう卒業式の前日となり、親友ふたりに怖い顔で迫られた。
「遥香、もう崖っぷちだよ。今日告白して明日の卒業式で恋人宣言しておかないと、玉砕覚悟で永山くんに告白する子がいるかもよ」
「体当たりの告白を受けて、永山くん思わず頷いちゃうかもよ!?」
さすがにそれはないだろうと思いつつ、万が一ってこともある……? と一抹の不安が頭をよぎった。
そして、親友にけしかけられたからという言い訳を自分自身にしながら、下校前に司を人影のない体育館の裏へとわざわざ連れて行って告白したのだ。
「わたしたち、これからは幼馴染じゃなくて恋人同士にならない?」って。
その返事がまさか「ごめん」だとは……。
何度思い返しても、いたたまれなくなって死にたくなる。
卒業式の当日の朝も、司は当然のようにわたしを迎えに来たらしい。
前日にわたしのことを振っておきながら、なんて野暮な男なんだろうか。
しかしそれも想定の範囲内だ。朴念仁の司ならやりかねない。
それを見越していつもより早く家を出て正解だった。
司が翌日の卒業式で体当たり告白を受けたのか否かは定かではないし、知りたくもない。
司の本性を知っているのは、わたしだけだ。
クールだと勘違いされているのは表情筋がうまく機能していないだけ。
実は微妙な目の動きや口元の変化で感情が目まぐるしく動いていることに気付けるのは、司の家族以外ではわたししかいない。
司が腹痛を訴えたときのこと。
「ケロッとした顔しているから大丈夫そうね」
そう言って、保健室の先生はただ胃腸薬を飲ませて終わらせようとしていた。
「とっても痛がっているじゃないですか!」
わたしが食ってかかったことで、ようやく病院に連れて行ってもらったところ虫垂炎だった、なんてこともあった。
うちのお母さんは、部活の試合で知らない場所に行くときも塾の帰りが遅くなったときも、司が一緒だから安心と言っていたけど、とんでもない!
司が大の方向音痴である上に、夜道では側溝に落ちたりするものだから、面倒をみてやったのはこっちのほうだ。
あんなに世話を焼いたっていうのに!
日常生活がポンコツな男に甲斐甲斐しく付き添ってやったというのに、ヤツは一体どういうつもりでいたんだろうか。
オカンだとでも思っていたのか。
一緒にいるのが当たり前。世話するのが当たり前。世話されるのが当たり前。
ただそれだけだったのかと思うと、なんだか虚しすぎる。
返せ!
わたしの労力と時間と初恋を!
司のバカヤロ~~~っ!
******
「それで? そのあと永山くんとはどんな感じなの?」
萌絵がスマホをいじる合間に目だけこちらにちらりと向ける。
食べかけのポテトをコーラで喉の奥に流し込み一呼吸置くと、わたしもスマホを取りだして画面のロックを解除しながら答える。
「さあ、知らない。死んだって聞いてないから、生きてるんじゃない?」
「やだ遥香、めっちゃ冷めてるじゃん、ウケる」
萌絵の横で綾美がケラケラ笑った。
卒業式の翌週、わたしは仲の良い萌絵と綾美を誘って駅前のファーストフード店で待ち合わせた。
「ほんとよ、あれだけ司、司って言ってた遥香なのにね」
スマホをテーブルに置いた萌絵が頬杖をついて、くるっとした可愛い瞳にわたしの姿を収めた。
「もう立ち直った?」
「うん。あの時はごめんね。よく考えたら、わざわざ学校で告白なんかしなきゃよかったんだって気づいたよ、家が隣なのにさ」
司がオッケーしてくれたら遠巻きに見守ってくれている友人ふたりに笑顔でピースサインを送ろう――あの時のわたしは、告白が成功することしか考えていなかった。
なんという自信過剰。振られることを想定していなかっただなんて!
自嘲しながら、なんとなくスマホの画面を親指でスクロールしていく。
「けしかけたのはうちらだもん、こっちこそごめん!」
「まさか永山くんが断るなんて思ってなかったよ、ごめんね」
ふたり同時に手を合わせて謝罪してくれて、逆にこっちのほうが申し訳なくなる。
だからわざと明るい声を出した。
「ねえ! 今のわたしのスマホのいじり方、サマになってた!?」
綾美がプッと笑う。
「うん! バッチリ!」
萌絵も少し呆れたように笑った。
「昨日初めてスマホを手に入れた人とは思えないよ」
高校で新しくできるであろう友人たちに、スマホ操作が不慣れだと悟られたくないという、なんともちっぽけな見栄だ。
よっしゃ! と小さくガッツポーツをしておどけてみせると、3人であははっと笑った。
高校生になるにあたり、わたしにはとても楽しみにしていることがあった。
卒業式が終わったらスマホを買ってもらう約束を親としていたことだ。
中学のお友達はもうみんなスマホを持っていると親に何度訴えても、必要ないの一点張りで首を縦に振ってはもらえなかった。
それに「みんな」と言いながら司は持っていないだろうと言われてしまえばその通りで反論できなかったし、塾で帰りが遅くなった時の防犯用にと言っても司と一緒に帰ってくれば問題ないと一蹴された。
こういうとき、うちの両親と翼の両親は結託して足並みをそろえるのだ。
じゃあこちらも子供同士で足並みをそろえて反論……はできなかった。
ふたりで一緒にスマホの必要性を親に訴えようと言うわたしに、司はいつもの飄々とした顔で、
「あったら便利だなって思うことはたまにあるけど、そんなに必要性を感じないから遥香とおんなじ熱量で訴えるのは無理だと思う」
と言いやがったのだ。
SNSのメッセージのやり取りで盛り上がって気づいたら深夜2時だった――萌絵と綾美からそんな話を聞くたびにうらやましさと疎外感で泣きたくなっていたわたしの気持ちなんて、誰も理解も共感もしてくれない。
そうボヤくたびに司は苦笑しながらなぐさめてくれた。
「じゃあ卒業したら、春休みに毎晩俺が深夜まで付き合ってやるから今は我慢しろって」
萌絵と綾美と遊んだ帰り道、ふと司のその言葉と笑顔を思い出した。
「……嘘つき」
夕焼け空が涙で滲んだ。