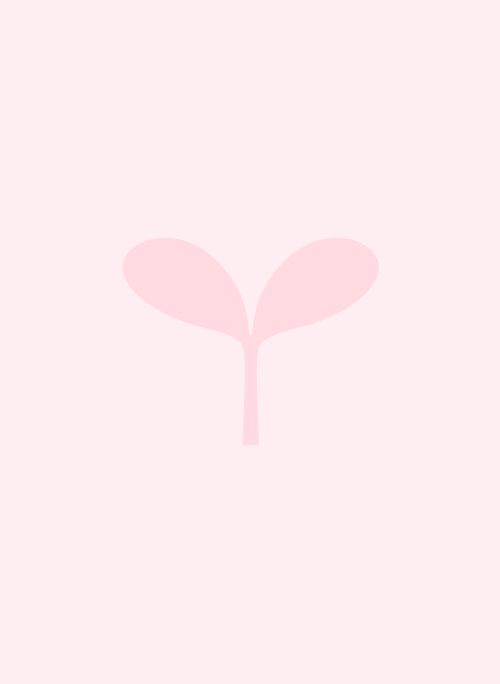「やあやあ、立派になったじゃねぇか、ペィラ。」
工場の端っこに戻ると、相も変わらずヘラヘラしたルベリーが、意味ありげな視線を送ってきた。
「ベリー。ちゃんと起きて仕事しなさいよ。」
「やってるよ。ホラ、手紙のし・わ・け。」
手紙の山の近くに腹ばいになり、両肘をついて仕分けている。
「オイ、あのよぅ新入りー?お前そこいたら・・・」
リン♪リン♪
「うわっ、ぷ・・・アッ!」
バサバサバサッ
手紙が天窓から大量に落下し、部屋の中を雪が舞う。
ペィラは再び小山に押し潰され、ゼイゼイと喘ぎながら顔を出した。
ルベリーはげらげらと転げ回っている。
「学習しねぇなぁ。そこは危ないって言ったろ?」
「分かってるよ、くそっ・・・油断しただけだ。」
大量の手紙を掻き分け、床の上に転がり出ると、忌ま忌ましげに紙と雪の山を見上げた。
「ペィラ、大丈夫?」
「あぁ・・・それにしても、この大量の手紙は一体なんなんだ?」
「それは、・・・子供達から、サンタ達へのお願いよ。」
ペィラはふぅんと鼻を鳴らし、つまんでいた一通を透かし見た。
「知らない?サンタへの手紙の出し方。」
ペィラはさぁ?と肩を竦めると、手紙をヒラリと山の上に落とす。
「手紙を書いて、暖炉の中へ放るの。そうすると、暖炉の精が空高く舞い上げて、北の風に乗せるのよ。やがてそれは雲の上まで立ち昇って、冬の子供達のところまで届くわ。で、彼らがサンタの工場まで届けてくれるの。とっても素敵でしょ?」
メグは楽しそうに話してくれた。
けれど、ペィラのココロには響かなかった。
子供だった頃。
手紙を出したことはなかったし、サンタも来なかった。
クリスマスに、特別な思い入れなんてないのだ。
工場の端っこに戻ると、相も変わらずヘラヘラしたルベリーが、意味ありげな視線を送ってきた。
「ベリー。ちゃんと起きて仕事しなさいよ。」
「やってるよ。ホラ、手紙のし・わ・け。」
手紙の山の近くに腹ばいになり、両肘をついて仕分けている。
「オイ、あのよぅ新入りー?お前そこいたら・・・」
リン♪リン♪
「うわっ、ぷ・・・アッ!」
バサバサバサッ
手紙が天窓から大量に落下し、部屋の中を雪が舞う。
ペィラは再び小山に押し潰され、ゼイゼイと喘ぎながら顔を出した。
ルベリーはげらげらと転げ回っている。
「学習しねぇなぁ。そこは危ないって言ったろ?」
「分かってるよ、くそっ・・・油断しただけだ。」
大量の手紙を掻き分け、床の上に転がり出ると、忌ま忌ましげに紙と雪の山を見上げた。
「ペィラ、大丈夫?」
「あぁ・・・それにしても、この大量の手紙は一体なんなんだ?」
「それは、・・・子供達から、サンタ達へのお願いよ。」
ペィラはふぅんと鼻を鳴らし、つまんでいた一通を透かし見た。
「知らない?サンタへの手紙の出し方。」
ペィラはさぁ?と肩を竦めると、手紙をヒラリと山の上に落とす。
「手紙を書いて、暖炉の中へ放るの。そうすると、暖炉の精が空高く舞い上げて、北の風に乗せるのよ。やがてそれは雲の上まで立ち昇って、冬の子供達のところまで届くわ。で、彼らがサンタの工場まで届けてくれるの。とっても素敵でしょ?」
メグは楽しそうに話してくれた。
けれど、ペィラのココロには響かなかった。
子供だった頃。
手紙を出したことはなかったし、サンタも来なかった。
クリスマスに、特別な思い入れなんてないのだ。