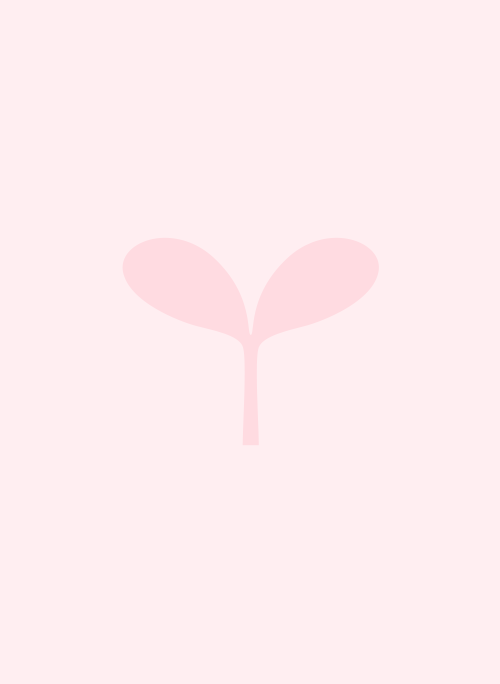ひざまずくペィラに、戸惑いながらメグが声をかける。
「・・・ペィラ。あなたは・・・・」
「メグ。」
老人は彼女をそっと制し、ペィラの傍らに屈んだ。
「君は、地下鉄に跳ねられたんだよ。」
フルフルと震える指先で、破れた書類を繋ぎあわせる。
「ペィラ。この国は、普通の人間には入れない。人を愛し、愛された人間の魂が、自分のなすべきことを求めてやってくるんだ。」
ペィラは破れた書類から離れない。
「君が、ここに来たのは間違いではないんだよ。君の家族の想いが道を開き、君の魂が望んでこの国にたどり着いた。それは使命だからだ。」
ペィラはぴたりと指を止めて、肩を震わせた。
「馬鹿な。」
「うん、何がだね?」
「家族が愛してる?私を?そんなはずはない!・・・私は、私にはどこにも居場所なんかなかった。」
ペィラは苦々しく言葉を噛み潰した。
「・・・・ペィラ。もしも、君がここに来た意味が分かったなら、もう一度ここへおいで。君が本当に欲したそのときに、この扉は再び開くだろう。それまでは、"その"コートで君のなすべきことをするがいい。」
えっ?とペィラが顔を上げた瞬間、温かい暖炉の部屋は消えた。
サンタクロースの格好をした老人も、ロッキンチェアもなく、辺りはほの暗い氷の壁に包まれていた。
「え、え?」
立ち上がったペィラは、もさっとした感触に驚いて転んだ。
「なんだ、こりゃ?」
ふかふかと自分を包むあたたかなコート。
まるで、サンタクロースになったようだ。
一つの相違点を除けば。
「緑・・・?」
「そうよ。」
カツンと蹄が鳴る。
「あなたは・・・愛が欠けた、見習いサンタなの。」
「・・・ペィラ。あなたは・・・・」
「メグ。」
老人は彼女をそっと制し、ペィラの傍らに屈んだ。
「君は、地下鉄に跳ねられたんだよ。」
フルフルと震える指先で、破れた書類を繋ぎあわせる。
「ペィラ。この国は、普通の人間には入れない。人を愛し、愛された人間の魂が、自分のなすべきことを求めてやってくるんだ。」
ペィラは破れた書類から離れない。
「君が、ここに来たのは間違いではないんだよ。君の家族の想いが道を開き、君の魂が望んでこの国にたどり着いた。それは使命だからだ。」
ペィラはぴたりと指を止めて、肩を震わせた。
「馬鹿な。」
「うん、何がだね?」
「家族が愛してる?私を?そんなはずはない!・・・私は、私にはどこにも居場所なんかなかった。」
ペィラは苦々しく言葉を噛み潰した。
「・・・・ペィラ。もしも、君がここに来た意味が分かったなら、もう一度ここへおいで。君が本当に欲したそのときに、この扉は再び開くだろう。それまでは、"その"コートで君のなすべきことをするがいい。」
えっ?とペィラが顔を上げた瞬間、温かい暖炉の部屋は消えた。
サンタクロースの格好をした老人も、ロッキンチェアもなく、辺りはほの暗い氷の壁に包まれていた。
「え、え?」
立ち上がったペィラは、もさっとした感触に驚いて転んだ。
「なんだ、こりゃ?」
ふかふかと自分を包むあたたかなコート。
まるで、サンタクロースになったようだ。
一つの相違点を除けば。
「緑・・・?」
「そうよ。」
カツンと蹄が鳴る。
「あなたは・・・愛が欠けた、見習いサンタなの。」