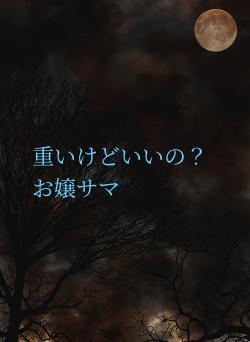「匠はもう教室に居なかった。アイツ気まぐれなとこあんだろ。ガキの頃からそこは変わらねぇんだよ。だからその……あんま気にすんな」
「……うん」
「ま、愁の言う通り。猫みたいなもんだから匠はさ。実際は気にかけてると思うけどね俺は」
二人とも、わたしに気を遣ってくれる。
見た目こそ変わったけど、根が優しいのは子供の頃のまま──かな。
ほとんどが帰ったあとの校舎を出て、今朝三人と会った校門のとこに出る。
「……ほーらね」
「え?あ……」
壁に寄りかかりながら、ヘッドフォンをしているたーちゃんの姿があって、いっちゃんはわたしの肩を叩いて教えてくれた。
わたしたちに気付いたたーちゃんは、ヘッドフォンを首にかけ、眉を歪めてこちらに歩いてくる。
「おそい。こんなおそいとか聞いてないんだけど」
「お前がこいつにめんどくさいとか言うからだろうが」
「そうだっけ?」
「は?お前ふざけてんのか?」