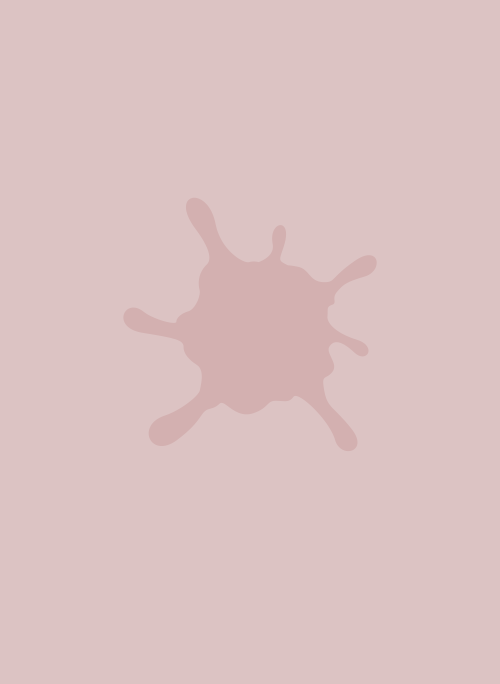度を越した扱きは、先輩からだけに限られなかった。
つまり、先輩以外からも扱きを受けていたという訳だ。
誰かと言うと、それは教官だった。
俺を指導した教官は、異常なほど俺に厳しかった。
他の生徒とは、明らかに指導方法が異なっていた。
俺にだけ指導が極端に厳しいことは、誰の目から見ても明かだった。
事ある毎に家の名前、姉の名前を出され、散々に扱き下ろされた。
それは露骨で、陰湿なほどだった。
騎士官学校の教官は元々スパルタなことで有名だが、それにしたって酷かった。
明らかに俺にだけ課される課題は多かったし、きついものだった。
求められるレベルも、他の生徒より明らかに高かった。
そして叱責するときの言葉も、俺に対してだけ、人格を否定するようなものばかりだった。
何故そこまで言われなければならないのだと、理不尽に思った。
しかし、言い返すことは出来なかった。
生徒にとって教官は、比喩ではなく神にも等しい存在だったから。
教官に口答えするなんて、先輩に口答えするのと同じくらい有り得なかった。
何を言われようと、ぐっと我慢するしかなかった。
けれど腹の中では、理不尽に対する怒りに燃えていた。
あの頃はまだ、怒りを覚えるだけの気力があった。
この野郎、と思えている頃はまだ…幸せだった。
それにしても何故あの教官は俺を目の敵にしたのか。何がしたかったのか後になつて聞いたところによると、あいつは俺を潰したかったらしい。
名家の生まれで、将来を約束された俺が妬ましかったんだと。
実に下らない。そんな理由で、俺はあれほどの苦しみを与えられたのか。
なんとも理不尽なことだ。
何より腹が立つのは、そんなゲス野郎の目論見通りに、潰れてしまった自分である。
あれほどの苦痛だったのだから、潰れるのもやむを得ないとは思うが。やはり悔しい。
同級生達も、俺に対する扱きが度を越していると分かっていても、教官に意見をするなんて畏れ多いことは出来ないから、彼らも見て見ぬ振りだった。
あいつらは知っていたはずだ。俺が教官に度を越した扱きをされていたこと。学生寮でルームメイトにいじめられていたことも。
皆、知っていた。それは確かなのだ。
でも、俺を助けようとする者は一人もいなかった。
教官にも先輩にも逆らえない立場だからそれは仕方のないことなのかもしれない。下手なことをすれば目をつけられるのは自分なのだと思うと、良心が二の足を踏んでしまうのは仕方ない。
それは理解する。
けれど彼らは、見て見ぬ振りをした。
俺をいない者扱いして、同情するどころか、慰めるどころか、励ますどころか。
俺を集団無視して、完全に一人孤立させた。
俺にとって一番辛いのはそれだった。
考えてみて欲しい。周りに多くの人間がいるのに、無視されるのは辛い。
予想以上に、集団無視は堪える。
殴られるのも怒鳴られるのも嫌だったけど、無視されるのも同じくらい嫌だった。
そんな訳で、俺は四面楚歌だった。
そして孤立無援だった。
…彼が、来るまでは。
つまり、先輩以外からも扱きを受けていたという訳だ。
誰かと言うと、それは教官だった。
俺を指導した教官は、異常なほど俺に厳しかった。
他の生徒とは、明らかに指導方法が異なっていた。
俺にだけ指導が極端に厳しいことは、誰の目から見ても明かだった。
事ある毎に家の名前、姉の名前を出され、散々に扱き下ろされた。
それは露骨で、陰湿なほどだった。
騎士官学校の教官は元々スパルタなことで有名だが、それにしたって酷かった。
明らかに俺にだけ課される課題は多かったし、きついものだった。
求められるレベルも、他の生徒より明らかに高かった。
そして叱責するときの言葉も、俺に対してだけ、人格を否定するようなものばかりだった。
何故そこまで言われなければならないのだと、理不尽に思った。
しかし、言い返すことは出来なかった。
生徒にとって教官は、比喩ではなく神にも等しい存在だったから。
教官に口答えするなんて、先輩に口答えするのと同じくらい有り得なかった。
何を言われようと、ぐっと我慢するしかなかった。
けれど腹の中では、理不尽に対する怒りに燃えていた。
あの頃はまだ、怒りを覚えるだけの気力があった。
この野郎、と思えている頃はまだ…幸せだった。
それにしても何故あの教官は俺を目の敵にしたのか。何がしたかったのか後になつて聞いたところによると、あいつは俺を潰したかったらしい。
名家の生まれで、将来を約束された俺が妬ましかったんだと。
実に下らない。そんな理由で、俺はあれほどの苦しみを与えられたのか。
なんとも理不尽なことだ。
何より腹が立つのは、そんなゲス野郎の目論見通りに、潰れてしまった自分である。
あれほどの苦痛だったのだから、潰れるのもやむを得ないとは思うが。やはり悔しい。
同級生達も、俺に対する扱きが度を越していると分かっていても、教官に意見をするなんて畏れ多いことは出来ないから、彼らも見て見ぬ振りだった。
あいつらは知っていたはずだ。俺が教官に度を越した扱きをされていたこと。学生寮でルームメイトにいじめられていたことも。
皆、知っていた。それは確かなのだ。
でも、俺を助けようとする者は一人もいなかった。
教官にも先輩にも逆らえない立場だからそれは仕方のないことなのかもしれない。下手なことをすれば目をつけられるのは自分なのだと思うと、良心が二の足を踏んでしまうのは仕方ない。
それは理解する。
けれど彼らは、見て見ぬ振りをした。
俺をいない者扱いして、同情するどころか、慰めるどころか、励ますどころか。
俺を集団無視して、完全に一人孤立させた。
俺にとって一番辛いのはそれだった。
考えてみて欲しい。周りに多くの人間がいるのに、無視されるのは辛い。
予想以上に、集団無視は堪える。
殴られるのも怒鳴られるのも嫌だったけど、無視されるのも同じくらい嫌だった。
そんな訳で、俺は四面楚歌だった。
そして孤立無援だった。
…彼が、来るまでは。