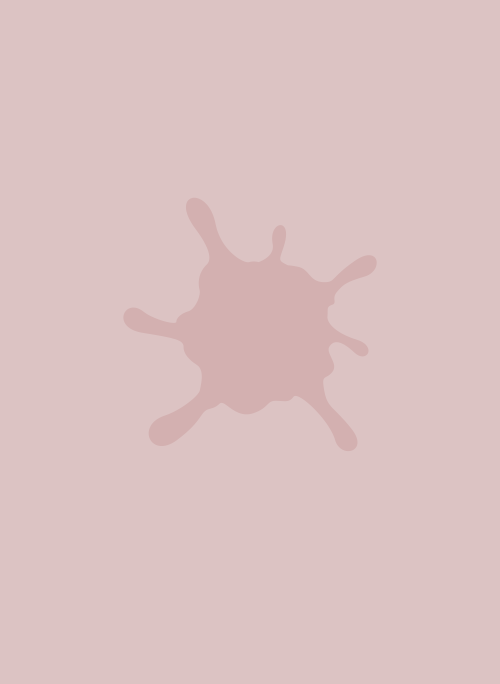ルームメイト五人全員が、俺へのいじめの首謀者だったけれど。
その役割は、全員同じではなかった。
暴力が好きなのはシューレン。でも、ろくでもないことを閃くのは、そのシューレンの親友である、ベリエス・エル・シュレーゲルだった。
こいつが余計なことを思い付き、シューレンが同調して、実行するのはその他の取り巻きの三人。
大抵が、そういう構図だった。
上下関係が厳しい社会では、少なからず先輩から後輩へのいびりはあるだろう。
恐らくどの部屋でも、大なり小なりそういうことはあったはずだ。
後輩は先輩に気を遣い、時には先輩からの理不尽ないびりにも、歯を食い縛って我慢することはあっただろう。
その点は理解する。こんな閉鎖された封建制の生活では、どうしても先輩からの扱きはある。
だから、ある程度は許容するつもりだった。
しかも俺は、ウィスタリアの名を背負っていた。
学園の中では、その名前を知らない者はいなかった。
姉はその頃には既に帝国騎士団二番隊の隊長に就任していたし、俺は余計人気者だった。
悪い意味の方で、だ。
家の名前。姉の名前。そして、なまじ才能のあった俺。
やっかまれない訳がなかった。僻まれない訳がなかった。
同輩の人間よりは、いびられるだろうなとは思っていた。姉も騎士官学校出だが、在学中はその類稀な才能の為に、嫌な目を見たことがあるらしい。
けれど、俺ほどではないのは確かだった。
少なくとも姉は、俺のように空虚な目はしていなかった。
覚悟はしていた。
けれど、これほどとは思わなかった。
いびりは、予想以上に酷いものだった。それは日に日にエスカレートしていき、耐え難いものになっていた。
あの部屋で、俺には人権なんてなかった。
本物の、サンドバッグだった。
いびりなんてものじゃない。あれは最早、集団リンチだ。
身の毛もよだつような、ありとあらゆるおぞましい方法でいじめられた。
希望に満ち溢れていたはずの俺は、段々…精神をやられていった。
元々、ストレスには慣れているつもりだった。幼い頃から厳しい家庭教師に指導されていたから。
実際、あの学生寮がなければ、俺はなんとか耐えられただろう。
けれど、無理だった。
俺はとても、あのいじめに耐えられなかった。
何故なら俺の苦痛は、学生寮のみに限られなかったからである。
その役割は、全員同じではなかった。
暴力が好きなのはシューレン。でも、ろくでもないことを閃くのは、そのシューレンの親友である、ベリエス・エル・シュレーゲルだった。
こいつが余計なことを思い付き、シューレンが同調して、実行するのはその他の取り巻きの三人。
大抵が、そういう構図だった。
上下関係が厳しい社会では、少なからず先輩から後輩へのいびりはあるだろう。
恐らくどの部屋でも、大なり小なりそういうことはあったはずだ。
後輩は先輩に気を遣い、時には先輩からの理不尽ないびりにも、歯を食い縛って我慢することはあっただろう。
その点は理解する。こんな閉鎖された封建制の生活では、どうしても先輩からの扱きはある。
だから、ある程度は許容するつもりだった。
しかも俺は、ウィスタリアの名を背負っていた。
学園の中では、その名前を知らない者はいなかった。
姉はその頃には既に帝国騎士団二番隊の隊長に就任していたし、俺は余計人気者だった。
悪い意味の方で、だ。
家の名前。姉の名前。そして、なまじ才能のあった俺。
やっかまれない訳がなかった。僻まれない訳がなかった。
同輩の人間よりは、いびられるだろうなとは思っていた。姉も騎士官学校出だが、在学中はその類稀な才能の為に、嫌な目を見たことがあるらしい。
けれど、俺ほどではないのは確かだった。
少なくとも姉は、俺のように空虚な目はしていなかった。
覚悟はしていた。
けれど、これほどとは思わなかった。
いびりは、予想以上に酷いものだった。それは日に日にエスカレートしていき、耐え難いものになっていた。
あの部屋で、俺には人権なんてなかった。
本物の、サンドバッグだった。
いびりなんてものじゃない。あれは最早、集団リンチだ。
身の毛もよだつような、ありとあらゆるおぞましい方法でいじめられた。
希望に満ち溢れていたはずの俺は、段々…精神をやられていった。
元々、ストレスには慣れているつもりだった。幼い頃から厳しい家庭教師に指導されていたから。
実際、あの学生寮がなければ、俺はなんとか耐えられただろう。
けれど、無理だった。
俺はとても、あのいじめに耐えられなかった。
何故なら俺の苦痛は、学生寮のみに限られなかったからである。