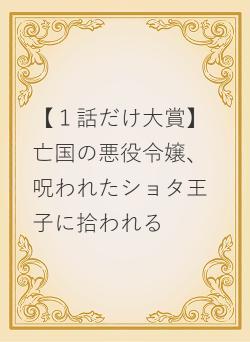目を覚ました時、自分がどこに寝ているのかわからなかった。
頭がまだボーっとしていたこともあるが、視界が塞がれて何も見えない。
瞼がわずかしか開かない。
首を左右に動かして手足ももぞもぞと動かして、体が無事であることを確認すると勢いよく上半身を起こした。
「うわっ!」
横から男性の驚いたような声が聞こえる。
「ヴィー! 大丈夫か!?」
ああ、この声は――。
「ロイさん?」
言った途端にぎゅうっと抱きしめられた。
「ああそうだ。俺だよ、ヴィー」
わたし、もしかしたら死んだのかしら。
こんなに都合よくロイさんに再会できるなんてこと、ある?
「あのね、目が見えないの」
そう訴えると、瞼に指が触れる。
革の手袋をはめているようだ。ロイさんはいつもそうだった。
「目にゼリーが張り付いて固まってるんだな。待ってろ、今すぐガーゼを……」
「待って!」
離れて行こうとするロイさんの腕を掴んで引き留めた。
ここで離れたらもう次はない気がしたからだ。
「行かないで、ロイさん」
手探りで手を伸ばし、今度はわたしのほうからぎゅうっと抱き着いた。
「ロイさん、わたし最後はひとりでボススライムと戦ったのよ」
「ああ、聞いた」
「大地の亀裂っていう大技を使ったの。本当はラスボス用に取っておいた必殺技だったのに」
「そうか。頑張ったな」
ロイさんが優しく頭をなでてくれる。
「ロイさん、わたし結婚したの」
「……知ってたよ」
やや間があったのは、わたしが人妻だと知って驚いたからだろうか。
「これは内緒だけど、もう最後かもしれないから言いますね。わたし、ロイさんのことが好きだったのよ」
「ああ、それも知ってた」
そうよね、ロイさん本人だってわたしの恋心に気付いてたわよね。
なぜ突然冒険者を辞めてしまったのかと聞く前にロイさんのほうから質問された。
「ヴィーの夫は、どんな男なんだ?」
「かっこいい人です」
「ほかには?」
「かっこよくてクズです」
「……ほかには?」
「とてもかっこよくて、とてもク……」
「もういい」
途中で止められた。
声色から察するに、なぜか怒らせてしまったようだ。
「ヴィー、お湯とガーゼを持ってくるから待っていてくれ」
額に触れた柔らかい感触はもしや唇だろうか。
そう考えているうちにロイさんの温もりが離れていく。
「待って! まだ話したいことが……」
「すぐに戻るから」
ドアの開閉音が聞こえて、伸ばした手を下ろした。
ロイさんがまたわたしを置いて行ってしまった。
こんなにも短い再会だとわかっていたら、もっと他に話したいことがたくさんあったのに。
そう思うとどっと疲れが出て、深いため息をつきながら体を横たえる。
心地よい寝具に包まれると、わたしは再び眠りに落ちていったのだった。
頭がまだボーっとしていたこともあるが、視界が塞がれて何も見えない。
瞼がわずかしか開かない。
首を左右に動かして手足ももぞもぞと動かして、体が無事であることを確認すると勢いよく上半身を起こした。
「うわっ!」
横から男性の驚いたような声が聞こえる。
「ヴィー! 大丈夫か!?」
ああ、この声は――。
「ロイさん?」
言った途端にぎゅうっと抱きしめられた。
「ああそうだ。俺だよ、ヴィー」
わたし、もしかしたら死んだのかしら。
こんなに都合よくロイさんに再会できるなんてこと、ある?
「あのね、目が見えないの」
そう訴えると、瞼に指が触れる。
革の手袋をはめているようだ。ロイさんはいつもそうだった。
「目にゼリーが張り付いて固まってるんだな。待ってろ、今すぐガーゼを……」
「待って!」
離れて行こうとするロイさんの腕を掴んで引き留めた。
ここで離れたらもう次はない気がしたからだ。
「行かないで、ロイさん」
手探りで手を伸ばし、今度はわたしのほうからぎゅうっと抱き着いた。
「ロイさん、わたし最後はひとりでボススライムと戦ったのよ」
「ああ、聞いた」
「大地の亀裂っていう大技を使ったの。本当はラスボス用に取っておいた必殺技だったのに」
「そうか。頑張ったな」
ロイさんが優しく頭をなでてくれる。
「ロイさん、わたし結婚したの」
「……知ってたよ」
やや間があったのは、わたしが人妻だと知って驚いたからだろうか。
「これは内緒だけど、もう最後かもしれないから言いますね。わたし、ロイさんのことが好きだったのよ」
「ああ、それも知ってた」
そうよね、ロイさん本人だってわたしの恋心に気付いてたわよね。
なぜ突然冒険者を辞めてしまったのかと聞く前にロイさんのほうから質問された。
「ヴィーの夫は、どんな男なんだ?」
「かっこいい人です」
「ほかには?」
「かっこよくてクズです」
「……ほかには?」
「とてもかっこよくて、とてもク……」
「もういい」
途中で止められた。
声色から察するに、なぜか怒らせてしまったようだ。
「ヴィー、お湯とガーゼを持ってくるから待っていてくれ」
額に触れた柔らかい感触はもしや唇だろうか。
そう考えているうちにロイさんの温もりが離れていく。
「待って! まだ話したいことが……」
「すぐに戻るから」
ドアの開閉音が聞こえて、伸ばした手を下ろした。
ロイさんがまたわたしを置いて行ってしまった。
こんなにも短い再会だとわかっていたら、もっと他に話したいことがたくさんあったのに。
そう思うとどっと疲れが出て、深いため息をつきながら体を横たえる。
心地よい寝具に包まれると、わたしは再び眠りに落ちていったのだった。