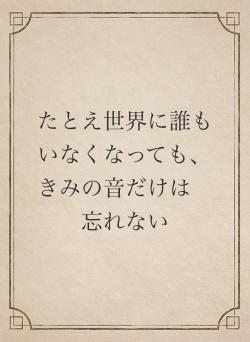お気に入りの島で、ふたりでのんびりと過ごしていたら、不意にイーヴがぴくりと肩を震わせて空を見上げた。
「……雨が、降るな」
「雨? こんなに晴れてるのに」
つられて見上げた空は明るく、雨の気配はない。まさかとつぶやいたシェイラを見て、イーヴは首を横に振った。
「少し冷たい風が吹いてきただろう。こういう時は、急な雨になることが多い」
降り出す前に帰ろうと言って、イーヴは手早く荷物をまとめ始めた。
もう少しゆっくりしていたかった気持ちはあるものの、雨に濡れるのはシェイラも避けたい。早めに帰って、部屋でイーヴと過ごすのも悪くないだろう。
読んでいた本をぱたんと閉じて、シェイラもバスケットに荷物を詰めていく。
「雨雲が近づいてきたな」
イーヴの声に顔を上げると、さっきまであんなに晴れていた西の方の空が真っ黒になっていた。
「わぁ、本当。こんなに急に天気が変わるなんて」
「急ごう」
シェイラはうなずくと、竜に姿を変えたイーヴの背に飛び乗った。
雨雲に追いかけられるような形でドレージアを目指していたのだが、帰りつく前に雨が降り出した。
まるでシャワーを浴びているかのような激しい雨に、シェイラは思わず悲鳴をあげる。打ちつける雨のせいで、目を開けていられない。
「しっかり掴まってろ」
「うん」
ぎゅうっとイーヴのたてがみにしがみつくと、彼が更にスピードを上げた。
ようやく屋敷の庭に帰り着いた頃には、全身びしょ濡れになってしまった。
ぽたぽたと雫を滴らせながら、シェイラはイーヴの背から下りる。濡れて重さを増した服が、身体に纏わりついて不快だ。
「大丈夫か、シェイラ。すぐにエルフェを呼んで入浴を……」
人の姿に戻ったイーヴは、シェイラを見た瞬間に目を見開いて固まってしまった。その頬は、いつもより赤く見える。
「? どうしたんですか、イーヴ」
「……っシェイラ。その格好は、だめだ」
「え?」
どういうことかと自らの服を見下ろしたシェイラは、一気に真っ赤になった。
濡れて肌に貼りついた服はシェイラの身体のラインをくっきりと際立たせている。薄手の素材だったこともあり、胸元や太腿の肌が透けて見えるのが何だかいやらしい。
「だ、だって、雨に濡れて……!」
自分の身体を抱きしめるようにしながら、シェイラは小さく叫ぶ。まさか雨に降られるなんて思いもしなかったし、わざとこんな格好をしているわけではないのだ。
「分かってる。でもこんな姿は、たとえエルフェにだって見せられない」
そう言ってイーヴはシャツを脱ぐとシェイラに着せ、そのまま抱き上げた。彼のシャツも濡れているけれど、羽織ったことでシェイラの露出は減った。
だけど、そうなればイーヴは上半身裸で、しかも抱き上げられているシェイラは彼の肌のぬくもりをしっかりと感じ取ってしまう。
雨に濡れて身体は冷えているはずなのに、頬が熱くてたまらない。
イーヴの肌が目に入ることも落ち着かなくて、シェイラはじっとうつむいていることしかできなかった。
大股で廊下を歩くイーヴは、どうやら浴室を目指しているようだ。お互いの肌が触れ合っている部分はあたたかいけれど、水に濡れた服はどんどん体温を奪っていく。寒気を感じて小さく身体を震わせたら、抱きしめる腕の力が強くなった。
「お湯を張るまで待つと風邪をひくだろうから、先に熱いシャワーを浴びるといい」
浴室の入口で、イーヴはシェイラを下ろすとそんなことを言った。そのまま出て行こうとするイーヴの腕を、シェイラは思わず掴む。
「イーヴは?」
「え?」
「だって、イーヴも冷えてるでしょう。だから一緒に」
「……シェイラ、その意味を分かって言ってるのか?」
うかがうような視線を向けられて、シェイラは黙ってうなずいた。何度も身体は重ねているけれど、一緒に入浴したことはない。恥ずかしい気持ちはあるけれど、それよりイーヴをこのままにはしておけない。
「風邪ひいたら、困るから。だからイーヴも一緒に」
とんでもなく大胆なことを言っている自覚はあるので、顔が上げられない。下を向いたままもう一度そう言うと、がしがしと頭を掻いたイーヴが大きく息を吐くとシェイラを抱き寄せた。
「ただでさえ、シェイラのそんな姿見せられて余裕をなくしてるんだ。そこにきて、このお誘い……。身体をあたためるだけじゃ済まなくなるんだが」
「構わないわ」
「その言葉に嘘はないな?」
くすりと笑ったイーヴがシェイラの額にそっと口づける。その優しいぬくもりにうなずくと、ふわりと抱き上げられた。
イーヴは迷いのない足どりで浴室内に入ると、壁に取り付けられたシャワーに手を伸ばした。あたたかなお湯がふたりの身体に柔らかく降り注ぎ、湯気であたりが一気に白くなった。
「待って、イーヴ、服……着たままっ」
「どうせ濡れてるんだし、このままでいい。シェイラのその格好を、もう少し堪能したいしな」
悪戯っぽく告げられた言葉に、シェイラの頬は更に熱くなった。
結局シェイラは、シャワーを浴びながらイーヴに散々愛されることになった。
最終的に気が遠くなってぐったりとしてしまったのは、熱いお湯にのぼせたのではなく、イーヴがあれこれしたせいだ。
調子に乗りすぎたと平謝りするイーヴに、それなら流行りのお菓子が食べたいと、シェイラはちゃっかりリクエストしておいた。
色とりどりでまるで宝石のような見た目の砂糖菓子は、その可愛さと美味しさでとても人気なのだとルベリアに教えてもらったのだ。
お店はいつも行列だと聞いたけど、イーヴは何時間並んででも買ってくると約束してくれた。
倒れたシェイラを心配して、イーヴは屋敷の面々にこってり絞られた。だけど、実際のところシェイラもしっかりイーヴを受け入れていたので、彼ばかりが悪いわけではない。
シャワーを浴びて髪から水を滴らせるイーヴの姿はいつも以上に艶めいて見えたし、ほんのり湯気の舞う浴室内で愛しあうこともなんだかドキドキした。
たまにはこういうのも悪くないと、シェイラは密かにそんなことを思って小さく笑った。
「……雨が、降るな」
「雨? こんなに晴れてるのに」
つられて見上げた空は明るく、雨の気配はない。まさかとつぶやいたシェイラを見て、イーヴは首を横に振った。
「少し冷たい風が吹いてきただろう。こういう時は、急な雨になることが多い」
降り出す前に帰ろうと言って、イーヴは手早く荷物をまとめ始めた。
もう少しゆっくりしていたかった気持ちはあるものの、雨に濡れるのはシェイラも避けたい。早めに帰って、部屋でイーヴと過ごすのも悪くないだろう。
読んでいた本をぱたんと閉じて、シェイラもバスケットに荷物を詰めていく。
「雨雲が近づいてきたな」
イーヴの声に顔を上げると、さっきまであんなに晴れていた西の方の空が真っ黒になっていた。
「わぁ、本当。こんなに急に天気が変わるなんて」
「急ごう」
シェイラはうなずくと、竜に姿を変えたイーヴの背に飛び乗った。
雨雲に追いかけられるような形でドレージアを目指していたのだが、帰りつく前に雨が降り出した。
まるでシャワーを浴びているかのような激しい雨に、シェイラは思わず悲鳴をあげる。打ちつける雨のせいで、目を開けていられない。
「しっかり掴まってろ」
「うん」
ぎゅうっとイーヴのたてがみにしがみつくと、彼が更にスピードを上げた。
ようやく屋敷の庭に帰り着いた頃には、全身びしょ濡れになってしまった。
ぽたぽたと雫を滴らせながら、シェイラはイーヴの背から下りる。濡れて重さを増した服が、身体に纏わりついて不快だ。
「大丈夫か、シェイラ。すぐにエルフェを呼んで入浴を……」
人の姿に戻ったイーヴは、シェイラを見た瞬間に目を見開いて固まってしまった。その頬は、いつもより赤く見える。
「? どうしたんですか、イーヴ」
「……っシェイラ。その格好は、だめだ」
「え?」
どういうことかと自らの服を見下ろしたシェイラは、一気に真っ赤になった。
濡れて肌に貼りついた服はシェイラの身体のラインをくっきりと際立たせている。薄手の素材だったこともあり、胸元や太腿の肌が透けて見えるのが何だかいやらしい。
「だ、だって、雨に濡れて……!」
自分の身体を抱きしめるようにしながら、シェイラは小さく叫ぶ。まさか雨に降られるなんて思いもしなかったし、わざとこんな格好をしているわけではないのだ。
「分かってる。でもこんな姿は、たとえエルフェにだって見せられない」
そう言ってイーヴはシャツを脱ぐとシェイラに着せ、そのまま抱き上げた。彼のシャツも濡れているけれど、羽織ったことでシェイラの露出は減った。
だけど、そうなればイーヴは上半身裸で、しかも抱き上げられているシェイラは彼の肌のぬくもりをしっかりと感じ取ってしまう。
雨に濡れて身体は冷えているはずなのに、頬が熱くてたまらない。
イーヴの肌が目に入ることも落ち着かなくて、シェイラはじっとうつむいていることしかできなかった。
大股で廊下を歩くイーヴは、どうやら浴室を目指しているようだ。お互いの肌が触れ合っている部分はあたたかいけれど、水に濡れた服はどんどん体温を奪っていく。寒気を感じて小さく身体を震わせたら、抱きしめる腕の力が強くなった。
「お湯を張るまで待つと風邪をひくだろうから、先に熱いシャワーを浴びるといい」
浴室の入口で、イーヴはシェイラを下ろすとそんなことを言った。そのまま出て行こうとするイーヴの腕を、シェイラは思わず掴む。
「イーヴは?」
「え?」
「だって、イーヴも冷えてるでしょう。だから一緒に」
「……シェイラ、その意味を分かって言ってるのか?」
うかがうような視線を向けられて、シェイラは黙ってうなずいた。何度も身体は重ねているけれど、一緒に入浴したことはない。恥ずかしい気持ちはあるけれど、それよりイーヴをこのままにはしておけない。
「風邪ひいたら、困るから。だからイーヴも一緒に」
とんでもなく大胆なことを言っている自覚はあるので、顔が上げられない。下を向いたままもう一度そう言うと、がしがしと頭を掻いたイーヴが大きく息を吐くとシェイラを抱き寄せた。
「ただでさえ、シェイラのそんな姿見せられて余裕をなくしてるんだ。そこにきて、このお誘い……。身体をあたためるだけじゃ済まなくなるんだが」
「構わないわ」
「その言葉に嘘はないな?」
くすりと笑ったイーヴがシェイラの額にそっと口づける。その優しいぬくもりにうなずくと、ふわりと抱き上げられた。
イーヴは迷いのない足どりで浴室内に入ると、壁に取り付けられたシャワーに手を伸ばした。あたたかなお湯がふたりの身体に柔らかく降り注ぎ、湯気であたりが一気に白くなった。
「待って、イーヴ、服……着たままっ」
「どうせ濡れてるんだし、このままでいい。シェイラのその格好を、もう少し堪能したいしな」
悪戯っぽく告げられた言葉に、シェイラの頬は更に熱くなった。
結局シェイラは、シャワーを浴びながらイーヴに散々愛されることになった。
最終的に気が遠くなってぐったりとしてしまったのは、熱いお湯にのぼせたのではなく、イーヴがあれこれしたせいだ。
調子に乗りすぎたと平謝りするイーヴに、それなら流行りのお菓子が食べたいと、シェイラはちゃっかりリクエストしておいた。
色とりどりでまるで宝石のような見た目の砂糖菓子は、その可愛さと美味しさでとても人気なのだとルベリアに教えてもらったのだ。
お店はいつも行列だと聞いたけど、イーヴは何時間並んででも買ってくると約束してくれた。
倒れたシェイラを心配して、イーヴは屋敷の面々にこってり絞られた。だけど、実際のところシェイラもしっかりイーヴを受け入れていたので、彼ばかりが悪いわけではない。
シャワーを浴びて髪から水を滴らせるイーヴの姿はいつも以上に艶めいて見えたし、ほんのり湯気の舞う浴室内で愛しあうこともなんだかドキドキした。
たまにはこういうのも悪くないと、シェイラは密かにそんなことを思って小さく笑った。