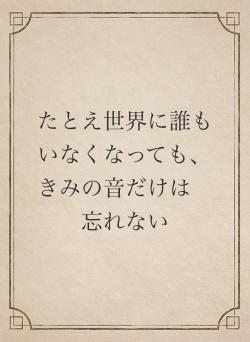疲れていたシェイラは、イーヴの腕の中でそのまま眠りに落ちた。
夢うつつに、彼が小さく笑ってベッドまで運んでくれたこと、そして額に柔らかなキスをもらったことだけ、覚えている。
次に目を覚ましたら、昼だった。窓の外の太陽は随分高い位置にあり、明るい日差しが窓辺を照らしている。
広いベッドの上にはシェイラ一人で、イーヴの姿は部屋の中にもない。そのことに少し寂しくなりながらよろよろと起き上がると、シェイラは着替えのために立ち上がった。
浴室の鏡を見つめて、シェイラは眉を顰めた。傷ひとつない白い首筋にばかり、視線を向けてしまうのだ。
番いの証のことなんて、聞いたこともなかった。きっとイーヴは、それを人間であるシェイラに教えるつもりはなかったのだろう。
いつかシェイラが寿命を迎えたら、イーヴは竜族の誰かと結ばれる。その人に、彼はきっと番いの証を贈るはずだ。
自分の寿命が尽きるまでの間だけでいいからイーヴにはこちらを見ていてほしいと願い、それは確かに叶ったのに、自分が死んだあとですらもイーヴの心を縛りつけておきたいと思ってしまう。彼の唯一の伴侶になりたいと、願ってしまう。
イーヴに関しては、どこまでも欲深くなってしまうなとシェイラはため息をついた。
部屋に戻ったシェイラは、テーブルの上にイーヴの手紙が置いてあることに気づいた。
軽食を用意しているので、目覚めたらエルフェに声をかけること、食事をとったらまたベッドで身体を休めるよう書かれている。
少し右肩上がりのその文字を指先でなぞって、シェイラはメモを抱きしめた。イーヴの本心や未来のことは分からないし、番いにはなれないけれど、彼はこんなにもシェイラのことを大切にしてくれている。これ以上を望むのは、きっと贅沢すぎるのだ。
夢うつつに、彼が小さく笑ってベッドまで運んでくれたこと、そして額に柔らかなキスをもらったことだけ、覚えている。
次に目を覚ましたら、昼だった。窓の外の太陽は随分高い位置にあり、明るい日差しが窓辺を照らしている。
広いベッドの上にはシェイラ一人で、イーヴの姿は部屋の中にもない。そのことに少し寂しくなりながらよろよろと起き上がると、シェイラは着替えのために立ち上がった。
浴室の鏡を見つめて、シェイラは眉を顰めた。傷ひとつない白い首筋にばかり、視線を向けてしまうのだ。
番いの証のことなんて、聞いたこともなかった。きっとイーヴは、それを人間であるシェイラに教えるつもりはなかったのだろう。
いつかシェイラが寿命を迎えたら、イーヴは竜族の誰かと結ばれる。その人に、彼はきっと番いの証を贈るはずだ。
自分の寿命が尽きるまでの間だけでいいからイーヴにはこちらを見ていてほしいと願い、それは確かに叶ったのに、自分が死んだあとですらもイーヴの心を縛りつけておきたいと思ってしまう。彼の唯一の伴侶になりたいと、願ってしまう。
イーヴに関しては、どこまでも欲深くなってしまうなとシェイラはため息をついた。
部屋に戻ったシェイラは、テーブルの上にイーヴの手紙が置いてあることに気づいた。
軽食を用意しているので、目覚めたらエルフェに声をかけること、食事をとったらまたベッドで身体を休めるよう書かれている。
少し右肩上がりのその文字を指先でなぞって、シェイラはメモを抱きしめた。イーヴの本心や未来のことは分からないし、番いにはなれないけれど、彼はこんなにもシェイラのことを大切にしてくれている。これ以上を望むのは、きっと贅沢すぎるのだ。