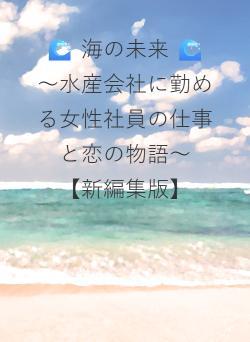最上極
最上製薬の社長になることが約束されていた。
いや、決められていた。
一人息子である自分に他の選択肢はなかった。
「運命だからな」
親友の須尚に対していつもそう言っていたが、本当になりたい職業は製薬会社の経営者ではなかった。
クラシック・ピアノの演奏家になるのが夢だった。
幼稚園に上がった頃からピアノを習い始めてすぐに夢中になった。
特にショパンの曲が大好きだった。
暇さえあればショパンを弾いていた。
夢の中でも練習しているくらいだった。
中学生になると、音大卒の演奏家から個人レッスンを受けるようになった。
教え方の上手な先生で、褒めて褒めて褒めまくられた。
そのせいか更に練習に熱が入り、三度の飯よりもピアノという感じになった。
当然のように、ピアノ・コンクールでは何度も優勝した。
しかし、受験を控えた中学3年生の夏、習うのを止めた。
それは当然のことだった。
敷かれたレールの上を走らなければならないからだ。
だからトップクラスと評判の私立高校に入ってからも一度もピアノに触らなかった。
*
転機が訪れたのは大学入学後のサークル勧誘だった。
ジャズ演奏同好会の勧誘を受けて足を運ぶと、心地良いピアノの音が聞こえてきた。
『ジャズピアノの詩人』と呼ばれたビル・エヴァンスの有名な曲だった。
弾いていたのは丸顔のぽっちゃりとした女性で、顔にはまだあどけなさが残っていた。
ベースとドラムをバックにしたシンプルな演奏だったが、しなやかな指が紡ぐメロディーは心を捉えて離さなかった。
演奏が終わると同時に拍手をしていた。
そのくらい素晴らしかった。
彼女はちょっとはにかんだようになったが、すぐに笑みを浮かべて軽く頭を下げた。
すると、サークルの代表が彼女を紹介してくれた。
「『もがみ・えみ』さんです」
えっ、
もがみ?
同じ名字?
もしかして、
遠い親戚?
まさかね……、
ちょっと驚いたが、
そんなふりを見せないようにして自らの名前を告げた。
「俺もモガミです」
告げた途端、
彼女の目が真ん丸になった。
「わたしは『上に茂る』と書きますが、同じ漢字ですか?」
「いえ、『最も上』と書く最上です」
すると突然、笑い声が聞こえた。
見ると、サークルの代表が破顔していた。
「これは面白い。2人がバンドを組んだら〈最も上に茂る〉、つまり、一番人気の大評判のバンドになるぞ」
そして、
「もう決まりだ。これ、入会届。今書いて出して」と演奏も聞かずに押し付けられた。
余りにも強引なのでちょっと引いてしまったが、これも何かの縁だと思い直して素直に従った。
書き終わると、彼女が高校生だということを告げられた。
付属高校の軽音楽部に所属しているのだという。
大学との合同演奏会を年に2回行っているのだが、1年前から合同演奏会の連絡係をすることになって、ちょくちょく打ち合わせに来るようになったのだそうだ。
「気づいたら準メンバーのような感じになっていて、時々こうやってピアノを弾かせてもらっています」
「ピアノが上手いだけじゃなくて成績も抜群だから、推薦入学間違いないしね」
代表が自分のことのように自慢すると、彼女は謙遜するかのように首を振った。
「ところで、君はどこの学部?」
「あっ、はい、薬学部製薬学科です」
「へ~、笑美ちゃんの志望学部じゃん」
「あ、そうなんですね」
すると彼女は頷いて、「先輩、よろしくお願いします」とまだそうなったわけでもないのに親しげな視線を送ってきた。
「こちらこそ」
ほんの少し頭を下げたが、最上製薬の跡継ぎだということは言わなかった。
最上製薬の社長になることが約束されていた。
いや、決められていた。
一人息子である自分に他の選択肢はなかった。
「運命だからな」
親友の須尚に対していつもそう言っていたが、本当になりたい職業は製薬会社の経営者ではなかった。
クラシック・ピアノの演奏家になるのが夢だった。
幼稚園に上がった頃からピアノを習い始めてすぐに夢中になった。
特にショパンの曲が大好きだった。
暇さえあればショパンを弾いていた。
夢の中でも練習しているくらいだった。
中学生になると、音大卒の演奏家から個人レッスンを受けるようになった。
教え方の上手な先生で、褒めて褒めて褒めまくられた。
そのせいか更に練習に熱が入り、三度の飯よりもピアノという感じになった。
当然のように、ピアノ・コンクールでは何度も優勝した。
しかし、受験を控えた中学3年生の夏、習うのを止めた。
それは当然のことだった。
敷かれたレールの上を走らなければならないからだ。
だからトップクラスと評判の私立高校に入ってからも一度もピアノに触らなかった。
*
転機が訪れたのは大学入学後のサークル勧誘だった。
ジャズ演奏同好会の勧誘を受けて足を運ぶと、心地良いピアノの音が聞こえてきた。
『ジャズピアノの詩人』と呼ばれたビル・エヴァンスの有名な曲だった。
弾いていたのは丸顔のぽっちゃりとした女性で、顔にはまだあどけなさが残っていた。
ベースとドラムをバックにしたシンプルな演奏だったが、しなやかな指が紡ぐメロディーは心を捉えて離さなかった。
演奏が終わると同時に拍手をしていた。
そのくらい素晴らしかった。
彼女はちょっとはにかんだようになったが、すぐに笑みを浮かべて軽く頭を下げた。
すると、サークルの代表が彼女を紹介してくれた。
「『もがみ・えみ』さんです」
えっ、
もがみ?
同じ名字?
もしかして、
遠い親戚?
まさかね……、
ちょっと驚いたが、
そんなふりを見せないようにして自らの名前を告げた。
「俺もモガミです」
告げた途端、
彼女の目が真ん丸になった。
「わたしは『上に茂る』と書きますが、同じ漢字ですか?」
「いえ、『最も上』と書く最上です」
すると突然、笑い声が聞こえた。
見ると、サークルの代表が破顔していた。
「これは面白い。2人がバンドを組んだら〈最も上に茂る〉、つまり、一番人気の大評判のバンドになるぞ」
そして、
「もう決まりだ。これ、入会届。今書いて出して」と演奏も聞かずに押し付けられた。
余りにも強引なのでちょっと引いてしまったが、これも何かの縁だと思い直して素直に従った。
書き終わると、彼女が高校生だということを告げられた。
付属高校の軽音楽部に所属しているのだという。
大学との合同演奏会を年に2回行っているのだが、1年前から合同演奏会の連絡係をすることになって、ちょくちょく打ち合わせに来るようになったのだそうだ。
「気づいたら準メンバーのような感じになっていて、時々こうやってピアノを弾かせてもらっています」
「ピアノが上手いだけじゃなくて成績も抜群だから、推薦入学間違いないしね」
代表が自分のことのように自慢すると、彼女は謙遜するかのように首を振った。
「ところで、君はどこの学部?」
「あっ、はい、薬学部製薬学科です」
「へ~、笑美ちゃんの志望学部じゃん」
「あ、そうなんですね」
すると彼女は頷いて、「先輩、よろしくお願いします」とまだそうなったわけでもないのに親しげな視線を送ってきた。
「こちらこそ」
ほんの少し頭を下げたが、最上製薬の跡継ぎだということは言わなかった。