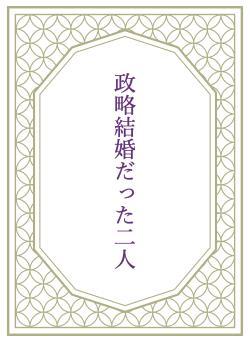目を覚ますと、猫がいた。
ベッドに仰向けに横たわる私の左脇腹近くで、金色の毛並みをした子が丸まっている。
起き抜けでぼんやりとしたまま、顔だけ動かしてそれを確認した私は、緩慢に口を開いた。
「……ミケ?」
あの毛並みには見覚えがある。
短大に通うかたわらアルバイト中の猫カフェにいるマンチカンのオス、ミケのそれだった。
キリッとした顔立ちと短い足でてちてち歩く姿のギャップがたまらないマンチカン。
穏やかで人懐っこい性格だと言われるが、ミケはツンデレ……いや、ツンツンツンツンツンデレで、普段は猫一倍つれない子だ。
「でも、お客さんの理不尽なクレームとか、店長にめっちゃ怒られたりで私が落ち込んでいたら、いつもそっと隣に寄り添ってくれる優しい子なんだよね」
そういう時のミケは、お腹に顔を埋めても肉球をクンクンしまくっても、嫌な顔一つせず好きにさせてくれた。
「今夜だって、そうだ……私が、先輩に閉店作業を押し付けられて凹んでいたから、掃除が終わるまで一緒にいてくれたんだった……」
そんな中、私は子猫の鳴き声に気づく。
扱いに困った猫を店の玄関に置いていかれることも少なくない。
ひとまず子猫の様子を窺おうと、玄関に近い窓から顔を出したその瞬間、後頭部に衝撃を受けた──までは覚えていた。
「上の階から何か落ちてきたのかな……それがぶつかって気を失った私を、誰かがベッドに運んでくれたってこと?」
いや、誰かって誰だろう。
猫カフェには、人間はもう私しか残っていなかったはずなのに。
そもそも人間用のベッドなんて、店にあっただろうか。
「頭に何かがぶつかったのに、左の脇腹の方が痛いのはなんでだろう……」
などと、釈然としないことはいくつもあったが──すぐにどうでもよくなった。
だって、愛しのミケがここにいるのだから。
ベッドに仰向けに横たわる私の左脇腹近くで、金色の毛並みをした子が丸まっている。
起き抜けでぼんやりとしたまま、顔だけ動かしてそれを確認した私は、緩慢に口を開いた。
「……ミケ?」
あの毛並みには見覚えがある。
短大に通うかたわらアルバイト中の猫カフェにいるマンチカンのオス、ミケのそれだった。
キリッとした顔立ちと短い足でてちてち歩く姿のギャップがたまらないマンチカン。
穏やかで人懐っこい性格だと言われるが、ミケはツンデレ……いや、ツンツンツンツンツンデレで、普段は猫一倍つれない子だ。
「でも、お客さんの理不尽なクレームとか、店長にめっちゃ怒られたりで私が落ち込んでいたら、いつもそっと隣に寄り添ってくれる優しい子なんだよね」
そういう時のミケは、お腹に顔を埋めても肉球をクンクンしまくっても、嫌な顔一つせず好きにさせてくれた。
「今夜だって、そうだ……私が、先輩に閉店作業を押し付けられて凹んでいたから、掃除が終わるまで一緒にいてくれたんだった……」
そんな中、私は子猫の鳴き声に気づく。
扱いに困った猫を店の玄関に置いていかれることも少なくない。
ひとまず子猫の様子を窺おうと、玄関に近い窓から顔を出したその瞬間、後頭部に衝撃を受けた──までは覚えていた。
「上の階から何か落ちてきたのかな……それがぶつかって気を失った私を、誰かがベッドに運んでくれたってこと?」
いや、誰かって誰だろう。
猫カフェには、人間はもう私しか残っていなかったはずなのに。
そもそも人間用のベッドなんて、店にあっただろうか。
「頭に何かがぶつかったのに、左の脇腹の方が痛いのはなんでだろう……」
などと、釈然としないことはいくつもあったが──すぐにどうでもよくなった。
だって、愛しのミケがここにいるのだから。