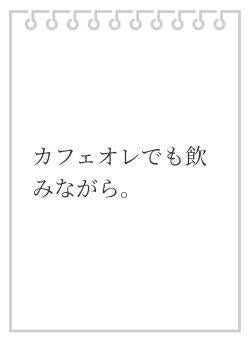モネは風を感じていた。
今日は天気が良く、窓ガラスが全部開け放たれた学校の廊下は輝かしく明るく、気持ちが良い。
モネは魔法について漠然としたイメージを考えていた。
────もし世界から魔法がなくなったら。
白いアーチのある裏庭には薔薇が咲いている。
波模様のアーチにくねった花が蔦を絡めて、庭一面に小さな花が咲いて、日差しの下の庭園は美しい。
小鳥が一羽飛んできて、白いアーチのてっぺんに止まった。
モネが花畑にしゃがむと、足音がして校舎の向こうの方からカナトが歩いてきた。
「ここに居た」
カナトがモネを見下ろした。
「学校へ残って花の世話をするより、僕の家へ来て呪文の復習でもしたら?。お前はいつも呪文を間違えるんだから。初歩の呪文なんか、間違えたらみっともないだろ。」
「だって」
花畑に座り込んだモネの前に、カナトもしゃがみ込んで、青空を見上げた。
「学校にはもう慣れた?。お前が家に居て学校に行かないって粘るから、ほとほと手を焼いたの、まだ覚えてる。来てみたら何ともなかっただろ?」
「うん」
「クラスメートと仲良くやって良い子にしてたら、僕がうちでご褒美を用意してやるよ。商店街の評判のケーキか、専門店のチョコレートを買ってやる。学校に行かないなんて、もう考えないで済むように。」
「ありがとう。」
カナトは手元に咲いていた花を自分側に引き寄せた。
「モネ。」
カナトは呼ぶと、手元にあった花を千切って、手を伸ばしてモネの耳の横に差した。
「お前と一緒に学校へ来れるのが嬉しい。屋敷でするパーティや振る舞われる贈り物やなんか、全部引き換えにしても、お前と一緒の方が良い。」
額に静かに落とされたキスに、ふわり、と風が吹く。
午後の日差しが静かに照っている。
カナトとモネが待ち合わせをしたのは交差点にある青い屋根の雑貨屋の前だった。
ショーウィンドウに、金色のバッグとドレス。脇に置いてある銀色の靴にはリボンが付いていて、足の見本にする透明な細いポールに結ばれている。
モネが欲しかったのは、ディスプレイに飾ってある銀色の靴だった。
縁に小さな星が散りばめられた模様があって、リボンにはラメが全体に入っている。
お小遣いを貯めれば買えたし、或いはカナトかシロウに言えば買ってくれたかもしれなかったが、モネは自分が靴を欲しがってる事を誰にも言わなかった。
「お待たせ。」
ディスプレイを凝視していたモネは、後ろから声をかけられて、カナトがやって来た事にやっと気が付いた。
「ほら。しゃんとしろよ。こんなに近くにいるのに、僕に気づかないなんて。」
「ごめん」
「まったく。」
プップーとクラクションを鳴らして交差点を旧式な青い車が走っていく。
カナトとモネは、手を繋いで商店街を歩いて行った。
駅は人が多く、天井が高く、プラットフォームには列車が停まっている。
「シロウと前に来たことがあるって言ってたけど、今度そうしたら許さないから。今お前の所に届けてやってるプレゼント、次やったら全部取り下げにするからな。」
奥へ進んだカナトは、駅の煉瓦塀に並んだポップスターのポスターを見てふんと鼻を鳴らした。
「つまらない。こんなもの。」
カナトが杖を一振りすると、ポスターの中の写真がひょこひょこと動き出した。
「魔法使いが居る」
「魔法使いの学校の生徒が来てるぞ」
駅に居た人々はそう囁やき合って動くポスターを物珍し気に眺めた。
「僕たちはまだ魔法使いじゃないよ。タマゴだけどね。」
カナトは腕組みをしてしれっとした顔で言った。
「アホ面で見てる奴ら、魔法が使えないなんて気の毒に。……すぐ僕の家に帰るよ、モネ。」
立ち止まっている人々の視線に目もくれず、カナトが言った。
「お前が列車の写真を撮りたいっていうから来たんだ。僕は人ゴミには居たくない。さっさとしな。」
モネは、バッグからカメラを出すと、後ろに下がって、ホームから列車の写真を1枚撮った。