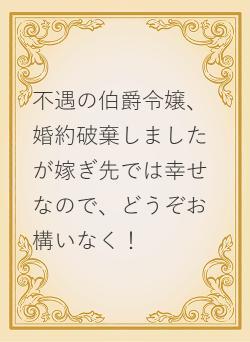お父様の執務室の前に着くと、家令が声をかけた。
「旦那様、シエラ様をお連れしました」
ここにきて、お父様に会うのに色褪せたメイド服のままに気づく。
まぁ、あの人は私の服装だって気にしないだろうけれど……。
最後に会ったのは何年前だったか? それくらい、仕事と社交とよそに愛人でもいるのだろう。
皇都の邸宅にはそうそう居ない。
ここは義母と姉、離れに兄夫婦の構成だ。そこに私も居るが、家族の扱いはされていない。
「入れ」
短い返事の後に家令がドアを開けて、私の入室を促す。
「失礼します」
執務室に入ると、父は執務机で仕事中。顔を上げることもないままに、私に言った。
「今日は話がある。とりあえず、まだ少しかかるから、座って待っていろ」
本当に、この人は家族に関心がない。
義母にも姉にも、唯一反応があるのは跡取りの兄くらいだろうか?
とりあえず言われた通り、執務室にあるソファーの入り口側に座って待つことにした。
そうすると部屋にいた侍従は居心地悪そうにしている。
普段、思いっきり無視している一応侯爵令嬢が色褪せたメイド服でソファーに座っていればね。
侍従のほうがよっぽどいい生地のお仕着せを着ているのだから。
「シエラ、なぜメイド服を着ている?」
ここにきて、仕事が落ち着き向かいのソファーに腰かけたお父様はようやく娘の格好に気づいたようだ。
「お義母様に、この服を着てメイドの仕事をしろと言われておりますので。お父様が帰宅しないここ数年はずっとこうですし、お父様の帰宅したとき以外は五歳からずっと私はメイドの扱いですよ」
今回、お義母様もお姉様も不在の時に帰宅して私を呼び出したからこのままの格好で会うことで気づいた様子。
いつもはお姉様のお下がりをサイズも合わないまま着せられて会っていたからね。
サイズも色も合わないのにドレスってだけでお義母様の私の扱いに気づかないのだから、今回くらいに見てわかる格好にならないと気づかないのでしょうね。
すでに、こんな生活を十二年続ければ血のつながりがあっても期待などとっくの昔に捨てている。
「しっかり令嬢教育をしていて、今年は社交デビューを準備すると予算も渡したはずだが……」
あぁ、それはお義母様のお飾りとお姉様の新しいドレスになったんでしょうね。
この間、新しいものが届いていたもの。
「そんなもの、とっくにお義母様とお姉様に使われていますね。私には、一つもありませんよ。そもそも、給金のいらないメイドとしてずっと使ってやるからねって日々言ってますもの」
私の言葉にお父様は絶句。
まぁ、家を家族を見ていないっていうのはこういうことよね。
だから、そろそろこの家から出ていこうと実は模索していたところだ。
十二年、メイド生活の名前だけ侯爵令嬢なんて私だけよね、きっと。
「旦那様、シエラ様をお連れしました」
ここにきて、お父様に会うのに色褪せたメイド服のままに気づく。
まぁ、あの人は私の服装だって気にしないだろうけれど……。
最後に会ったのは何年前だったか? それくらい、仕事と社交とよそに愛人でもいるのだろう。
皇都の邸宅にはそうそう居ない。
ここは義母と姉、離れに兄夫婦の構成だ。そこに私も居るが、家族の扱いはされていない。
「入れ」
短い返事の後に家令がドアを開けて、私の入室を促す。
「失礼します」
執務室に入ると、父は執務机で仕事中。顔を上げることもないままに、私に言った。
「今日は話がある。とりあえず、まだ少しかかるから、座って待っていろ」
本当に、この人は家族に関心がない。
義母にも姉にも、唯一反応があるのは跡取りの兄くらいだろうか?
とりあえず言われた通り、執務室にあるソファーの入り口側に座って待つことにした。
そうすると部屋にいた侍従は居心地悪そうにしている。
普段、思いっきり無視している一応侯爵令嬢が色褪せたメイド服でソファーに座っていればね。
侍従のほうがよっぽどいい生地のお仕着せを着ているのだから。
「シエラ、なぜメイド服を着ている?」
ここにきて、仕事が落ち着き向かいのソファーに腰かけたお父様はようやく娘の格好に気づいたようだ。
「お義母様に、この服を着てメイドの仕事をしろと言われておりますので。お父様が帰宅しないここ数年はずっとこうですし、お父様の帰宅したとき以外は五歳からずっと私はメイドの扱いですよ」
今回、お義母様もお姉様も不在の時に帰宅して私を呼び出したからこのままの格好で会うことで気づいた様子。
いつもはお姉様のお下がりをサイズも合わないまま着せられて会っていたからね。
サイズも色も合わないのにドレスってだけでお義母様の私の扱いに気づかないのだから、今回くらいに見てわかる格好にならないと気づかないのでしょうね。
すでに、こんな生活を十二年続ければ血のつながりがあっても期待などとっくの昔に捨てている。
「しっかり令嬢教育をしていて、今年は社交デビューを準備すると予算も渡したはずだが……」
あぁ、それはお義母様のお飾りとお姉様の新しいドレスになったんでしょうね。
この間、新しいものが届いていたもの。
「そんなもの、とっくにお義母様とお姉様に使われていますね。私には、一つもありませんよ。そもそも、給金のいらないメイドとしてずっと使ってやるからねって日々言ってますもの」
私の言葉にお父様は絶句。
まぁ、家を家族を見ていないっていうのはこういうことよね。
だから、そろそろこの家から出ていこうと実は模索していたところだ。
十二年、メイド生活の名前だけ侯爵令嬢なんて私だけよね、きっと。