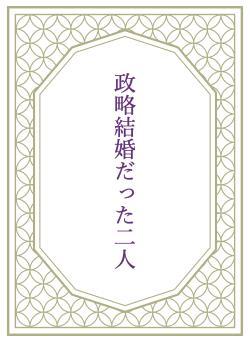素っ頓狂なジュニアの叫び声に、四人分の女性の声が返る。
イヴと、その向こうで優雅にカップを傾ける王女ロメリア、宰相の右腕クローディア、そして──
「血統なんて……ばかばかしいわ……」
今にも消え入りそうな弱々しい声でそう呟くのは、白金色の毛並みを赤く染めたオオカミ娘。
西の山際にかかった夕日が、風になびく草原と──そこに敷物を広げて和気藹々とする四人の女達を赤く彩っていた。
「──って、あんた誰!? 別人じゃん!!」
両目をまんまるにしたジュニアが、ビシリッと人差し指を突きつける。
ルーシア・メイソン公爵令嬢に。
とたん、彼女はビクンと跳び上がった。
「きゃっ、ねこ……こわい……猫こわい……」
「大丈夫ですよ、ルーシアさん。彼はまだ子猫ですからね。──ジュニアさん、大きな声を出さないでください。ルーシアさんが怯えてしまいますでしょう」
「いや、ホントに誰なのっ!?」
ジュニアは目を白黒させる。
なにしろ、さきほど『カフェ・フォルコ』の前で散々高慢に振る舞っていったルーシアが、今は耳をペタン伏せて縋るようにイヴの袖を握っているのだ。
彼女達が座る敷物の上にはバスケットが置かれ、ポットやお菓子が乗った皿が並んでいた。
イヴと、その向こうで優雅にカップを傾ける王女ロメリア、宰相の右腕クローディア、そして──
「血統なんて……ばかばかしいわ……」
今にも消え入りそうな弱々しい声でそう呟くのは、白金色の毛並みを赤く染めたオオカミ娘。
西の山際にかかった夕日が、風になびく草原と──そこに敷物を広げて和気藹々とする四人の女達を赤く彩っていた。
「──って、あんた誰!? 別人じゃん!!」
両目をまんまるにしたジュニアが、ビシリッと人差し指を突きつける。
ルーシア・メイソン公爵令嬢に。
とたん、彼女はビクンと跳び上がった。
「きゃっ、ねこ……こわい……猫こわい……」
「大丈夫ですよ、ルーシアさん。彼はまだ子猫ですからね。──ジュニアさん、大きな声を出さないでください。ルーシアさんが怯えてしまいますでしょう」
「いや、ホントに誰なのっ!?」
ジュニアは目を白黒させる。
なにしろ、さきほど『カフェ・フォルコ』の前で散々高慢に振る舞っていったルーシアが、今は耳をペタン伏せて縋るようにイヴの袖を握っているのだ。
彼女達が座る敷物の上にはバスケットが置かれ、ポットやお菓子が乗った皿が並んでいた。