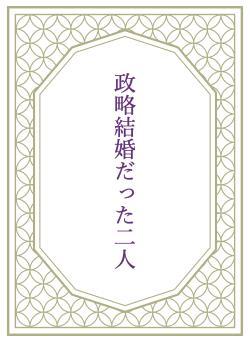「──それで? ヒト族の国の手がかりは何か掴めたのか?」
手網に入れたコーヒー豆を、オリバーが焚き火の上で振っている。
先日イヴと座ったあの切り株に、今日はその兄と並んだウィリアムは、木の棒の先で火種を突きながら質問の答えを待った。
「このコーヒーの木が立つ山の所有者の、祖父の友達の彼女の顔見知りの隣人の隣人がヒト族の末裔だった、ってことは分かったよ」
「いや、それ……コーヒーの木の所有者とは無関係にもほどがあるだろう」
「ただし、祖父の友達の彼女の顔見知りの隣人は、コーヒーの木の所有者の愛人だった」
「じゃあ、愛人の隣人がヒト族の末裔だった、でよくなかったか? 何なんだ、最初の注釈は」
ウィリアムとオリバーのそんなやりとりに、くふふふっとさもおかしそうに笑うのは、焚き火を挟んで向かいの切り株に腰を下ろしているマンチカン伯爵だ。
彼はさっきから、木の枝に刺したマシュマロを焼いている。
オリバーが焙煎しているのは、マンチカン伯爵が持ち帰り用に頼んだ新しい豆だった。
「その愛人の隣人……気のいいばあさんだったんだけど、彼女に話を聞いた限りでは、少なくとも五十年前まではヒト族の国の所在が把握できていたみたいだな」
「それ以降のことは?」
「わからないんだとさ。東の海を渡って、どこかの島に移り住んだっていう噂も耳にしたんだけどね。確証はない」
「そうか……」
ここで、パチパチと一回目の爆ぜが始まった。
すると、猫舌のマンチカン伯爵が、焼けたマショマロをふーふーしながら問う。
手網に入れたコーヒー豆を、オリバーが焚き火の上で振っている。
先日イヴと座ったあの切り株に、今日はその兄と並んだウィリアムは、木の棒の先で火種を突きながら質問の答えを待った。
「このコーヒーの木が立つ山の所有者の、祖父の友達の彼女の顔見知りの隣人の隣人がヒト族の末裔だった、ってことは分かったよ」
「いや、それ……コーヒーの木の所有者とは無関係にもほどがあるだろう」
「ただし、祖父の友達の彼女の顔見知りの隣人は、コーヒーの木の所有者の愛人だった」
「じゃあ、愛人の隣人がヒト族の末裔だった、でよくなかったか? 何なんだ、最初の注釈は」
ウィリアムとオリバーのそんなやりとりに、くふふふっとさもおかしそうに笑うのは、焚き火を挟んで向かいの切り株に腰を下ろしているマンチカン伯爵だ。
彼はさっきから、木の枝に刺したマシュマロを焼いている。
オリバーが焙煎しているのは、マンチカン伯爵が持ち帰り用に頼んだ新しい豆だった。
「その愛人の隣人……気のいいばあさんだったんだけど、彼女に話を聞いた限りでは、少なくとも五十年前まではヒト族の国の所在が把握できていたみたいだな」
「それ以降のことは?」
「わからないんだとさ。東の海を渡って、どこかの島に移り住んだっていう噂も耳にしたんだけどね。確証はない」
「そうか……」
ここで、パチパチと一回目の爆ぜが始まった。
すると、猫舌のマンチカン伯爵が、焼けたマショマロをふーふーしながら問う。